瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り
夢渓筆談 巻11より 范仲淹の飢饉対策
皇祐二年,吳中大饑,殍殣枕路,是時範文正領浙西,發粟及募民存餉,為術甚備,吳人喜競渡,好為佛事。希文乃縱民競渡,太守日出宴於湖上,自春至夏,居民空巷出遊。又召諸佛寺主首,諭之曰:“饑歳工價至賤,可以大興土木之役。”於是諸寺工作鼎興。又新敖倉吏舍,日役千夫。監司奏劾杭州不恤荒政,嬉遊不節,及公私興造,傷耗民力,文正乃自條敘所以宴遊及興造,皆欲以發有餘之財,以惠貧者。貿易飲食、工技服力之人,仰食於公私者,日無慮數萬人。荒政之施,莫此為大。是歳,兩浙唯杭州晏然,民不流徙,皆文正之惠也。歳饑發司農之粟,募民興利,近歳遂著為令。既已恤饑,因之以成就民利,此先王之美澤也。
〔訳〕皇祐二年〔1050年、宋、仁宗の年号〕呉地方は大飢饉に襲われ、道には餓死体がごろごろ転がっていた。このとき范文正〔989~1052年、仲淹〕は〔杭州の知事で〕淅江西部を治めており、穀物の放出および難民に仕事や食物を与えて救済するに当たって、非常に周到な処置をした。
呉地方の人は競渡(ボートレース)好き、仏事好きでもある。そこで、希文〔范仲淹の字〕は呉地方の人に思う存分競渡をさせ、知事みずから日毎西湖に船を浮かべて宴を開き、春から夏まで、市民は町を空っぽにして遊びで歩いた。また諸仏事の住職を集めて「飢饉の年には工賃がとても安いから、大いに土木工事をするがよかろう」と命じた。そこで寺々ではさかんに工事を始めた。また穀倉・官舎の新築をして、日に千人の人夫を使った。
監察官は、杭州の知事は飢饉対策を講ぜず、遊びに耽っており、しかも公私の建築工事を起して民力を消耗していると弾劾した。すると文正は次のように理路整然と応えた。
宴遊と建築工事をしたのは、すべて余分な財を動かして貧者にも恵もうとしたからである。商売人、飲食業者、職人、力仕事に携わる者などで、公私の宴遊・工事によって食を得た者は、日に無慮数万人にのぼる。これ以上の飢饉対策はあるまい、と。
この年両淅〔宋代には淅江は紹興のある東淅と杭州のある西淅とに分けられていた〕で、杭州だけが落ち着いていて、逃散(ちょうさん)する民もなかったのは、みな文正のお陰である。
飢饉の年に官庫の穀物を放出し、民を集めて利益になる事業を興すということは,近頃ではついに法令として成文化してしまった。飢饉から救った上に、それによって民の利をはかるということは、殷の湯王や夏の禹王のような昔の聖天子の善政にも比すべきことである。
 ※范仲淹(はんちゅうえん):字は希文、文正は諡。この飢饉の時文正は62歳であった。宋の仁宗の時の代表的名臣で、その語「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂〔天下の憂いに先んじて憂い、天下の楽しみに遅れて楽しむ〕」は有名である。
※范仲淹(はんちゅうえん):字は希文、文正は諡。この飢饉の時文正は62歳であった。宋の仁宗の時の代表的名臣で、その語「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂〔天下の憂いに先んじて憂い、天下の楽しみに遅れて楽しむ〕」は有名である。
皇祐二年,吳中大饑,殍殣枕路,是時範文正領浙西,發粟及募民存餉,為術甚備,吳人喜競渡,好為佛事。希文乃縱民競渡,太守日出宴於湖上,自春至夏,居民空巷出遊。又召諸佛寺主首,諭之曰:“饑歳工價至賤,可以大興土木之役。”於是諸寺工作鼎興。又新敖倉吏舍,日役千夫。監司奏劾杭州不恤荒政,嬉遊不節,及公私興造,傷耗民力,文正乃自條敘所以宴遊及興造,皆欲以發有餘之財,以惠貧者。貿易飲食、工技服力之人,仰食於公私者,日無慮數萬人。荒政之施,莫此為大。是歳,兩浙唯杭州晏然,民不流徙,皆文正之惠也。歳饑發司農之粟,募民興利,近歳遂著為令。既已恤饑,因之以成就民利,此先王之美澤也。
〔訳〕皇祐二年〔1050年、宋、仁宗の年号〕呉地方は大飢饉に襲われ、道には餓死体がごろごろ転がっていた。このとき范文正〔989~1052年、仲淹〕は〔杭州の知事で〕淅江西部を治めており、穀物の放出および難民に仕事や食物を与えて救済するに当たって、非常に周到な処置をした。
呉地方の人は競渡(ボートレース)好き、仏事好きでもある。そこで、希文〔范仲淹の字〕は呉地方の人に思う存分競渡をさせ、知事みずから日毎西湖に船を浮かべて宴を開き、春から夏まで、市民は町を空っぽにして遊びで歩いた。また諸仏事の住職を集めて「飢饉の年には工賃がとても安いから、大いに土木工事をするがよかろう」と命じた。そこで寺々ではさかんに工事を始めた。また穀倉・官舎の新築をして、日に千人の人夫を使った。
監察官は、杭州の知事は飢饉対策を講ぜず、遊びに耽っており、しかも公私の建築工事を起して民力を消耗していると弾劾した。すると文正は次のように理路整然と応えた。
宴遊と建築工事をしたのは、すべて余分な財を動かして貧者にも恵もうとしたからである。商売人、飲食業者、職人、力仕事に携わる者などで、公私の宴遊・工事によって食を得た者は、日に無慮数万人にのぼる。これ以上の飢饉対策はあるまい、と。
この年両淅〔宋代には淅江は紹興のある東淅と杭州のある西淅とに分けられていた〕で、杭州だけが落ち着いていて、逃散(ちょうさん)する民もなかったのは、みな文正のお陰である。
飢饉の年に官庫の穀物を放出し、民を集めて利益になる事業を興すということは,近頃ではついに法令として成文化してしまった。飢饉から救った上に、それによって民の利をはかるということは、殷の湯王や夏の禹王のような昔の聖天子の善政にも比すべきことである。
昨夜の内に3通のメールあり。
「日高先生、メールありがとうございます。/まだ、なんとも信じ難く、何も感じないというような感覚です。少年野球関係の方が大勢いらしていたので、お通夜もだれかのお父さんが亡くなったかのような錯覚にとらわれ、あまりちゃんとお別れを言えなかったように思います。/3人のお子さんに恵まれ、お孫さんまでいらして、前野さんはきっと幸せな人生を過ごされたことと思います。/短かったけれど、いつも全力で生きていた。私は、そう信じています。Y子」
「日高 先生、メール・写真ありがとうございます。/マイチの思い出は、やはり臨海での水泳部長です。
高校生のいつもニコニコしているマイチが私の中のマイチです。/まだ信じられなくて深い悲しみの中で初めての塾友の旅立ちをかみしめております。/御礼まで A美」
「日高先生、メールとお写真ありがとうございました。/マイチの訃報は、悲しいというより悔しいです。/追悼文を書いておきます。 Ⅰ朗」
夢渓筆談巻11より 劉晏式米価対策
劉晏掌南計、數百裏外物價高下、即日知之。人有得晏一事、余在三司時、嘗行之於東南、每歳發運司和糴米於郡縣、未知價之高下、須先具價申稟、然後視其貴賤、貴則寡取、賤則取盈。盡得郡縣之價、方能契數行下、比至則粟價已增、所以常得貴。各得其宜、已無極售。晏法則令多粟通途郡縣、以數十歳糴價與所糴粟數高下、各類五等、具籍於主者。今屬發運司。粟價才定、更不申稟、即時廩收、但第一價則糴五數、第五價即糴第一數、第二價則糴第四數、第四價即糴第二數、乃即馳遞報發運司。如此、粟賤之地、自糴盡極數:其余節級、各得其宜、已無極售。發運司仍會諸郡所糴之數計之、若過於多、則損貴與遠者;尚少、則增賤與近者。自此粟價未嘗失時;各當本處豐儉、即日知價。信皆有術。
〔訳〕劉晏が国家の財政を司っていたとき、数百里外の物価の高低をその日の内に掴んでいた。じつは晏のしたようなことは誰でもできるのだ。わたしが三司につとめていたとき、東南地方〔江准地方〕でこれをやってみたことがある。
毎年、初運司が国庫の金を出して民間の米を郡県から買い入れる場合、まだ価格の高低をつかんでいないのに、各郡県から価格を申告させ、そこでその価格の高下をみて、高いのは買い入れを少なくし、安いのは大量買い入れることにきめていた。こうしてすべての郡県の価格がでそろったところで買い入れ数量を決定して各郡県に通達すると、その時にはもう穀物の価格は高くなっているから、いつも高価で買い入れることになってしまう。
晏の方法は、多量の穀物を郡県に運び集めさせるに当たって、数十年間の買入価格に照らして、買い入れる穀物の数量を、高下各五等に分けて、主官者――いまは発運司に属する――に記録させておいて、当座の穀物買い入れ価格を決めると、価格を民間から申し出などさせないで、すぐに買い入れてしまうのである。その場合、一番高価なものの買入量は最少量の第五位、五番目の最低価なものの買入量は最多量の第一位、二番目に高いものの買入量は第四位、四番目に高いものの買入量は第二位として、すぐ発運司に急報する。このようになれば、穀物の安い土地では自然と買入量が最も多く、その他は各段階で適当量を買い入れることができ、天上値段で買い入れてしまうことはない。発運司はなお諸郡が買い入れる量を合計し、もし多すぎるようであれば、高価なものと遠方のものの買入量を減じ、少ないようであれば、安価なものと近くのものの買入量を増す。こうしてから穀物の価格は当を失することもなく、各々の土地における産量に相応するものとなり、即日にして価格を知ることができた。このようにいい方法がちゃんとあるのである。
 ※劉晏〔715?~780年〕は唐代中葉の人、肅宗・代宗・徳宗3帝に仕え、塩鉄・租庸などを担当した有能な経済官僚であった。特に代宗の時、安録山の乱後の財政立て直しに当たり、戸部侍郎となり天下の財計をつかさどり、塩運については十五年間担当して縦横に才腕を振るい、大暦〔766~779年〕末には塩利千二百万貫を得て歳入の半ばを満たした。徳宗が立ち彼と意見の合わぬ楊炎〔727~781年〕が宰相となるに及んで、その讒言のため死を賜り、家族は嶺安に流され、連座する者も数十人にのぼったが、当時の人人はみなこれは無実の罪であるといったという。
※劉晏〔715?~780年〕は唐代中葉の人、肅宗・代宗・徳宗3帝に仕え、塩鉄・租庸などを担当した有能な経済官僚であった。特に代宗の時、安録山の乱後の財政立て直しに当たり、戸部侍郎となり天下の財計をつかさどり、塩運については十五年間担当して縦横に才腕を振るい、大暦〔766~779年〕末には塩利千二百万貫を得て歳入の半ばを満たした。徳宗が立ち彼と意見の合わぬ楊炎〔727~781年〕が宰相となるに及んで、その讒言のため死を賜り、家族は嶺安に流され、連座する者も数十人にのぼったが、当時の人人はみなこれは無実の罪であるといったという。
※三司:宋代において、全国の財務行政を管理する役所で、塩鉄司〔塩と鉄の専売を担当〕、度支司〔財政収支の管理を担当〕、戸部〔税取立ての基礎となる戸籍をつかさどる〕の3部門に分かれており、三司使がこれを総括した。沈括は神宗の煕寧年間に権三司使をつとめている。
※発運司:宋代に主要米穀産地である華中・江南各地の財貨を調べ、首都に租税として米穀等を漕運する事務を担当する役所の長官のこと。
「日高先生、メールありがとうございます。/まだ、なんとも信じ難く、何も感じないというような感覚です。少年野球関係の方が大勢いらしていたので、お通夜もだれかのお父さんが亡くなったかのような錯覚にとらわれ、あまりちゃんとお別れを言えなかったように思います。/3人のお子さんに恵まれ、お孫さんまでいらして、前野さんはきっと幸せな人生を過ごされたことと思います。/短かったけれど、いつも全力で生きていた。私は、そう信じています。Y子」
「日高 先生、メール・写真ありがとうございます。/マイチの思い出は、やはり臨海での水泳部長です。
高校生のいつもニコニコしているマイチが私の中のマイチです。/まだ信じられなくて深い悲しみの中で初めての塾友の旅立ちをかみしめております。/御礼まで A美」
「日高先生、メールとお写真ありがとうございました。/マイチの訃報は、悲しいというより悔しいです。/追悼文を書いておきます。 Ⅰ朗」
夢渓筆談巻11より 劉晏式米価対策
劉晏掌南計、數百裏外物價高下、即日知之。人有得晏一事、余在三司時、嘗行之於東南、每歳發運司和糴米於郡縣、未知價之高下、須先具價申稟、然後視其貴賤、貴則寡取、賤則取盈。盡得郡縣之價、方能契數行下、比至則粟價已增、所以常得貴。各得其宜、已無極售。晏法則令多粟通途郡縣、以數十歳糴價與所糴粟數高下、各類五等、具籍於主者。今屬發運司。粟價才定、更不申稟、即時廩收、但第一價則糴五數、第五價即糴第一數、第二價則糴第四數、第四價即糴第二數、乃即馳遞報發運司。如此、粟賤之地、自糴盡極數:其余節級、各得其宜、已無極售。發運司仍會諸郡所糴之數計之、若過於多、則損貴與遠者;尚少、則增賤與近者。自此粟價未嘗失時;各當本處豐儉、即日知價。信皆有術。
〔訳〕劉晏が国家の財政を司っていたとき、数百里外の物価の高低をその日の内に掴んでいた。じつは晏のしたようなことは誰でもできるのだ。わたしが三司につとめていたとき、東南地方〔江准地方〕でこれをやってみたことがある。
毎年、初運司が国庫の金を出して民間の米を郡県から買い入れる場合、まだ価格の高低をつかんでいないのに、各郡県から価格を申告させ、そこでその価格の高下をみて、高いのは買い入れを少なくし、安いのは大量買い入れることにきめていた。こうしてすべての郡県の価格がでそろったところで買い入れ数量を決定して各郡県に通達すると、その時にはもう穀物の価格は高くなっているから、いつも高価で買い入れることになってしまう。
晏の方法は、多量の穀物を郡県に運び集めさせるに当たって、数十年間の買入価格に照らして、買い入れる穀物の数量を、高下各五等に分けて、主官者――いまは発運司に属する――に記録させておいて、当座の穀物買い入れ価格を決めると、価格を民間から申し出などさせないで、すぐに買い入れてしまうのである。その場合、一番高価なものの買入量は最少量の第五位、五番目の最低価なものの買入量は最多量の第一位、二番目に高いものの買入量は第四位、四番目に高いものの買入量は第二位として、すぐ発運司に急報する。このようになれば、穀物の安い土地では自然と買入量が最も多く、その他は各段階で適当量を買い入れることができ、天上値段で買い入れてしまうことはない。発運司はなお諸郡が買い入れる量を合計し、もし多すぎるようであれば、高価なものと遠方のものの買入量を減じ、少ないようであれば、安価なものと近くのものの買入量を増す。こうしてから穀物の価格は当を失することもなく、各々の土地における産量に相応するものとなり、即日にして価格を知ることができた。このようにいい方法がちゃんとあるのである。
※三司:宋代において、全国の財務行政を管理する役所で、塩鉄司〔塩と鉄の専売を担当〕、度支司〔財政収支の管理を担当〕、戸部〔税取立ての基礎となる戸籍をつかさどる〕の3部門に分かれており、三司使がこれを総括した。沈括は神宗の煕寧年間に権三司使をつとめている。
※発運司:宋代に主要米穀産地である華中・江南各地の財貨を調べ、首都に租税として米穀等を漕運する事務を担当する役所の長官のこと。
「2月7日の通夜と8日の告別式に参加してきました。/通夜には村井正太郎先生が、鳥取県の大山から駆けつけてくれました。ケンツも岩城さん・横山さん・青木さん・平瀬さんも大勢の人たちが参列してくださいました。みんな涙・涙でした。夜9時過ぎまで、マイチの思い出話をして偲びました。/8日の告別式には、荒木田君、沖縄出張していた木島君も参加してくれました。みんなを代表して、ナベちゃん・クリちゃん・チャキちゃんが火葬場まで行ってくれました。/みんなの思いはそれぞれで語りつくすことは出来ません。皆さんの思いを馳せた追悼文集でもできたらいいなあと思っていますが、如何なものでしょう。/先ずは、マイチの通夜と告別式の報告旁当日の写真貼付まで 日高 節夫」
通夜・告別式に参加した塾友にもこれらの写真を貼付したメールを送った。
「前野祐二君の通夜・告別式にご出席くださり、ありがとう。改めてマイチの仁徳に頭が下がります。/マイチの事は語っても語っても尽きぬことと思います。出来得れば追悼の冊子でも作りたい気持ちです。/先ずは、写真貼付のうえ、御礼まで 日高 節夫」
アドレス変更のためか、メールが満タンになっているのか、届かなかった方が何件あったが、
sechin@nethome.ne.jp に送信してくだされば、貼付送信できるので連絡メールをよこされたし。
告別式の日通夜の全員写真を持参した所、お別れの時、ナベちゃんがこの写真をマイチのお棺の中に入れてマエチにも持って旅立ってもらった。
TI氏から、早速メールを戴く。曰く「日高節夫先生/一昨日はマイチの通夜席でお目にかかるという残念な場面でございました。/昨日の告別式は、小生仕事の調整が付かず失礼いたしました。/それにしても彼の人徳が偲ばれる式であったと感じました。/先輩・友人・仲間・教え子と多くの方が参列され、生前の彼の人柄がよく伺い知ることが出来ました。/日高先生、可愛い教え子が先立ち深い悲しみにあることとは存じますが、ご自愛いただき今後もマイチの素晴らしい人柄を後世の語りべとなっていただきたくお願い申し上げます。/取り急ぎ御礼申し上げます。 TI拝」
アラリンからメールが入った。曰く、「日高先生/詳細な報告、有難うございます。/本当に あの健康優良児だった彼が、亡くなるとは思ってもいませんでした。/それにしても 医師からの通知を聞いて、3年間 家族以外へ伝えなかった 意思の強さに驚いています。/突然の事故などと違い、その3年間は かえって過酷なものでしょうし、彼の心境は 察し出来ません。/兎に角 和子さんへ手紙を送るつもりですが、多少 落ち着いてからにしようと思います。/心から ご冥福を祈ります。合掌/A」
「前野祐二君の通夜・告別式にご出席くださり、ありがとう。改めてマイチの仁徳に頭が下がります。/マイチの事は語っても語っても尽きぬことと思います。出来得れば追悼の冊子でも作りたい気持ちです。/先ずは、写真貼付のうえ、御礼まで 日高 節夫」
アドレス変更のためか、メールが満タンになっているのか、届かなかった方が何件あったが、
sechin@nethome.ne.jp に送信してくだされば、貼付送信できるので連絡メールをよこされたし。
告別式の日通夜の全員写真を持参した所、お別れの時、ナベちゃんがこの写真をマイチのお棺の中に入れてマエチにも持って旅立ってもらった。
TI氏から、早速メールを戴く。曰く「日高節夫先生/一昨日はマイチの通夜席でお目にかかるという残念な場面でございました。/昨日の告別式は、小生仕事の調整が付かず失礼いたしました。/それにしても彼の人徳が偲ばれる式であったと感じました。/先輩・友人・仲間・教え子と多くの方が参列され、生前の彼の人柄がよく伺い知ることが出来ました。/日高先生、可愛い教え子が先立ち深い悲しみにあることとは存じますが、ご自愛いただき今後もマイチの素晴らしい人柄を後世の語りべとなっていただきたくお願い申し上げます。/取り急ぎ御礼申し上げます。 TI拝」
アラリンからメールが入った。曰く、「日高先生/詳細な報告、有難うございます。/本当に あの健康優良児だった彼が、亡くなるとは思ってもいませんでした。/それにしても 医師からの通知を聞いて、3年間 家族以外へ伝えなかった 意思の強さに驚いています。/突然の事故などと違い、その3年間は かえって過酷なものでしょうし、彼の心境は 察し出来ません。/兎に角 和子さんへ手紙を送るつもりですが、多少 落ち着いてからにしようと思います。/心から ご冥福を祈ります。合掌/A」
夢渓筆談巻11 赫連の城
延州故豐林縣城、赫連勃勃所築、至今謂之赫連城。緊密如石、劚之皆火出。其城不甚厚、但馬面極長且密。予親使人步之、馬面皆長四丈、相去六七丈、以其馬面密、則城不須太厚、人力亦難兼也。余曾親見攻城、若馬面長則可反射城下攻者、兼密則矢石相及、敵人至城下、則四面矢石臨之。須使敵人不能到城下、乃為良法。今邊城雖厚、而馬面極短且疏、若敵人可到城下、則城雖厚。終為危道。其間更多其角、謂之團敵、此尤無益。全藉倚樓角以發矢石、以覆護城腳。但使敵人備處多、則自不可存立。赫連之城、深可為法也。
〔訳〕延州(今の陝西省延安)にある旧豊林県城は、赫連勃勃の築いたもので、いまでも赫連城と呼んでいる。〔土を固めた城壁の〕堅固さは石のようで、どこを刃物で切りつけても火花が散る。城壁はそう厚いものではないが、突出部が長く伸びており、かつその数が多い。わたしがみずから歩測させてみたところ、突出部の長さはみな四丈〔約12m〕,間隔は六・七丈〔20m前後〕であった。突出部が数多くあれば城壁はあまり厚くする必要はないし、攻め手には攻略しにくいだろう。わたしも攻略戦を観戦したことがあるが、城壁の突出部が長いと、城壁の真下に攻め寄せてきた者を側面から射ることが出来るし、その上突出部の数が多ければ、〔どこも〕矢や石の射程投擲距離範囲内にカバーでき、敵が城壁の下に押し寄せると、まわりから矢や石が飛んで来ることになる。敵を城壁に寄せ付けないのにまことによい方法である。いま国境に築かれている城の城壁は厚さは厚いが、突出部はとても短くて数も少ない。もし敵に城壁の下に取り付かれたら、城壁が厚くても危ないものだ。そのうえ角を削って丸くして「団敵」と呼んでいるものが多いが、これは全く無益であり、楼角(やぐら)だけを頼りにして、そこから矢や石を放って城壁の下を守ろうとするものである。だがこれでは敵にみずからを守る死角を多く与えることになり、自分のほうが危ない。赫連の作った城を大いに手本とすべきだ。
 ※赫連勃勃(?~425年)は、五胡十六国のひとつである夏の建国の主である。匈奴族で、姓の赫連は古トルコ語で天を指すköklerに由来すると考えられているという。夏は東晋時代、北方では北魏と対立する強国で陝西省北部を本拠地とした。勃勃は無定河の上流、納領(ナリン)、西拉烏蘇(シリウス)の二川の合流点に、「統万(トウマン)城」という都城を築いた時にも、土を蒸して城壁を固めたが、もしその土がよく固まらなくて、錐で突いて少しでも刺さろうものならその工人を殺して城壁に埋め込んでしまうという苛酷さであったと「晋書」に述べられているという。
※赫連勃勃(?~425年)は、五胡十六国のひとつである夏の建国の主である。匈奴族で、姓の赫連は古トルコ語で天を指すköklerに由来すると考えられているという。夏は東晋時代、北方では北魏と対立する強国で陝西省北部を本拠地とした。勃勃は無定河の上流、納領(ナリン)、西拉烏蘇(シリウス)の二川の合流点に、「統万(トウマン)城」という都城を築いた時にも、土を蒸して城壁を固めたが、もしその土がよく固まらなくて、錐で突いて少しでも刺さろうものならその工人を殺して城壁に埋め込んでしまうという苛酷さであったと「晋書」に述べられているという。
朝が来れば、必ず夜が来るように生には必ず死がある。逝く者は再びは返り来ぬように、死せる者の再び生き返ることはない。
人として生を欲しない者があろうか。しかしてこれを永遠に生き返させることは出来ない。
人として逝く者を傷(いた)まない者はない。しかしてこれを留めて逝かせないでおくことは出来ない。
久遠に生き長らえさせることが出来ないのならば、生は欲しないがよい。
逝かせないでおくことができないのならば、逝く者は傷まないがよい。
死は必ずしも傷まず、生あることこそ傷むべきや? 逝く者を傷むことなかれ、願わくば生をこそ傷まん。
今夕、H寺においてマイチのお通夜に出かける。
延州故豐林縣城、赫連勃勃所築、至今謂之赫連城。緊密如石、劚之皆火出。其城不甚厚、但馬面極長且密。予親使人步之、馬面皆長四丈、相去六七丈、以其馬面密、則城不須太厚、人力亦難兼也。余曾親見攻城、若馬面長則可反射城下攻者、兼密則矢石相及、敵人至城下、則四面矢石臨之。須使敵人不能到城下、乃為良法。今邊城雖厚、而馬面極短且疏、若敵人可到城下、則城雖厚。終為危道。其間更多其角、謂之團敵、此尤無益。全藉倚樓角以發矢石、以覆護城腳。但使敵人備處多、則自不可存立。赫連之城、深可為法也。
〔訳〕延州(今の陝西省延安)にある旧豊林県城は、赫連勃勃の築いたもので、いまでも赫連城と呼んでいる。〔土を固めた城壁の〕堅固さは石のようで、どこを刃物で切りつけても火花が散る。城壁はそう厚いものではないが、突出部が長く伸びており、かつその数が多い。わたしがみずから歩測させてみたところ、突出部の長さはみな四丈〔約12m〕,間隔は六・七丈〔20m前後〕であった。突出部が数多くあれば城壁はあまり厚くする必要はないし、攻め手には攻略しにくいだろう。わたしも攻略戦を観戦したことがあるが、城壁の突出部が長いと、城壁の真下に攻め寄せてきた者を側面から射ることが出来るし、その上突出部の数が多ければ、〔どこも〕矢や石の射程投擲距離範囲内にカバーでき、敵が城壁の下に押し寄せると、まわりから矢や石が飛んで来ることになる。敵を城壁に寄せ付けないのにまことによい方法である。いま国境に築かれている城の城壁は厚さは厚いが、突出部はとても短くて数も少ない。もし敵に城壁の下に取り付かれたら、城壁が厚くても危ないものだ。そのうえ角を削って丸くして「団敵」と呼んでいるものが多いが、これは全く無益であり、楼角(やぐら)だけを頼りにして、そこから矢や石を放って城壁の下を守ろうとするものである。だがこれでは敵にみずからを守る死角を多く与えることになり、自分のほうが危ない。赫連の作った城を大いに手本とすべきだ。
朝が来れば、必ず夜が来るように生には必ず死がある。逝く者は再びは返り来ぬように、死せる者の再び生き返ることはない。
人として生を欲しない者があろうか。しかしてこれを永遠に生き返させることは出来ない。
人として逝く者を傷(いた)まない者はない。しかしてこれを留めて逝かせないでおくことは出来ない。
久遠に生き長らえさせることが出来ないのならば、生は欲しないがよい。
逝かせないでおくことができないのならば、逝く者は傷まないがよい。
死は必ずしも傷まず、生あることこそ傷むべきや? 逝く者を傷むことなかれ、願わくば生をこそ傷まん。
今夕、H寺においてマイチのお通夜に出かける。
夢渓筆談巻10 鶴のたより
林逋隱居杭州孤山、常畜兩鶴、縱之則飛入雲霄、盤旋久之、復入籠中。逋常泛小艇、遊西湖諸寺。有客至逋所居、則一童子出應門、延客坐、為開籠縱鶴。良久、逋必棹小船而歸。蓋嘗以鶴飛為驗也。逋高逸倨傲、多所學、唯不能棋。常謂人曰:“逋世間事皆能之、唯不能擔糞與著棋。”
〔訳〕林逋は杭州の孤算山に隠居し、いつも二羽の鶴を飼っていて、空に放ち雲の中までぐるぐると長いこと飛び回らせては籠に入れるのであった。逋はまた小舟を浮かべて西湖の寺巡りをするのが常であった。客が逋の所へにやって来ると、童子が対応に出て来て、客を召じ入れ、籠を開いて鶴を放つ。と、やがて逋が必ず小舟に掉さして帰ってくる。鶴を飛ばして来客のしるしにしていたからである。
彼は趣味が高く我を通す性格であったから、いろいろな学芸を身につけていたのに碁だけはやらず、いつも人に「わしは世間のことはみな出来るが、ただ肥え担ぎと碁だけは出来ん」と言っていた。
 ※林逋〔967~1028年〕は、銭塘〔淅江省・杭州〕の人。独身で杭州西湖北岸に近い小島である孤山に隠居所を作り一生を終えた。梅300本を植え、鶴を飼う風流三昧の暮らしをしたが、詩人としてもすぐれ、人柄も清らかだったので、世人は「梅を妻とし鶴を子としている」といい尊敬した。和靖先生というのは仁宗が彼に賜った諡である。
※林逋〔967~1028年〕は、銭塘〔淅江省・杭州〕の人。独身で杭州西湖北岸に近い小島である孤山に隠居所を作り一生を終えた。梅300本を植え、鶴を飼う風流三昧の暮らしをしたが、詩人としてもすぐれ、人柄も清らかだったので、世人は「梅を妻とし鶴を子としている」といい尊敬した。和靖先生というのは仁宗が彼に賜った諡である。
山園小梅 林逋 山園の小梅
衆芳揺落独嬋妍 衆芳 揺落して 独(ひと)り嬋妍たり
占尽風情向小園 小園にて 風情を占め尽くす
疎影横斜水清浅 疎影 横斜して 水 清浅
暗香浮動月黄昏 暗香 浮動して 月 黄昏
霜禽欲下先偸眼 霜禽 下らんと欲して 先ず眼を偸む
粉蝶如知合断魂 粉蝶 如(も)し知らば 合(まさ)に魂を断つべし
幸有微吟可相狎 幸に微吟の相い狎(な)るべき有り
不須檀板共金樽 須(もち)いず 檀板と金樽とを
 〔訳〕いろいろな花が散ってしまった後で、梅だけがあでやかに咲き誇り、
〔訳〕いろいろな花が散ってしまった後で、梅だけがあでやかに咲き誇り、
ささやかな庭の風情を独り占めしている。
咲き初めて葉もまばらな枝の影を、清く浅い水の上に横に斜めに落とし、
月もおぼろな黄昏時になると、香りがどことも知れず、ほのかにただよう。
霜夜の小鳥が降り立とうとして、まずそっと流し目を向ける。
白い蝶がもしこの花のことを知れば、きっと魂を奪われてうっとりするに違いない。
幸いに、私の小声の詩吟を梅はかねがね好いてくれているから、
いまさら歌舞音曲も宴会もいりはしない。
林逋隱居杭州孤山、常畜兩鶴、縱之則飛入雲霄、盤旋久之、復入籠中。逋常泛小艇、遊西湖諸寺。有客至逋所居、則一童子出應門、延客坐、為開籠縱鶴。良久、逋必棹小船而歸。蓋嘗以鶴飛為驗也。逋高逸倨傲、多所學、唯不能棋。常謂人曰:“逋世間事皆能之、唯不能擔糞與著棋。”
〔訳〕林逋は杭州の孤算山に隠居し、いつも二羽の鶴を飼っていて、空に放ち雲の中までぐるぐると長いこと飛び回らせては籠に入れるのであった。逋はまた小舟を浮かべて西湖の寺巡りをするのが常であった。客が逋の所へにやって来ると、童子が対応に出て来て、客を召じ入れ、籠を開いて鶴を放つ。と、やがて逋が必ず小舟に掉さして帰ってくる。鶴を飛ばして来客のしるしにしていたからである。
彼は趣味が高く我を通す性格であったから、いろいろな学芸を身につけていたのに碁だけはやらず、いつも人に「わしは世間のことはみな出来るが、ただ肥え担ぎと碁だけは出来ん」と言っていた。
山園小梅 林逋 山園の小梅
衆芳揺落独嬋妍 衆芳 揺落して 独(ひと)り嬋妍たり
占尽風情向小園 小園にて 風情を占め尽くす
疎影横斜水清浅 疎影 横斜して 水 清浅
暗香浮動月黄昏 暗香 浮動して 月 黄昏
霜禽欲下先偸眼 霜禽 下らんと欲して 先ず眼を偸む
粉蝶如知合断魂 粉蝶 如(も)し知らば 合(まさ)に魂を断つべし
幸有微吟可相狎 幸に微吟の相い狎(な)るべき有り
不須檀板共金樽 須(もち)いず 檀板と金樽とを
ささやかな庭の風情を独り占めしている。
咲き初めて葉もまばらな枝の影を、清く浅い水の上に横に斜めに落とし、
月もおぼろな黄昏時になると、香りがどことも知れず、ほのかにただよう。
霜夜の小鳥が降り立とうとして、まずそっと流し目を向ける。
白い蝶がもしこの花のことを知れば、きっと魂を奪われてうっとりするに違いない。
幸いに、私の小声の詩吟を梅はかねがね好いてくれているから、
いまさら歌舞音曲も宴会もいりはしない。
夢渓筆談巻9 夫婦のきずな
朝士劉廷式、本田家。鄰舍翁甚貧、有一女、約與廷式為婚。後契闊數年、廷式讀書登科、歸鄉閭。訪鄰翁、而翁已死;女因病雙瞽、家極困餓。廷式使人申前好、而女子之家辭以疾、仍以傭耕、不敢姻士大夫。廷式堅不可、“與翁有約、豈可以翁死子疾而背之?”卒與成婚。閨門極雍睦、其妻相攜而後能行、凡生數子。廷式嘗坐小譴、監司欲逐之、嘉其有美行、遂為之闊略。其後廷式管幹江州太平宮而妻死、哭之極哀。蘇子瞻愛其義、為文以美之。
〔訳〕朝廷に仕える劉廷式ももと百姓であった。隣に非常に貧しいじいさんがいて、その一人娘と廷式とは婚約をしたが、そのあと数年たって廷式は勉学の末官吏登用試験に合格した。故郷に帰って来て隣の爺さんを訪ねたところ、じいさんはすでに死んでいて、娘も病気のために両眼を失明しており、家は困窮のどん底にあった。廷式は人をやって前からの約束通り嫁を迎えることを申し入れさせた。だが娘の家では盲人だし、百姓の身分でし士大夫に嫁ぐわけにはいかぬと辞退した。だが廷式は断固として聞き入れず、じいさんと約束したのだ、じいさまが亡くなり娘が盲人になったからと言って、どうして約束にそむいていいものかといって、とうとう結婚してしまった。夫婦仲はきわめてむつまじく、妻と手に手を取ってでなければ出かけず、数人の子供をつくった。廷式がかつて小事件に連座して、司法官が免職にしようとしたときも、この善行があったことによって寛大な処置がとられた。その後、廷式は江州〔江西省九江〕にある太平宮の管理官になったが、妻に先立たれてしまい、その哀しみ振りといってはなかった。蘇東坡はその情の深さを愛して、文を作り称えた。
※劉廷式:字は得之。斉州つまり山東人で、蘇東坡と同時代の人。進士に合格した後密州〔山東省諸城県〕の通判になった。「宋史、卓行伝」にその伝は載っている。なお、蘇東坡の文およびその文に拠った「宋史」では、庭式とある。
 ※蘇軾(1031~1101年)の蘇東坡集にある『書劉庭式事』によると、妻を失ってから何年経っても庭式の妻に対する哀しみが消えずどうしても再婚しなかったので、東坡が訊ねる。
※蘇軾(1031~1101年)の蘇東坡集にある『書劉庭式事』によると、妻を失ってから何年経っても庭式の妻に対する哀しみが消えずどうしても再婚しなかったので、東坡が訊ねる。
予偶問之:「哀生於愛、愛生於色。子娶盲女、與之偕老、義也。愛從何生、哀從何出乎?」庭式曰:「吾知喪吾妻而已、有目亦吾妻也、無目亦吾妻也。 吾若緣色而生愛、緣愛而生哀、色衰愛弛、吾哀亦忘。則凡揚袂(衣袖)倚市、 目挑而心招者、皆可以為妻也耶?」
《訳》私はこれについて問うた、「哀しみは愛より生じ、愛は容色より生ずるもの。あなたが盲女を娶り、睦まじく暮らしたことは立派と言えるが、その愛は何処から生じ、その哀しみは何処から出たものか?」庭式はこたえた、「わたしは、わたしの妻を失ったのだ。目があろうがなかろうが、わたしの妻であることには変わりない。わたしがもし容色によって愛を生じ、愛によって哀しみを生じたというのであれば、容色がおとろえれば愛も弱まり、哀しみも消えてしまい、きれいな着物をひらひらさせて色目を使う姐さんでも娶ってしまうということになるのではなかろうか。」
この文の著者である沈括自身にも逸話が残っている。
沈括(しんかつ)は翰林院(かんりんいん)を振り出しに、外交軍事面でも手腕を発揮してその才名を広く知られていた。多才有能な政治家であり、博覧な学者でもあった彼にとって最大の悩みの種は後添いの張氏であった。非常に凶暴で、遼や西夏を前にして一歩もひくことのなかった沈括でさえ手を焼いた。/怒り狂った張氏が沈括を罵り殴りつけたことがある。殴るだけでは満足しなかったのか、沈括の鬚(ひげ)を引きむしるなり投げ捨てた。驚いた子供達が駆け寄って鬚を拾い上げてみれば、根元には血や肉がついている。子供達が父のために泣き叫んで許しを乞うても、張氏は一向に気にとめなかった。/沈括には先妻との間に博毅(はくき)という長男がいた。張氏はこれを追い出してしまったのだが、沈括は隠れて生活の援助を続けていた。張氏はこのことを知ると激怒し、博毅の悪逆非道ぶりを訴え出た。沈括は家庭内の不祥事を治めることができなかった責めを負って、秀州(注:現浙江省)に左遷された。/張氏の無道ぶりは限度を超えたもので、役所に乗り込んでは夫の悪口を言いふらした。家人は裸足でその後を追い、懸命にとりなすのだが聞かない。見かねた親戚の勧めもあり、張氏と別居することにした。こうして沈括の生活に平穏がもたらされた。/紹聖初年(1094)に沈括は中央に復帰した。実に十余年ぶりのことであった。/その時、張氏が病で急死した。生前の悪妻ぶりを知る人々は、葬儀の席で沈括に祝いを述べたものである。不思議なことに沈括は呆けたようになっていた。あまりにぼんやりとしすぎて、船で揚子江を渡る時にもう少しで水に落ちそうになり、周りの人に助けられたほどであった。/しばらくして、沈括も亡くなった。張氏の死からわずか一年後のことであった。/ 長い間、張氏の暴虐に苦しめられて心の落ち着く間もなかったのが、ようやく解放されたというのにどうしてこうなってしまったのだろう。思うに張氏の獰猛ぶりは並大抵ではなかった。死んでもその亡魂が沈括を苦しめ続けたのではないだろうか。 (宋 朱彧『萍州可談』より)
朝士劉廷式、本田家。鄰舍翁甚貧、有一女、約與廷式為婚。後契闊數年、廷式讀書登科、歸鄉閭。訪鄰翁、而翁已死;女因病雙瞽、家極困餓。廷式使人申前好、而女子之家辭以疾、仍以傭耕、不敢姻士大夫。廷式堅不可、“與翁有約、豈可以翁死子疾而背之?”卒與成婚。閨門極雍睦、其妻相攜而後能行、凡生數子。廷式嘗坐小譴、監司欲逐之、嘉其有美行、遂為之闊略。其後廷式管幹江州太平宮而妻死、哭之極哀。蘇子瞻愛其義、為文以美之。
〔訳〕朝廷に仕える劉廷式ももと百姓であった。隣に非常に貧しいじいさんがいて、その一人娘と廷式とは婚約をしたが、そのあと数年たって廷式は勉学の末官吏登用試験に合格した。故郷に帰って来て隣の爺さんを訪ねたところ、じいさんはすでに死んでいて、娘も病気のために両眼を失明しており、家は困窮のどん底にあった。廷式は人をやって前からの約束通り嫁を迎えることを申し入れさせた。だが娘の家では盲人だし、百姓の身分でし士大夫に嫁ぐわけにはいかぬと辞退した。だが廷式は断固として聞き入れず、じいさんと約束したのだ、じいさまが亡くなり娘が盲人になったからと言って、どうして約束にそむいていいものかといって、とうとう結婚してしまった。夫婦仲はきわめてむつまじく、妻と手に手を取ってでなければ出かけず、数人の子供をつくった。廷式がかつて小事件に連座して、司法官が免職にしようとしたときも、この善行があったことによって寛大な処置がとられた。その後、廷式は江州〔江西省九江〕にある太平宮の管理官になったが、妻に先立たれてしまい、その哀しみ振りといってはなかった。蘇東坡はその情の深さを愛して、文を作り称えた。
※劉廷式:字は得之。斉州つまり山東人で、蘇東坡と同時代の人。進士に合格した後密州〔山東省諸城県〕の通判になった。「宋史、卓行伝」にその伝は載っている。なお、蘇東坡の文およびその文に拠った「宋史」では、庭式とある。
予偶問之:「哀生於愛、愛生於色。子娶盲女、與之偕老、義也。愛從何生、哀從何出乎?」庭式曰:「吾知喪吾妻而已、有目亦吾妻也、無目亦吾妻也。 吾若緣色而生愛、緣愛而生哀、色衰愛弛、吾哀亦忘。則凡揚袂(衣袖)倚市、 目挑而心招者、皆可以為妻也耶?」
《訳》私はこれについて問うた、「哀しみは愛より生じ、愛は容色より生ずるもの。あなたが盲女を娶り、睦まじく暮らしたことは立派と言えるが、その愛は何処から生じ、その哀しみは何処から出たものか?」庭式はこたえた、「わたしは、わたしの妻を失ったのだ。目があろうがなかろうが、わたしの妻であることには変わりない。わたしがもし容色によって愛を生じ、愛によって哀しみを生じたというのであれば、容色がおとろえれば愛も弱まり、哀しみも消えてしまい、きれいな着物をひらひらさせて色目を使う姐さんでも娶ってしまうということになるのではなかろうか。」
この文の著者である沈括自身にも逸話が残っている。
沈括(しんかつ)は翰林院(かんりんいん)を振り出しに、外交軍事面でも手腕を発揮してその才名を広く知られていた。多才有能な政治家であり、博覧な学者でもあった彼にとって最大の悩みの種は後添いの張氏であった。非常に凶暴で、遼や西夏を前にして一歩もひくことのなかった沈括でさえ手を焼いた。/怒り狂った張氏が沈括を罵り殴りつけたことがある。殴るだけでは満足しなかったのか、沈括の鬚(ひげ)を引きむしるなり投げ捨てた。驚いた子供達が駆け寄って鬚を拾い上げてみれば、根元には血や肉がついている。子供達が父のために泣き叫んで許しを乞うても、張氏は一向に気にとめなかった。/沈括には先妻との間に博毅(はくき)という長男がいた。張氏はこれを追い出してしまったのだが、沈括は隠れて生活の援助を続けていた。張氏はこのことを知ると激怒し、博毅の悪逆非道ぶりを訴え出た。沈括は家庭内の不祥事を治めることができなかった責めを負って、秀州(注:現浙江省)に左遷された。/張氏の無道ぶりは限度を超えたもので、役所に乗り込んでは夫の悪口を言いふらした。家人は裸足でその後を追い、懸命にとりなすのだが聞かない。見かねた親戚の勧めもあり、張氏と別居することにした。こうして沈括の生活に平穏がもたらされた。/紹聖初年(1094)に沈括は中央に復帰した。実に十余年ぶりのことであった。/その時、張氏が病で急死した。生前の悪妻ぶりを知る人々は、葬儀の席で沈括に祝いを述べたものである。不思議なことに沈括は呆けたようになっていた。あまりにぼんやりとしすぎて、船で揚子江を渡る時にもう少しで水に落ちそうになり、周りの人に助けられたほどであった。/しばらくして、沈括も亡くなった。張氏の死からわずか一年後のことであった。/ 長い間、張氏の暴虐に苦しめられて心の落ち着く間もなかったのが、ようやく解放されたというのにどうしてこうなってしまったのだろう。思うに張氏の獰猛ぶりは並大抵ではなかった。死んでもその亡魂が沈括を苦しめ続けたのではないだろうか。 (宋 朱彧『萍州可談』より)
本日は爺の誕生日。1932年はこの日節分であったので、「節夫」と名付けられた。爺も八十歳、 ―― 傘という字は略字で「仐」書くことが出来るので ―― 八十歳を傘寿と言うのだそうだ。
昨今日本人女性の平均寿命は86.39歳、男性の平均寿命は79.64歳というから、80歳といってもさほど珍しくもあるまいが、昨年暮れ姉は86歳8か月まさに平均寿命の歳に亡くなっている。爺もまさに男性の平均寿命に達したわけだ。
府西池 白居易
柳無気力枝先動 柳 気力無くして 枝先ず動き
池有波紋氷尽開 池 波紋有りて 氷尽(ことごと)く開く
今日不知誰計会 今日知らず 誰か計会するを
春風春水一時来 春風春水 一時に来る
池には波紋が広がって 氷が皆とけてゆく
今日のこの様子は誰が一体計算したのか
春の風と春の水が一度にやって来るなんて
春たちける日よめる 紀貫之
袖ひちて むすびし水の こほれるを
春立つけふの 風やとくらむ 《古今和歌集2》
〔訳〕夏に袖が濡れて手に掬った水が、冬の間に氷ったのを、春になった今日の風が解かしているだろうか。
昨夕、ブログ集19の到着の電話があった水門会のヤントからのメールが入っていた。曰く、
「日高 節夫 様/今日は節分ですが我が家では先ほど老父婦でささやかに真似事ながら豆まきをしました。/節分の今日は貴兄の誕生日、月並みだけど傘寿おめでとうございます。これからもまだまだ達者で過ごされたし。(夕方電話のときに言うのを忘れていました。)」
水門会のN氏からも、メールが届く。曰く、
「日高 節夫 様/本日、君の80歳の誕生日。おめでとう。/足はときどき痛むようだが、頭と口はまだしゃんとしている。/どうかこれからも、元気で、われわれ同期生を勇気づけてください。/昔の徴兵適齢、つまり軍隊に徴兵されるときの同年兵に年令基準は、前年の12月1日から、その年の11月30日に生まれた男の子が、同年兵になるということを知ってから、われら同年兵の仲間はとくに懐かしい。/これからもがんばりましょう。奥様にもよろしく…。」
皆さんからのメールやコメントに励まされてこれからも大いに生き恥を晒してまいりましょう。
論語 先進篇 より
顏淵死。子曰:「噫! 天喪予!天喪予!」
顔淵が死んだ時、先生〔孔子〕は仰った。「ああ、天はこの私を亡ぼした。天はこの私を亡ぼした」
顏淵死、子哭之慟。從者曰:「子慟矣。」曰:「有慟乎? 非夫人之為慟而誰為!」
顔淵が死んだ時、先生は〔顔淵の家で〕哭の礼を行われたが〔本当に〕身を震わせて泣かれた。〔後日〕お供をした門人が、「先生は身を震わせてお泣きになりました」と申し上げると、〔先生が〕仰った。「身を震わせるほどだったかね。あれのために慟哭するのでなくて、誰のためにそんなに泣こうか」
顏淵死、門人欲厚葬之、子曰:「不可。」門人厚葬之。子曰:「回也視予猶父也、予不得視猶子也。非我也、夫二三子也。」
顔淵が死んだ時、同門の弟子たちは盛大な葬式を執行しようとした。先生は「いけない」と言われたが、弟子たちは盛大に葬式をおこなってしまった。先生が仰った。「回は〔生前〕私をまるで実の父のようにしていたものだ。ところが〔今度〕私は彼を実の子のように出来なかった。〔あんな分不相応な葬式をして私にそのような思いをさせたのは〕私の所為ではないぞ。あの〔お節介な〕弟子どもだよ」
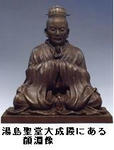
 顔回〔BC513~482年、顔淵〕は、孔子が最も深く愛し将来を嘱望した高弟であり、孔子の諸国遊説以前から孔子に師事していた人物である。顔回は、巧言令色を好まず議論で積極的に意見を述べることも殆どなかったが、寡黙な態度を保持しながら内面に徳の高さを感じさせる人物であったという。同じ論語の爲政篇には
顔回〔BC513~482年、顔淵〕は、孔子が最も深く愛し将来を嘱望した高弟であり、孔子の諸国遊説以前から孔子に師事していた人物である。顔回は、巧言令色を好まず議論で積極的に意見を述べることも殆どなかったが、寡黙な態度を保持しながら内面に徳の高さを感じさせる人物であったという。同じ論語の爲政篇には
「子曰、吾与回言終日、不違如愚、退而省其私、亦足以発、回也不愚。〔子曰く、吾回と言(かたる)ること終日、違わざること愚なるが如し。退きてその私を省(かえりみ)れば、亦(また)以って発(あき)らかにするに足れり。回は愚ならず。〕」とある。顔回は孔子よりも早く41歳でこの世を去り、最愛の弟子に先立たれた孔子は深い悲しみに襲われることになったのである。
爺がまだ国民学校6年生だった頃の国語の教科書の文を見つけたので、以下に掲載する。
《孔子と顔回》
一
「ああ、天は予(よ)をほろぼした。天は予をほろぼした。」
七十歳の孔子は、弟子顔回の死にあつて、聲をあげて泣いた。
三千人の弟子のうち、顔回ほどその師を知り、師の敎へを守り、師の敎へを實行することに心掛けた者はなかつた。これこそは、わが道を傳へ得るただ一人の弟子だと、孔子はかねてから深く信頼してゐた。その顔回が、年若くてなくなつたのである。
「ああ、天は予をほろぼした。天は予をほろぼした。」
まさに、後繼者を失つた者の悲痛な叫びでなくて何であらう。
二
十數年前にさかのぼる。孔子が、弟子たちをつれて、匡(きやう)といふところを通つた時、突然軍兵に圍まれたことがある。かつて陽虎(やうこ)といふ者が、この地でらんばうを働いた。不幸にも、孔子の顔が陽虎に似てゐたところから、匡人は孔子を取り圍んだのである。この時、おくればせにかけつけた顔回を見た孔子は、ほつとしながら、
「おお、顔回。お前は無事であつたか。死んだのではないかと心配した。」
といつた。すると顔回は、
「先生が生きていらつしやる限り、どうして私が死ねませう。」
と答へた。
孔子は五十餘歳、顔回は一靑年であつた。わが身の上の危さも忘れて、孔子は年若い顔回をひたすらに案じ、また顔回は、これほどまでその師を慕つてゐたのであつた。
三
それから數年たつて、陳(ちん)・蔡(さい)の厄があつた。孔子は楚(そ)の國へ行かうとして、弟子たちとともに陳・蔡の野を旅行した。あいにくこの地方に戰亂があつて、道ははかどらず、七日七夜、孔子も弟子も、ろくろく食ふ物がなかつた。
困難に際會すると、おのづから人の心がわかるものである。弟子たちの中には、ぶつぶつ不平をもらす者があつた。き一本な子路が、とがり聲で孔子にいつた。
「いつたい、德の修つた君子でも困られることがあるのですか。」
德のある者なら、天が助けるはずだ。助けないところを見ると、先生はまだ君子ではないのか──子路には、ひよつとすると、さういふ考へがわいたのかも知れない。孔子は平然として答へた。
「君子だつて、困る場合はある。ただ、困り方が違ふぞ。困つたら惡いことでも何でもするといふのが小人である。君子はそこが違ふ。」
子貢(しこう)といふ弟子がいつた。
「先生の道は餘りに大き過ぎます。だから、世の中が先生を受け容れて用ひようとしません。先生は、少し手かげんをなさつたらいかがでせう。」
孔子は答へた。
「細工のうまい大工が、必ず人にほめられるときまつてはゐない。ほめられないからといつて、手かげんするのが果してよい大工だらうか。君子も同じことだ。道の修つた者が、必ず人に用ひられるとはきまつてゐない。といつて手かげんをしたら、人に用ひられるためには、道はどうでもよいといふことになりはしないか。」
顔回は師を慰めるやうにいつた。
「世の中に容れられないといふことは、何でもありません。今の亂れた世に容れられなければこそ、ほんたうに先生の大きいことがわかります。道を修めないのは君子の恥でございますが、君子を容れないのは世の中の恥でございます。」
このことばが、孔子をどんなに滿足させたことか。
四
孔子は、弟子に道を説くのに、弟子の才能に應じてわかる程度に敎へた。
孔子の理想とする「仁」についても、ある者には「人を愛することだ。」といひ、ある者には「人のわる口をいはないことだ。」と説き、ある者には「むづかしいことを先にすることだ。」と敎へた。いづれも「仁」の一部の説明で、その行ひやすい方面を述べたのである。ところで顔回には、
「己に克(か)つて禮に復(かへ)るのが仁である。」
と敎へた。あらゆる欲望にうちかつて、禮を實行せよといふのである。その實行方法として、
「非禮は見るな。非禮は聞くな。非禮はいふな。非禮に動くな。」
と敎へた。朝起きるから夜寝るまで、見ること、聞くこと、いふこと、行ふこと、いつさい禮に從ひ、禮にかなへよといふのである。ここに、「仁」の全體が説かれてゐる。さうして、顔回なればこそ、この最もむづかしい敎へを、そのまま實行することができたのである。
五
孔子は顔回をほめて、
「顔回は、予の前で敎へを受ける時、ただだまつてゐるので、何だかぼんやり者のやうに見える。しかし退いて一人でゐる時は、師の敎へについて何か自分で工夫をこらしてゐる。決してぼんやり者ではない。」
といつてゐる。また、
「ほかの弟子は、敎へについていろいろ質問もし、それで予を啓發してくれることがある。しかし、顔回は質問一つせず、すぐ會得して實行にかかる。かれは、一を聞いて十を知る男だ。」
ともいつてゐる。
孔子がよく顔回を知つてゐたやうに、顔回もまたよくその師を知つてゐた。顔回は孔子をたたへて、
「先生は、仰げば仰ぐほど高く、接すれば接するほど奥深いお方だ。大きな力で、ぐんぐんと人を引つぱつて行かれる。とても先生には追ひつけないから、もうよさうと思つても、やはりついて行かないではゐられない。私が力のあらん限り修養しても、先生は、いつでも更に高いところに立つておいでになる。結局、足もとにも寄りつけないと感じながら、ついて行くのである。」
といつてゐる。顔回なればこそ、偉大な孔子の全面を、よく認めることができたのである。
六
「先生が生きていらつしやる限り、どうして私が死ねませう。」
といつた顔回が、先生よりも先に死んでしまつた。ある日、魯(ろ)の哀公(あいこう)が孔子に、
「おんみの弟子のうち、最も學を好むものはだれか。」
とたづねた。孔子は、
「顔回といふ者がをりました。學を好み、過ちも二度とはしない男でございましたが、不幸にも短命でございました。」
と答へた。 国民学校国語教科書『初等科國語八』より(旧仮名遣い)
 昨日大久保病院に見舞ったマイチが、爺との面会を待っていたかのように今朝ほど5時35分帰らぬ人となった。これが宿命と言うものなら、宿命とやらを憾みに思いたい。
昨日大久保病院に見舞ったマイチが、爺との面会を待っていたかのように今朝ほど5時35分帰らぬ人となった。これが宿命と言うものなら、宿命とやらを憾みに思いたい。
人一倍元気で明るく、いつもみんなを楽しませてくれたマイチは3年程前、胃のスキルス癌で、放っておけば3ヶ月の余命、胃と周りの臓器4つを取る手術をすれば、3年生存率が50%、5年生存率が20%以下と言われたらしいが、本人の選択で手術はやめ、食事療法とサプリメントと鍼で、2年ほどは元気に何事もなく過ごしたと言う。一昨年の暮れに癌の活動が活発になったため、通院で抗がん剤治療も始めたが、やはり限界もあり、昨年10月に1ヶ月入院したという。この時点で同期の友人2・3名には知らせたらしいが、「先生には心配を掛けるのが申し訳ない」という本人の思いもあり、この爺には知らせなかったらしい。年末年始は自宅で過ごしたが、年明から病状は悪化の一途(いっと)の辿るばかり、痛みは全くなく、意識もまだはっきりしていたが、主治医からはいつ何があってもおかしくない状態と余命宣告され、この爺にも知らせてくれた次第である。心からご冥福を祈る。 合掌
顏淵死。子曰:「噫! 天喪予!天喪予!」
顔淵が死んだ時、先生〔孔子〕は仰った。「ああ、天はこの私を亡ぼした。天はこの私を亡ぼした」
顏淵死、子哭之慟。從者曰:「子慟矣。」曰:「有慟乎? 非夫人之為慟而誰為!」
顔淵が死んだ時、先生は〔顔淵の家で〕哭の礼を行われたが〔本当に〕身を震わせて泣かれた。〔後日〕お供をした門人が、「先生は身を震わせてお泣きになりました」と申し上げると、〔先生が〕仰った。「身を震わせるほどだったかね。あれのために慟哭するのでなくて、誰のためにそんなに泣こうか」
顏淵死、門人欲厚葬之、子曰:「不可。」門人厚葬之。子曰:「回也視予猶父也、予不得視猶子也。非我也、夫二三子也。」
顔淵が死んだ時、同門の弟子たちは盛大な葬式を執行しようとした。先生は「いけない」と言われたが、弟子たちは盛大に葬式をおこなってしまった。先生が仰った。「回は〔生前〕私をまるで実の父のようにしていたものだ。ところが〔今度〕私は彼を実の子のように出来なかった。〔あんな分不相応な葬式をして私にそのような思いをさせたのは〕私の所為ではないぞ。あの〔お節介な〕弟子どもだよ」
「子曰、吾与回言終日、不違如愚、退而省其私、亦足以発、回也不愚。〔子曰く、吾回と言(かたる)ること終日、違わざること愚なるが如し。退きてその私を省(かえりみ)れば、亦(また)以って発(あき)らかにするに足れり。回は愚ならず。〕」とある。顔回は孔子よりも早く41歳でこの世を去り、最愛の弟子に先立たれた孔子は深い悲しみに襲われることになったのである。
爺がまだ国民学校6年生だった頃の国語の教科書の文を見つけたので、以下に掲載する。
《孔子と顔回》
一
「ああ、天は予(よ)をほろぼした。天は予をほろぼした。」
七十歳の孔子は、弟子顔回の死にあつて、聲をあげて泣いた。
三千人の弟子のうち、顔回ほどその師を知り、師の敎へを守り、師の敎へを實行することに心掛けた者はなかつた。これこそは、わが道を傳へ得るただ一人の弟子だと、孔子はかねてから深く信頼してゐた。その顔回が、年若くてなくなつたのである。
「ああ、天は予をほろぼした。天は予をほろぼした。」
まさに、後繼者を失つた者の悲痛な叫びでなくて何であらう。
二
十數年前にさかのぼる。孔子が、弟子たちをつれて、匡(きやう)といふところを通つた時、突然軍兵に圍まれたことがある。かつて陽虎(やうこ)といふ者が、この地でらんばうを働いた。不幸にも、孔子の顔が陽虎に似てゐたところから、匡人は孔子を取り圍んだのである。この時、おくればせにかけつけた顔回を見た孔子は、ほつとしながら、
「おお、顔回。お前は無事であつたか。死んだのではないかと心配した。」
といつた。すると顔回は、
「先生が生きていらつしやる限り、どうして私が死ねませう。」
と答へた。
孔子は五十餘歳、顔回は一靑年であつた。わが身の上の危さも忘れて、孔子は年若い顔回をひたすらに案じ、また顔回は、これほどまでその師を慕つてゐたのであつた。
三
それから數年たつて、陳(ちん)・蔡(さい)の厄があつた。孔子は楚(そ)の國へ行かうとして、弟子たちとともに陳・蔡の野を旅行した。あいにくこの地方に戰亂があつて、道ははかどらず、七日七夜、孔子も弟子も、ろくろく食ふ物がなかつた。
困難に際會すると、おのづから人の心がわかるものである。弟子たちの中には、ぶつぶつ不平をもらす者があつた。き一本な子路が、とがり聲で孔子にいつた。
「いつたい、德の修つた君子でも困られることがあるのですか。」
德のある者なら、天が助けるはずだ。助けないところを見ると、先生はまだ君子ではないのか──子路には、ひよつとすると、さういふ考へがわいたのかも知れない。孔子は平然として答へた。
「君子だつて、困る場合はある。ただ、困り方が違ふぞ。困つたら惡いことでも何でもするといふのが小人である。君子はそこが違ふ。」
子貢(しこう)といふ弟子がいつた。
「先生の道は餘りに大き過ぎます。だから、世の中が先生を受け容れて用ひようとしません。先生は、少し手かげんをなさつたらいかがでせう。」
孔子は答へた。
「細工のうまい大工が、必ず人にほめられるときまつてはゐない。ほめられないからといつて、手かげんするのが果してよい大工だらうか。君子も同じことだ。道の修つた者が、必ず人に用ひられるとはきまつてゐない。といつて手かげんをしたら、人に用ひられるためには、道はどうでもよいといふことになりはしないか。」
顔回は師を慰めるやうにいつた。
「世の中に容れられないといふことは、何でもありません。今の亂れた世に容れられなければこそ、ほんたうに先生の大きいことがわかります。道を修めないのは君子の恥でございますが、君子を容れないのは世の中の恥でございます。」
このことばが、孔子をどんなに滿足させたことか。
四
孔子は、弟子に道を説くのに、弟子の才能に應じてわかる程度に敎へた。
孔子の理想とする「仁」についても、ある者には「人を愛することだ。」といひ、ある者には「人のわる口をいはないことだ。」と説き、ある者には「むづかしいことを先にすることだ。」と敎へた。いづれも「仁」の一部の説明で、その行ひやすい方面を述べたのである。ところで顔回には、
「己に克(か)つて禮に復(かへ)るのが仁である。」
と敎へた。あらゆる欲望にうちかつて、禮を實行せよといふのである。その實行方法として、
「非禮は見るな。非禮は聞くな。非禮はいふな。非禮に動くな。」
と敎へた。朝起きるから夜寝るまで、見ること、聞くこと、いふこと、行ふこと、いつさい禮に從ひ、禮にかなへよといふのである。ここに、「仁」の全體が説かれてゐる。さうして、顔回なればこそ、この最もむづかしい敎へを、そのまま實行することができたのである。
五
孔子は顔回をほめて、
「顔回は、予の前で敎へを受ける時、ただだまつてゐるので、何だかぼんやり者のやうに見える。しかし退いて一人でゐる時は、師の敎へについて何か自分で工夫をこらしてゐる。決してぼんやり者ではない。」
といつてゐる。また、
「ほかの弟子は、敎へについていろいろ質問もし、それで予を啓發してくれることがある。しかし、顔回は質問一つせず、すぐ會得して實行にかかる。かれは、一を聞いて十を知る男だ。」
ともいつてゐる。
孔子がよく顔回を知つてゐたやうに、顔回もまたよくその師を知つてゐた。顔回は孔子をたたへて、
「先生は、仰げば仰ぐほど高く、接すれば接するほど奥深いお方だ。大きな力で、ぐんぐんと人を引つぱつて行かれる。とても先生には追ひつけないから、もうよさうと思つても、やはりついて行かないではゐられない。私が力のあらん限り修養しても、先生は、いつでも更に高いところに立つておいでになる。結局、足もとにも寄りつけないと感じながら、ついて行くのである。」
といつてゐる。顔回なればこそ、偉大な孔子の全面を、よく認めることができたのである。
六
「先生が生きていらつしやる限り、どうして私が死ねませう。」
といつた顔回が、先生よりも先に死んでしまつた。ある日、魯(ろ)の哀公(あいこう)が孔子に、
「おんみの弟子のうち、最も學を好むものはだれか。」
とたづねた。孔子は、
「顔回といふ者がをりました。學を好み、過ちも二度とはしない男でございましたが、不幸にも短命でございました。」
と答へた。 国民学校国語教科書『初等科國語八』より(旧仮名遣い)
人一倍元気で明るく、いつもみんなを楽しませてくれたマイチは3年程前、胃のスキルス癌で、放っておけば3ヶ月の余命、胃と周りの臓器4つを取る手術をすれば、3年生存率が50%、5年生存率が20%以下と言われたらしいが、本人の選択で手術はやめ、食事療法とサプリメントと鍼で、2年ほどは元気に何事もなく過ごしたと言う。一昨年の暮れに癌の活動が活発になったため、通院で抗がん剤治療も始めたが、やはり限界もあり、昨年10月に1ヶ月入院したという。この時点で同期の友人2・3名には知らせたらしいが、「先生には心配を掛けるのが申し訳ない」という本人の思いもあり、この爺には知らせなかったらしい。年末年始は自宅で過ごしたが、年明から病状は悪化の一途(いっと)の辿るばかり、痛みは全くなく、意識もまだはっきりしていたが、主治医からはいつ何があってもおかしくない状態と余命宣告され、この爺にも知らせてくれた次第である。心からご冥福を祈る。 合掌
夢渓筆談巻9より 酒仙石曼卿
石曼卿喜豪飲、與布衣劉潛為友。嘗通判海州、劉潛來訪之、曼卿迎之於石闥堰、與潛劇飲。中夜酒欲竭、顧船中有醋鬥余、乃傾入酒中並飲之。至明日、酒醋俱盡。每與客痛飲、露發跣足、著械而坐。謂之“囚飲”。飲於木杪、謂之“巢飲”。以藁(?)束之、引首出飲、復就束、謂之“鱉飲”。其狂縱大率如此。廨後為一庵、常臥其間、名之日“捫虱庵”。未嘗一日不醉。仁宗愛其才、嘗對輔臣言、欲其戒酒、延年聞之。因不飲、遂成疾而卒。
〔訳〕石曼卿〔せきまんけい、992~1040年〕は豪飲するのが好きで、一平民であった劉譖(りゅうせん)と友達になった。海州〔江蘇省東海県〕の通判〔州知事に対する目付役〕になった時、劉譖が訪ねて来ると、曼卿はこれを石闥堰〔せきたつえん、陝西省長安縣西南〕まで迎えに出て譖と痛飲した。夜中に酒がなくなると、船中に酢が一升余りあるのを見つけ酒に混ぜて飲む。朝になった時には酒も酢もすっかり無くなっていた。客人と痛飲するたびに、ざんばら髪に裸足となり、械(かせ)をつけて飲むのを「囚飲(しゅういん)」と称し、梢にのぼって飲むのは「巣飲(そういん)」と称し、藁に身を包んで、頭を伸ばしては飲みまた引っ込めるのは「鼈飲(べついん)」と称するという奇抜さであった。役所の後ろに一庵をつくり、何時もそこにとぐろをまき「捫虱庵〔もんしつあん、無頓着庵、人前で虱を捻り潰すような無頓着な様を捫虱という〕と名付け、一日として酔わない日はなかった。仁宗はその才を愛して、かつて近臣に向かって、あれも酒を慎んで欲しいものだと言った事がある。延年、これを聞いて酒を絶ったところが、とうとう病気になって死んでしまった。
 ※ 石曼卿: 石延年、字は曼卿、宋の真宗・仁宗〔997~1053年〕の頃の人。豪放な性格で雄勁(ゆうけい)な文章を作り詩も巧みであったが、何と言っても酒仙としての名が最も売れていた。宋・欧楊修の『帰田録』にも石曼卿と劉譖の二酒仙が、都の酒楼で飲み比べしたことが載っている。二人は一日中一言も交わさず飲み続け、夕方になると、少しも酔った風もなく、互いに挨拶して去った、とある。
※ 石曼卿: 石延年、字は曼卿、宋の真宗・仁宗〔997~1053年〕の頃の人。豪放な性格で雄勁(ゆうけい)な文章を作り詩も巧みであったが、何と言っても酒仙としての名が最も売れていた。宋・欧楊修の『帰田録』にも石曼卿と劉譖の二酒仙が、都の酒楼で飲み比べしたことが載っている。二人は一日中一言も交わさず飲み続け、夕方になると、少しも酔った風もなく、互いに挨拶して去った、とある。
※ 劉譖 字は仲方、これもなかなかの変り種であるが、のち進士に合格して蓬莱県〔山東省〕の知事となり、鄆州〔山東省城県〕で酒友の石曼卿と飲んでいた時に母を病気で失い、死に目に合えなかったのを痛哭して世を去り、その妻も夫を慕って痛哭して世を去ったと『宋史』の伝は伝えていると言う。
石曼卿喜豪飲、與布衣劉潛為友。嘗通判海州、劉潛來訪之、曼卿迎之於石闥堰、與潛劇飲。中夜酒欲竭、顧船中有醋鬥余、乃傾入酒中並飲之。至明日、酒醋俱盡。每與客痛飲、露發跣足、著械而坐。謂之“囚飲”。飲於木杪、謂之“巢飲”。以藁(?)束之、引首出飲、復就束、謂之“鱉飲”。其狂縱大率如此。廨後為一庵、常臥其間、名之日“捫虱庵”。未嘗一日不醉。仁宗愛其才、嘗對輔臣言、欲其戒酒、延年聞之。因不飲、遂成疾而卒。
〔訳〕石曼卿〔せきまんけい、992~1040年〕は豪飲するのが好きで、一平民であった劉譖(りゅうせん)と友達になった。海州〔江蘇省東海県〕の通判〔州知事に対する目付役〕になった時、劉譖が訪ねて来ると、曼卿はこれを石闥堰〔せきたつえん、陝西省長安縣西南〕まで迎えに出て譖と痛飲した。夜中に酒がなくなると、船中に酢が一升余りあるのを見つけ酒に混ぜて飲む。朝になった時には酒も酢もすっかり無くなっていた。客人と痛飲するたびに、ざんばら髪に裸足となり、械(かせ)をつけて飲むのを「囚飲(しゅういん)」と称し、梢にのぼって飲むのは「巣飲(そういん)」と称し、藁に身を包んで、頭を伸ばしては飲みまた引っ込めるのは「鼈飲(べついん)」と称するという奇抜さであった。役所の後ろに一庵をつくり、何時もそこにとぐろをまき「捫虱庵〔もんしつあん、無頓着庵、人前で虱を捻り潰すような無頓着な様を捫虱という〕と名付け、一日として酔わない日はなかった。仁宗はその才を愛して、かつて近臣に向かって、あれも酒を慎んで欲しいものだと言った事がある。延年、これを聞いて酒を絶ったところが、とうとう病気になって死んでしまった。
※ 劉譖 字は仲方、これもなかなかの変り種であるが、のち進士に合格して蓬莱県〔山東省〕の知事となり、鄆州〔山東省城県〕で酒友の石曼卿と飲んでいた時に母を病気で失い、死に目に合えなかったのを痛哭して世を去り、その妻も夫を慕って痛哭して世を去ったと『宋史』の伝は伝えていると言う。
夢渓筆談巻3より 芸香(うんこう)
古人藏書辟蠹用蕓。蕓、香草也、今人謂之七裏香者是也。葉類豌豆、作小叢生、其葉極芬香、秋間葉間微白如粉汙、辟蠹殊驗。南人采置席下、能去蚤虱。余判昭文館時、曾得數株於潞公家、移植秘閣後、今不復有存者。香草之類、大率多異名、所謂蘭蓀、蓀、即今菖蒲是也;蕙、今零陵香是也;茞、今白芷是也。
 〔訳〕古人は蔵書の虫除けに芸(うん)を用いた。芸は香草であって、いまいわゆる七里香がこれである。葉は豌豆(えんどう)のそれに似ており、小じんまりと群って生える。その葉はきわめて香りがよく、秋過ぎて葉の間は白粉をまぶしたように少し白くなり、虫除けの効果が特に顕著である。南方人はこれを採集して席(しきもの)の下に置き、蚤や虱除けにする。私が昭文館で書籍の編修校訂の職に任じられた時、数株の芸を潞公(ろこう)の家からもらい、秘閣〔ひかく、貴重な文書などを所蔵する宮中の書庫〕に移植したが、今はもうない。
〔訳〕古人は蔵書の虫除けに芸(うん)を用いた。芸は香草であって、いまいわゆる七里香がこれである。葉は豌豆(えんどう)のそれに似ており、小じんまりと群って生える。その葉はきわめて香りがよく、秋過ぎて葉の間は白粉をまぶしたように少し白くなり、虫除けの効果が特に顕著である。南方人はこれを採集して席(しきもの)の下に置き、蚤や虱除けにする。私が昭文館で書籍の編修校訂の職に任じられた時、数株の芸を潞公(ろこう)の家からもらい、秘閣〔ひかく、貴重な文書などを所蔵する宮中の書庫〕に移植したが、今はもうない。
香草の類は、おおむね異名が多いものだ。いわゆる「蘭蓀〔らんそん、香り草〕の蓀は菖蒲(しょうぶ)のこと、蕙(けい)はいまの零陵香(ふじばかま)のこと、茝(さい)はいまの白芷(よろいぐさ)のことである。
※ 沈括は仁宗の嘉祐8(1063)年に進士となり、館閣すなわち宮中の図書館の一つである昭文館で書籍の編修校訂にあたった。そのあと彼は史館・集賢院などの館閣に数年勤務したが、その頃蘇軾も館閣にいて同僚であった。
※ 潞公(ろこう):宋の仁宋の時に潞国公に封じられた文彦博(1006~97年)のこと。彼は四川から帰任した時にこの芸草を持ってきたという。
古人藏書辟蠹用蕓。蕓、香草也、今人謂之七裏香者是也。葉類豌豆、作小叢生、其葉極芬香、秋間葉間微白如粉汙、辟蠹殊驗。南人采置席下、能去蚤虱。余判昭文館時、曾得數株於潞公家、移植秘閣後、今不復有存者。香草之類、大率多異名、所謂蘭蓀、蓀、即今菖蒲是也;蕙、今零陵香是也;茞、今白芷是也。
香草の類は、おおむね異名が多いものだ。いわゆる「蘭蓀〔らんそん、香り草〕の蓀は菖蒲(しょうぶ)のこと、蕙(けい)はいまの零陵香(ふじばかま)のこと、茝(さい)はいまの白芷(よろいぐさ)のことである。
※ 沈括は仁宗の嘉祐8(1063)年に進士となり、館閣すなわち宮中の図書館の一つである昭文館で書籍の編修校訂にあたった。そのあと彼は史館・集賢院などの館閣に数年勤務したが、その頃蘇軾も館閣にいて同僚であった。
※ 潞公(ろこう):宋の仁宋の時に潞国公に封じられた文彦博(1006~97年)のこと。彼は四川から帰任した時にこの芸草を持ってきたという。
プロフィール
ハンドルネーム:
目高 拙痴无
年齢:
93
誕生日:
1932/02/04
自己紹介:
くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。
sechin@nethome.ne.jp です。
sechin@nethome.ne.jp です。
カレンダー
| 04 | 2025/05 | 06 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新コメント
[enken 02/23]
[中村東樹 02/04]
[m、m 02/04]
[爺の姪 01/13]
[レンマ学(メタ数学) 01/02]
[m.m 10/12]
[爺の姪 10/01]
[あは♡ 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター