瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り
2011年共同通信十大ニュース 大震災、金総書記死去 ―― 2011年の十大ニュースは次のような手順で選ばれた。共同通信の編集関係各部が専門分野を中心に主要ニュースを提案し、編集委員室が国内、国際各30項目を候補に決めた。/投票したのは共同通信の編集関係部長と支社局長、全国の加盟新聞社の編集、論説の責任者、民放契約社の報道責任者ら242人。
 【国内】
【国内】
(1)東日本大震災と東電福島第1原発事故
(2)菅首相が居座りの末退陣、ドジョウ野田内閣誕生
(3)サッカー女子W杯、なでしこジャパン世界一
(4)円が戦後最高値を更新、円売り介入、輸出産業苦境に
(5)野田首相がTPP交渉参加を表明
(6)東電が初の計画停電、夏は15%節電
(7)政府要請で浜岡原発停止、九電ではやらせメール問題
(8)大阪ダブル選で橋下氏、愛知トリプル選で河村氏側完勝
(9)小沢民主党元代表を強制起訴、元秘書3人は有罪
(10)八百長問題で大相撲春場所中止、25人が角界追放
〈次点〉台風12号、15号で大きな被害
 【国際】
【国際】
(1)北朝鮮の金正日総書記が急死、世界に波紋
(2)欧州の財政危機拡大、政権交代相次ぐ
(3)中東に民主化の波、リビアのカダフィ大佐死亡
(4)米特殊部隊がビンラディン容疑者を殺害
(5)タイで大洪水、日本企業が操業停止
(6)東電福島第1原発事故で、欧州に脱原発の動き
(7)米国で反格差デモ、世界へ拡大
(8)ニュージーランド地震で日本人28人死亡
(9)米アップル創業者ジョブズ氏が死去
(10)中国高速鉄道で追突事故、40人死亡
(次点)世界人口70億人に (共同通信 2011年12月23日 18時10分)
(1)東日本大震災と東電福島第1原発事故
(2)菅首相が居座りの末退陣、ドジョウ野田内閣誕生
(3)サッカー女子W杯、なでしこジャパン世界一
(4)円が戦後最高値を更新、円売り介入、輸出産業苦境に
(5)野田首相がTPP交渉参加を表明
(6)東電が初の計画停電、夏は15%節電
(7)政府要請で浜岡原発停止、九電ではやらせメール問題
(8)大阪ダブル選で橋下氏、愛知トリプル選で河村氏側完勝
(9)小沢民主党元代表を強制起訴、元秘書3人は有罪
(10)八百長問題で大相撲春場所中止、25人が角界追放
〈次点〉台風12号、15号で大きな被害
(1)北朝鮮の金正日総書記が急死、世界に波紋
(2)欧州の財政危機拡大、政権交代相次ぐ
(3)中東に民主化の波、リビアのカダフィ大佐死亡
(4)米特殊部隊がビンラディン容疑者を殺害
(5)タイで大洪水、日本企業が操業停止
(6)東電福島第1原発事故で、欧州に脱原発の動き
(7)米国で反格差デモ、世界へ拡大
(8)ニュージーランド地震で日本人28人死亡
(9)米アップル創業者ジョブズ氏が死去
(10)中国高速鉄道で追突事故、40人死亡
(次点)世界人口70億人に (共同通信 2011年12月23日 18時10分)
荀子 哀公篇第三十一 より
孔子曰:「人有五儀:有庸人、有士、有君子、有賢人、有大聖。」
哀公曰:「敢問何如斯可謂庸人矣?」孔子對曰:「所謂庸人者、口不道善言、心不知邑邑;不知選賢人善士託其身焉以為己憂;動行不知所務、止立不知所定;日選擇於物、不知所貴;從物如流、不知所歸;五鑿為正、心從而壞:如此則可謂庸人矣。」
哀公曰:「善!敢問何如斯可謂士矣?」孔子對曰:「所謂士者、雖不能盡道術、必有率也;雖不能遍美善、必有處也。是故知不務多、務審其所知;言不務多、務審其所謂;行不務多、務審其所由。故知既已知之矣、言既已謂之矣、行既已由之矣、則若性命肌膚之不可易也。故富貴不足以益也、卑賤不足以損也:如此則可謂士矣。」
哀公曰:「善!敢問何如斯可謂之君子矣?」孔子對曰:「所謂君子者、言忠信而心不德、仁義在身而色不伐、思慮明通而辭不爭、故猶然如將可及者、君子也。」
「善! 敢問何如斯可謂賢人矣?」孔子對曰:「所謂賢人者、行中規繩而不傷於本、言足法於天下而不傷於身、富有天下而無怨財、布施天下而不病貧:如此則可謂賢人矣。」
哀公曰:「善! 敢問何如斯可謂大聖矣?」孔子對曰:「所謂大聖者、知通乎大道、應變而不窮、辨乎萬物之情性者也。大道者、所以變化遂成萬物也;情性者、所以理然不取舍也。是故其事大辨乎天地、明察乎日月、總要萬物於風雨、繆繆肫肫、其事不可循、若天之嗣、其事不可識、百姓淺然不識其鄰:若此則可謂大聖矣。」哀公曰:「善!」
孔子が、「人には五等の区別があります。凡人、士、君子、賢人、大聖の五つです」と言った。哀公は、
「どういう人が凡人なのか、是非聞きたい」と言ったので、孔子は
「所謂(いわゆる)凡人というものは、口を開けぱ善いことを話さず、自己満足して心に憂えることを知らず、賢人や善士を選んで時分の身を一切任せ、自分の心配事をなくすことを知らず、行動するにも何に務めたらよいか分らず、どんな立場に立てばよいか分らず、毎日あれこれ物を選んでいても、何をた貴んだらよいかをしらず、周囲の者の動きに流され、行き着くところを知らず、五情〔喜怒哀楽怨〕は正常であっても、心は外のものに従ってだめになってしまう。このようであれば凡人といえます」と答えた。哀公は、
「なるほど、そうするとどういうのが士といえるか、お聞きしたい」とたずねた。孔子は、
「所謂士というものは、道術をじゅうぶん尽くすことができないけれど、必ずそれに従い行う所があり、善美をじゅうぶん尽くすことはできないけれど、必ずそれを守っている所があります。こういうわけで知識は多くのことを知るように務めないで、知らねばならないものをじゅうぶんわきまえることに務め、言葉は多言であることに努力しないで、言わねばならないことをじゅうぶんわきまえ、行いは多くのことを行うように努力しないで、その拠り所をじゅうぶんわきまえるように努力します。だから知識はすでに知り尽くし、言葉はすでに言い尽くし、行いは拠り所があって行い尽くしたものになれば、それは生命や皮膚が他のものと代えられないようになります。だからこのような人に対しては、富貴をもってしても貧賤をもってしても、その志を変えさせることはできません。このようであれば士ということができます」と答えた。哀公は、
「なるほどもっともだ。そうするとどういうのが君子といえるのか、おたずねしたい」と言った。孔子はそれに対して、
 「所謂君子というものは、言葉が誠実であって、しかもそれを自分で徳あると思わず、身に仁義の徳があっても、それを誇るような顔色もせず、思慮は深く明らかであっても、人と言い争いません。だからのんびりとしていて一般の人と変わりないように見えていて、しかも一般の人は決して及ばないというのが君子であります」と答えた。哀公は、
「所謂君子というものは、言葉が誠実であって、しかもそれを自分で徳あると思わず、身に仁義の徳があっても、それを誇るような顔色もせず、思慮は深く明らかであっても、人と言い争いません。だからのんびりとしていて一般の人と変わりないように見えていて、しかも一般の人は決して及ばないというのが君子であります」と答えた。哀公は、
「なるほど、そうするとどういうのが賢人といえるのか、おたずねしたい」と言った。孔子は、
 「いわゆる賢人というものは、その行為は自然で無理にその本性をそこなわないでいて規範にかなっているし、その言葉は天下の模範とされるほどであって、しかもそれは自然にそうなって無理にそうするのではありません。富は天下のすべてを持っていながら、しかも私財はなく、天下のものに施しをして、しかも自分は貧しくなるということを心配しません。このようであれば賢人ということができます」と答えた。哀公は、
「いわゆる賢人というものは、その行為は自然で無理にその本性をそこなわないでいて規範にかなっているし、その言葉は天下の模範とされるほどであって、しかもそれは自然にそうなって無理にそうするのではありません。富は天下のすべてを持っていながら、しかも私財はなく、天下のものに施しをして、しかも自分は貧しくなるということを心配しません。このようであれば賢人ということができます」と答えた。哀公は、
「なるほど、どういうのが大聖といえるのか、おたずねしたい」と言った。孔子は、
 「いわゆる大聖というものは、その知識が大道に通じていて、如何なる変化に対してもうまく対応し困ることがなく、多くの事物の性情を区別する人です。大道というものは、万物を変化させ完成させてゆくための道理のことであり、性情というものは、正しいこと悪いこと、取るべきこと捨てるべきことを、うまく処理するための性質であります。だからその人の事業は天地に行き渡るほどおおきく、日月よりも明らかで、万物を統轄し、まことに調和が取れて美しく、細やかで、その事業をまねることはできません。天の支配者のようであって、その事業ははかり知ることはできません。一般の人々は浅はかで、その人についての表面的なことでも知りません。まして深いところを知るはずがありません。このようであれば大聖ということができます」と答えた。哀侯は、
「いわゆる大聖というものは、その知識が大道に通じていて、如何なる変化に対してもうまく対応し困ることがなく、多くの事物の性情を区別する人です。大道というものは、万物を変化させ完成させてゆくための道理のことであり、性情というものは、正しいこと悪いこと、取るべきこと捨てるべきことを、うまく処理するための性質であります。だからその人の事業は天地に行き渡るほどおおきく、日月よりも明らかで、万物を統轄し、まことに調和が取れて美しく、細やかで、その事業をまねることはできません。天の支配者のようであって、その事業ははかり知ることはできません。一般の人々は浅はかで、その人についての表面的なことでも知りません。まして深いところを知るはずがありません。このようであれば大聖ということができます」と答えた。哀侯は、
「なるほど」と言った。
孔子曰:「人有五儀:有庸人、有士、有君子、有賢人、有大聖。」
哀公曰:「敢問何如斯可謂庸人矣?」孔子對曰:「所謂庸人者、口不道善言、心不知邑邑;不知選賢人善士託其身焉以為己憂;動行不知所務、止立不知所定;日選擇於物、不知所貴;從物如流、不知所歸;五鑿為正、心從而壞:如此則可謂庸人矣。」
哀公曰:「善!敢問何如斯可謂士矣?」孔子對曰:「所謂士者、雖不能盡道術、必有率也;雖不能遍美善、必有處也。是故知不務多、務審其所知;言不務多、務審其所謂;行不務多、務審其所由。故知既已知之矣、言既已謂之矣、行既已由之矣、則若性命肌膚之不可易也。故富貴不足以益也、卑賤不足以損也:如此則可謂士矣。」
哀公曰:「善!敢問何如斯可謂之君子矣?」孔子對曰:「所謂君子者、言忠信而心不德、仁義在身而色不伐、思慮明通而辭不爭、故猶然如將可及者、君子也。」
「善! 敢問何如斯可謂賢人矣?」孔子對曰:「所謂賢人者、行中規繩而不傷於本、言足法於天下而不傷於身、富有天下而無怨財、布施天下而不病貧:如此則可謂賢人矣。」
哀公曰:「善! 敢問何如斯可謂大聖矣?」孔子對曰:「所謂大聖者、知通乎大道、應變而不窮、辨乎萬物之情性者也。大道者、所以變化遂成萬物也;情性者、所以理然不取舍也。是故其事大辨乎天地、明察乎日月、總要萬物於風雨、繆繆肫肫、其事不可循、若天之嗣、其事不可識、百姓淺然不識其鄰:若此則可謂大聖矣。」哀公曰:「善!」
孔子が、「人には五等の区別があります。凡人、士、君子、賢人、大聖の五つです」と言った。哀公は、
「どういう人が凡人なのか、是非聞きたい」と言ったので、孔子は
「所謂(いわゆる)凡人というものは、口を開けぱ善いことを話さず、自己満足して心に憂えることを知らず、賢人や善士を選んで時分の身を一切任せ、自分の心配事をなくすことを知らず、行動するにも何に務めたらよいか分らず、どんな立場に立てばよいか分らず、毎日あれこれ物を選んでいても、何をた貴んだらよいかをしらず、周囲の者の動きに流され、行き着くところを知らず、五情〔喜怒哀楽怨〕は正常であっても、心は外のものに従ってだめになってしまう。このようであれば凡人といえます」と答えた。哀公は、
「なるほど、そうするとどういうのが士といえるか、お聞きしたい」とたずねた。孔子は、
「所謂士というものは、道術をじゅうぶん尽くすことができないけれど、必ずそれに従い行う所があり、善美をじゅうぶん尽くすことはできないけれど、必ずそれを守っている所があります。こういうわけで知識は多くのことを知るように務めないで、知らねばならないものをじゅうぶんわきまえることに務め、言葉は多言であることに努力しないで、言わねばならないことをじゅうぶんわきまえ、行いは多くのことを行うように努力しないで、その拠り所をじゅうぶんわきまえるように努力します。だから知識はすでに知り尽くし、言葉はすでに言い尽くし、行いは拠り所があって行い尽くしたものになれば、それは生命や皮膚が他のものと代えられないようになります。だからこのような人に対しては、富貴をもってしても貧賤をもってしても、その志を変えさせることはできません。このようであれば士ということができます」と答えた。哀公は、
「なるほどもっともだ。そうするとどういうのが君子といえるのか、おたずねしたい」と言った。孔子はそれに対して、
「なるほど、そうするとどういうのが賢人といえるのか、おたずねしたい」と言った。孔子は、
「なるほど、どういうのが大聖といえるのか、おたずねしたい」と言った。孔子は、
「なるほど」と言った。
今日は、天皇78歳の誕生日。今朝のウェブニュースより
 対象は? 1代限り?配偶者身分は? …女性宮家創設の課題 ―― 陛下のご入院などをきっかけに、皇位の継承と、それをサポートする皇族方のあり方をめぐって、「女性宮家」や「旧皇族の皇籍復帰」などさまざまな意見があがっている。/悠仁さまが誕生された今、宮内庁の主な懸念は皇位の継承ではなく、女性皇族が結婚により皇室を離れると、悠仁さまの代の宮家が1つだけになってしまうことだ。皇族方の人数が減ると、国際親善や功労者を慰問するなどの皇室の活動が停滞する可能性もある。「女性宮家」の創設が検討される背景にはこうした事情がある。/では、「女性宮家」創設の課題は何なのか。/女性宮家を天皇の娘、孫娘にあたる「内親王」に限れば、現在の皇室での対象者は皇太子ご夫妻の長女、愛子さま、秋篠宮家の眞子さま、佳子さまの3人となる。天皇の曽孫の「女王」までとすると、大正天皇の曽孫にあたる寛仁親王家の彬子さま、瑶子さま、高円宮家の承子さま、典子さま、絢子さまを加えた8人となる。過去にさかのぼって、黒田清子さん(紀宮さま)の身分をどうするかも検討されるだろう。/女性宮家を1代限りとするのか、2代とするかなども議論の対象となる。配偶者の男性を皇族とするか否かも課題だ。/国民への影響としては、国費負担の増加が挙げられる。宮家の皇族の私的費用に当たる皇族費は、現在は当主で3050万円となっている。お住まいの確保や警備の問題も生じる。秋篠宮さまは平成21年の会見で「国費負担という点から見ますと、皇族の数が少ないというのは、私は決して悪いことではないというふうに思います」と述べられている。/女性宮家の創設は「女系天皇」容認につながると指摘する声もあがっている。宮内庁幹部は「女性宮家の議論は、女性天皇について踏み込まない」と皇位継承問題とは別の問題との見解を示しているが、自民党の安倍晋三元首相は「男系で紡いできた皇室の長い歴史と伝統の根本原理が崩れる」と慎重な議論を求めている。/国学院大の大原康男教授は「男系の維持を原則とした皇位継承か、わが国の歴史上いまだかつてない女系天皇という考えを導入するかの議論をまず正面からすべきだ」と、皇位継承と女性宮家を切り離した議論を批判している。 (産経ニュース 2011.12.23 08:29)
対象は? 1代限り?配偶者身分は? …女性宮家創設の課題 ―― 陛下のご入院などをきっかけに、皇位の継承と、それをサポートする皇族方のあり方をめぐって、「女性宮家」や「旧皇族の皇籍復帰」などさまざまな意見があがっている。/悠仁さまが誕生された今、宮内庁の主な懸念は皇位の継承ではなく、女性皇族が結婚により皇室を離れると、悠仁さまの代の宮家が1つだけになってしまうことだ。皇族方の人数が減ると、国際親善や功労者を慰問するなどの皇室の活動が停滞する可能性もある。「女性宮家」の創設が検討される背景にはこうした事情がある。/では、「女性宮家」創設の課題は何なのか。/女性宮家を天皇の娘、孫娘にあたる「内親王」に限れば、現在の皇室での対象者は皇太子ご夫妻の長女、愛子さま、秋篠宮家の眞子さま、佳子さまの3人となる。天皇の曽孫の「女王」までとすると、大正天皇の曽孫にあたる寛仁親王家の彬子さま、瑶子さま、高円宮家の承子さま、典子さま、絢子さまを加えた8人となる。過去にさかのぼって、黒田清子さん(紀宮さま)の身分をどうするかも検討されるだろう。/女性宮家を1代限りとするのか、2代とするかなども議論の対象となる。配偶者の男性を皇族とするか否かも課題だ。/国民への影響としては、国費負担の増加が挙げられる。宮家の皇族の私的費用に当たる皇族費は、現在は当主で3050万円となっている。お住まいの確保や警備の問題も生じる。秋篠宮さまは平成21年の会見で「国費負担という点から見ますと、皇族の数が少ないというのは、私は決して悪いことではないというふうに思います」と述べられている。/女性宮家の創設は「女系天皇」容認につながると指摘する声もあがっている。宮内庁幹部は「女性宮家の議論は、女性天皇について踏み込まない」と皇位継承問題とは別の問題との見解を示しているが、自民党の安倍晋三元首相は「男系で紡いできた皇室の長い歴史と伝統の根本原理が崩れる」と慎重な議論を求めている。/国学院大の大原康男教授は「男系の維持を原則とした皇位継承か、わが国の歴史上いまだかつてない女系天皇という考えを導入するかの議論をまず正面からすべきだ」と、皇位継承と女性宮家を切り離した議論を批判している。 (産経ニュース 2011.12.23 08:29)
 スカイツリーを白くライトアップ クリスマス・大みそか ―― 開業まで5カ月となった東京スカイツリー(東京都墨田区)がクリスマスと大みそかに合わせ、23、24、31日の夜にLED照明器具の一部を点灯して白くライトアップする。634メートルのタワー頂上までライトアップされた姿が初めて、夜空に浮かび上がる。/東武タワースカイツリー社によると、点灯するのはタワーに設置予定の照明器具1995台のうち、地上125メートル以上にある一部のLED照明(白色)720台。地上495メートルにあるゲイン塔用の60台も点灯し、頂上まで照らす。/点灯時間は23、24日は午後5時半から同10時まで、31日は午後9時から元日の午前1時までの予定。荒天で中止したり点灯時間を変更したりする可能性もある。 (asahi com. 2011年12月15日21時22分)
スカイツリーを白くライトアップ クリスマス・大みそか ―― 開業まで5カ月となった東京スカイツリー(東京都墨田区)がクリスマスと大みそかに合わせ、23、24、31日の夜にLED照明器具の一部を点灯して白くライトアップする。634メートルのタワー頂上までライトアップされた姿が初めて、夜空に浮かび上がる。/東武タワースカイツリー社によると、点灯するのはタワーに設置予定の照明器具1995台のうち、地上125メートル以上にある一部のLED照明(白色)720台。地上495メートルにあるゲイン塔用の60台も点灯し、頂上まで照らす。/点灯時間は23、24日は午後5時半から同10時まで、31日は午後9時から元日の午前1時までの予定。荒天で中止したり点灯時間を変更したりする可能性もある。 (asahi com. 2011年12月15日21時22分)

毎日寒い日が続いている。蘇軾の初冬の風景を詠った叙景詩 ―― 蘇軾が淅江総督として杭州に赴任していた55歳頃の作で、劉景文とは当時、淅江方面軍司令官だった友人だそうだ。冬の風景に託して自分の流浪の心境を伝えたものと思える。
贈劉景文 劉景文に贈る 蘇軾
荷尽已無擎雨蓋 荷(はす)は尽きて 已に雨を擎(ささ)ぐる蓋(かさ)無く
菊残猶有傲霜枝 菊は残(そこな)はれて 猶ほ霜に傲(おご)る枝有り
一年好景君須記 一年の好景 君須(すべか)らく記すべし
正是橙黄橘緑時 正に是れ 橙(ゆず)は黄に橘(みかん)は緑なる時
蓮の花は散り果てて、雨を防ぐ傘のようなあの葉ももう無い。
菊の花もしおれてしまったが、それでも霜に負けずに胸を張る枝はやはりある。
一年の中で最も良い風景を、君、是非心に留めるべきだ。
今は丁度、柚が黄色に熟れて、蜜柑がまだ緑の(素晴らしい)季節なのだ。
毎日寒い日が続いている。蘇軾の初冬の風景を詠った叙景詩 ―― 蘇軾が淅江総督として杭州に赴任していた55歳頃の作で、劉景文とは当時、淅江方面軍司令官だった友人だそうだ。冬の風景に託して自分の流浪の心境を伝えたものと思える。
贈劉景文 劉景文に贈る 蘇軾
荷尽已無擎雨蓋 荷(はす)は尽きて 已に雨を擎(ささ)ぐる蓋(かさ)無く
菊残猶有傲霜枝 菊は残(そこな)はれて 猶ほ霜に傲(おご)る枝有り
一年好景君須記 一年の好景 君須(すべか)らく記すべし
正是橙黄橘緑時 正に是れ 橙(ゆず)は黄に橘(みかん)は緑なる時
蓮の花は散り果てて、雨を防ぐ傘のようなあの葉ももう無い。
菊の花もしおれてしまったが、それでも霜に負けずに胸を張る枝はやはりある。
一年の中で最も良い風景を、君、是非心に留めるべきだ。
今は丁度、柚が黄色に熟れて、蜜柑がまだ緑の(素晴らしい)季節なのだ。
冬至は24節気の一つであり、中国では伝統的な祝日でもあった。冬至という節気は2700年前の春秋の時代をさかのぼることができるという。至は極点という意味であるが、「冬至」の意味は寒さが最高に達したことではなく、太陽の位置から言うことで、一年中、昼間が一番短く、夜が一番長い日となる。また、冬至の後、日増しに日が長くなることである。昔、冬至の日から5日間に渡って皇帝は大臣達と音楽を楽しむ。また、庶民も家で楽器を演奏したりする慣わしだ。この日、皇帝は天文暦法の分かる人を呼んで来て、暦法を確認する。同時に天を祭る式典を行なう。世界でも良く知られている北京の天壇は皇帝が冬至の日に天を祭る場所だった。昔、「冬至」の日に冬を祝う『賀冬』という賑やかな行事が行なわれる。この日の朝、人々は早く起きて、綺麗な服を着て、互いに挨拶をかわした。
 冬至の日には「消寒図」を描く習慣があった。すなわち、枝に一輪に9枚の花びらを付けた梅を合わせて9輪描き、毎日花びらに一枚ずつ色をつけてゆく、そして、九九八十一日過ぎると、「画中の梅すべて彩る時、外は緑に染まる」という詩句にも見られるように梅の花びらがすべて塗りつぶされた時、外は暖かい日差しを受けてうららかな春が訪れているというのだ。花弁のかわりに、画数の同じ九文字『庭前垂柳珍重待春風(庭の前の柳、元気で春の風を待つ)』という白抜きの文字を書き、これを毎日一画ずつ塗りつぶして行くこともあるという。
冬至の日には「消寒図」を描く習慣があった。すなわち、枝に一輪に9枚の花びらを付けた梅を合わせて9輪描き、毎日花びらに一枚ずつ色をつけてゆく、そして、九九八十一日過ぎると、「画中の梅すべて彩る時、外は緑に染まる」という詩句にも見られるように梅の花びらがすべて塗りつぶされた時、外は暖かい日差しを受けてうららかな春が訪れているというのだ。花弁のかわりに、画数の同じ九文字『庭前垂柳珍重待春風(庭の前の柳、元気で春の風を待つ)』という白抜きの文字を書き、これを毎日一画ずつ塗りつぶして行くこともあるという。
冬至はまた「交九」とも言って、冬至の日からの81日間を9つの9日間に分けて数えることだ。この81日間が過ぎたら、寒さが去り、天気が暖かくなり、春が来て桃の花も咲くと言うことだ。そして、一九から九九までの季節の移り変わりを歌ったのが「九九の歌」である。
一九二九不出手、三九四九氷上走、五九六九沿河看柳、七九河開、八九燕来、九九消寒〔耕牛遍地走〕
(訳)一番目の九日と二番目の九日は〔人に会っても寒いので〕手を出さず/三番目の九日、四番目の九日は〔川の水が凍り〕氷の上を平気で走れる/五番目の九日、六番目の九日は河沿いに柳をながめ/七番目の九日は河の氷が解け/八番目の九日は燕が戻り/九番目の九日に一番目の九日を加えるころは、寒さも消える。〔牛が鋤(すき)引き田起こしが始まる〕
皆の衆! あと数日で、新年! 寒い中、風邪引かないように、春の風を待とう。
ODE TO THE WEST WIND 〔Ⅴ〕
Percy Bysshe Shelley
 Make me thy lyre even as the forest is :
Make me thy lyre even as the forest is :
What if my leaves are falling like its own !
The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep, autumnal tone,
Sweet though in sadness. Be thou, Spirit fierce,
My spirit ! Be thou me, impetuous one !
Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth !
And, by the incantation of this verse,
Scatter, as from an unextinguished hearth
Ashes and sparks, my words among mankind !
Be through my lips to unawakened earth
The trumpet of a prophecy ! O, Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind ?
西風に寄せる歌 〔五〕 上田 敏 訳
 わたしを あの森のように おまえの竪琴にしてくれ
わたしを あの森のように おまえの竪琴にしてくれ
わたしの木の葉がたとえ森のように散り落ちようとも!
おまえのどよめく壮大な音楽が
悲しいけれど美しい 深い秋の調べを
わたしと森から得るだろう おまえ 荒々しい精よ
わたしの魂となれ! 烈しいものよ わたしとなれ!
わたしの死んだ思想を朽葉のごとく
宇宙にまき散らし 新しい生命をもたらせ!
この歌の魔力によって
くすぶる炉の灰や火花のように
わたしの言葉を 人類のあいだにまき散らせ!
わたしの口をとおして めざめぬ大地に
予言のラッパを吹き鳴らせ! おう 風よ
冬来たりなば 春は遠からずや
冬至はまた「交九」とも言って、冬至の日からの81日間を9つの9日間に分けて数えることだ。この81日間が過ぎたら、寒さが去り、天気が暖かくなり、春が来て桃の花も咲くと言うことだ。そして、一九から九九までの季節の移り変わりを歌ったのが「九九の歌」である。
一九二九不出手、三九四九氷上走、五九六九沿河看柳、七九河開、八九燕来、九九消寒〔耕牛遍地走〕
(訳)一番目の九日と二番目の九日は〔人に会っても寒いので〕手を出さず/三番目の九日、四番目の九日は〔川の水が凍り〕氷の上を平気で走れる/五番目の九日、六番目の九日は河沿いに柳をながめ/七番目の九日は河の氷が解け/八番目の九日は燕が戻り/九番目の九日に一番目の九日を加えるころは、寒さも消える。〔牛が鋤(すき)引き田起こしが始まる〕
皆の衆! あと数日で、新年! 寒い中、風邪引かないように、春の風を待とう。
ODE TO THE WEST WIND 〔Ⅴ〕
Percy Bysshe Shelley
What if my leaves are falling like its own !
The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep, autumnal tone,
Sweet though in sadness. Be thou, Spirit fierce,
My spirit ! Be thou me, impetuous one !
Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth !
And, by the incantation of this verse,
Scatter, as from an unextinguished hearth
Ashes and sparks, my words among mankind !
Be through my lips to unawakened earth
The trumpet of a prophecy ! O, Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind ?
西風に寄せる歌 〔五〕 上田 敏 訳
わたしの木の葉がたとえ森のように散り落ちようとも!
おまえのどよめく壮大な音楽が
悲しいけれど美しい 深い秋の調べを
わたしと森から得るだろう おまえ 荒々しい精よ
わたしの魂となれ! 烈しいものよ わたしとなれ!
わたしの死んだ思想を朽葉のごとく
宇宙にまき散らし 新しい生命をもたらせ!
この歌の魔力によって
くすぶる炉の灰や火花のように
わたしの言葉を 人類のあいだにまき散らせ!
わたしの口をとおして めざめぬ大地に
予言のラッパを吹き鳴らせ! おう 風よ
冬来たりなば 春は遠からずや
荀子 宥坐篇第二十八 より
5 孔子觀於東流之水。子貢問於孔子曰:「君子之所以見大水必觀焉者、是何?」孔子曰:「夫水遍與諸生而無為也、似德。其流也埤下、裾拘必循其理、似義、其洸洸乎不淈盡、似道。若有決行之、其應佚若聲響、其赴百仞之谷不懼、似勇。主量必平、似法。盈不求概、似正。淖約微達、似察。以出以入以就鮮絜、似善化。其萬折也必東、似志。是故見大水必觀焉。
 孔子が東に流れる河をじっと見つめていた。子貢が孔子に、
孔子が東に流れる河をじっと見つめていた。子貢が孔子に、
「君子が大きな河を見ると必ずじゅうぶん観察するのはどうしてでしょう」と問うた。孔子は、
「水というものは万物に生命を与えていながら、なにもしていないような状態でいるのは、徳と似ている。其の流れは低い方に従って直曲し、必ずこの道理に従うといういうことでは、義と似ている。水がこんこんと湧き出て尽きることがないということでは、道と似ている。もし堰(せき)を切って水を流すと、声に応ずる響きの速さで流れゆき、百仞(ひゃくじん)の谷でも何処でも恐れずに流れてゆくのは、勇気と似ている。くぼんだ所にそそいで必ず平らになるのは、法度に似ている。一杯になってもますかきで余分を除く必要もなく、たいらになるということでは、正に似ている。弱弱しくても大変小さな所まで浸透してゆくと言うことでは、洞察力に似ている。その中に出入りすることによって清潔になれるということでは、立派な感化に似ている。数多く曲がりくねっていても必ず東に流れると言うことでは、意志に似ている。だから君子は大きな河を見ると必ずじゅうぶんに観察して考えるのである」と答えた。
5 孔子觀於東流之水。子貢問於孔子曰:「君子之所以見大水必觀焉者、是何?」孔子曰:「夫水遍與諸生而無為也、似德。其流也埤下、裾拘必循其理、似義、其洸洸乎不淈盡、似道。若有決行之、其應佚若聲響、其赴百仞之谷不懼、似勇。主量必平、似法。盈不求概、似正。淖約微達、似察。以出以入以就鮮絜、似善化。其萬折也必東、似志。是故見大水必觀焉。
「君子が大きな河を見ると必ずじゅうぶん観察するのはどうしてでしょう」と問うた。孔子は、
「水というものは万物に生命を与えていながら、なにもしていないような状態でいるのは、徳と似ている。其の流れは低い方に従って直曲し、必ずこの道理に従うといういうことでは、義と似ている。水がこんこんと湧き出て尽きることがないということでは、道と似ている。もし堰(せき)を切って水を流すと、声に応ずる響きの速さで流れゆき、百仞(ひゃくじん)の谷でも何処でも恐れずに流れてゆくのは、勇気と似ている。くぼんだ所にそそいで必ず平らになるのは、法度に似ている。一杯になってもますかきで余分を除く必要もなく、たいらになるということでは、正に似ている。弱弱しくても大変小さな所まで浸透してゆくと言うことでは、洞察力に似ている。その中に出入りすることによって清潔になれるということでは、立派な感化に似ている。数多く曲がりくねっていても必ず東に流れると言うことでは、意志に似ている。だから君子は大きな河を見ると必ずじゅうぶんに観察して考えるのである」と答えた。
荀子 宥坐篇第二十八 より
2 孔子為魯攝相、朝七日而誅少正卯。門人進問曰:「夫少正卯魯之聞人也、夫子為政而始誅之、得無失乎、」孔子曰:「居、吾語女其故。人有惡者五、而盜竊不與焉:一曰:心達而險;二曰:行辟而堅;三曰:言偽而辯;四曰:記醜而博;五曰:順非而澤--此五者有一於人、則不得免於君子之誅、而少正卯兼有之。故居處足以聚徒成群、言談足飾邪營眾、強足以反是獨立、此小人之桀雄也、不可不誅也。是以湯誅尹諧、文王誅潘止、周公誅管叔、太公誅華仕、管仲誅付里乙、子產誅鄧析史付、此七子者、皆異世同心、不可不誅也。《詩》曰:『憂心悄悄、慍於群小。』小人成群、斯足憂也。」
 孔子は魯の国の司法大臣に任命され、朝廷へ出仕して七日しか経っていないときに、少正卯〔しょうせいぼう、?~BC496年、春秋時代の魯国の大夫〕を死刑に処した。門人らが進み出て、
孔子は魯の国の司法大臣に任命され、朝廷へ出仕して七日しか経っていないときに、少正卯〔しょうせいぼう、?~BC496年、春秋時代の魯国の大夫〕を死刑に処した。門人らが進み出て、
「あの少正卯は魯の国の名士です。先生が政治を取って第一番目に彼を誅罰せられましたことは、立派なやり方でしょうか」
と問うた。孔子は、
「まあ、坐れ、そのわけを話してやろう。人間であればしてはならない悪いことが五つあるが、盗みはこれに入らない。その第一は、心が物事によく通じていて陰険であること。第二は行いが偏って頑ななこと。第三は嘘つきなくせに雄弁なこと。第四は悪い事ばかりよく記憶していること。第五は悪いことに従って外面を美しく見せることである。この五つのことが一つでも人にあると、君子からの誅罰を逃れることのできないものである。それなのに少正卯はその全部を兼ね備えていた。だから彼の居宅では、よくない人々を集め、乱をなす群衆をつくることができ、彼の弁舌はよこしまなことでも言いつくろって民衆を騙すことができ、彼の勢力は正しいことに反対し、それでもって独立してゆけるほどである。これは小人たちの中での悪いほうの大将である。どうしても誅罰しなければならない。だから殷の湯王は尹諧を誅罰し、周の文王は潘止を誅罰し、周公は管叔を誅罰し、太公望の呂尚は華仕を誅罰し、斉の管仲は付里乙(ふりいつ)を誅罰し、鄭の子産は史付(しふ)を誅罰した。この七人は時代は違うが同じように悪い心をもっていたので、どうしても誅罰せねばならなかった。『詩経〔邶風(はいふう)・柏舟(はくしゅう)篇〕』に『憂いの心で一杯である。多くのつまらない人どもに怒られることを』とある。小人どもが群れをなすと、憂い悲しむべきことなのである」と言った。
詩経 邶風(はいふう) 柏舟(はくしゅう)篇
汎彼柏舟、亦汎其流、耿耿不寐、如有隱憂、微我無酒、以敖以遊
〔読み〕汎たる彼の柏舟、亦た汎として其れ流る、耿耿として寐ねられず、隱憂あるが如し、我に酒の以て敖(ごう)し、以て遊する無きに微(あら)ず
〔訳〕流れに浮かぶ柏(ひ)の舟は/よるべもなく漂うている/深い憂いが胸に満ち/うとうとと夜も眠られぬ/心の思いを忘れて遊ぶ/酒もないではないけれど
 我心匪鑒、不可以茹、亦有兄弟、不可以據、薄言往愬、逢彼之怒
我心匪鑒、不可以茹、亦有兄弟、不可以據、薄言往愬、逢彼之怒
〔読み〕我が心 鑒(かがみ)に匪(あら)ず、以て茹(い)る可からず、亦た兄弟有れども、以て據る可からず、薄らく言(ここ)に往き愬(つぐ)れば、彼の怒りに逢ふ
〔訳〕鏡でもない私の心に/人の思いは計られぬ/よし兄弟が在ればとて/何の頼りになるものか/かりに往って訴えても/却って怒られるばかりなのだ
我心匪石、不可轉也、我心匪席、不可卷也、威儀棣棣、不可選也
〔読み〕我が心 石に匪ず、轉がす可からざる也、我心 席(むしろ)に匪ず、卷く可からざる也、威儀(いぎ)棣棣(ていてい)として、選ぶ可からざる也
〔訳〕石ではない私の心を/頃がして移すことはできぬ/蓆でもない私の心を/巻いて収めることはできぬ/恐れることのない態度で/自分を枉げることはできぬのだ
憂心悄悄、慍于群小、覯閔既多、受侮不少、靜言思之、寤辟有摽
〔読み〕憂心 悄悄として、群小に慍(うら)まる、閔(うれひ)に覯(あ)ふこと既に多く、侮を受くること少なからず、靜かに言に之を思ひ、寤めて辟(むねう)つこと摽たる有り
〔訳〕心の憂いは果もない/つまらぬ者に憎まれて/辛い思いも重なれば/侮られたのも幾度か/醒めて静かに思う時/胸を辟(な)で摽(う)つばかりなのだ
日居月諸、胡迭而微、心之憂矣、如匪澣衣、靜言思之、不能奮飛
〔読み〕日や 月や、胡(なん)ぞ迭(かへ)って微なるや、心の憂ひ、澣(あら)はざる衣の如し、靜かに言に之を思ひ、奮ひ飛ぶこと能はず
〔訳〕ああ 日よ月よ/なぜ互いに欠けるのか/この心の憂わしさは/汚れた衣(きもの)を着ているようだ/静かに思い悩みつつ/飛び立ちかねる鳥ならぬ身は
※衛の頃侯〔(?~BC855年)の時、仁者は不遇で、小人が君の側にあった。その不遇な仁人の詩であると言う。『列女伝』では衛の寡夫人の詩であると、朱子は夫に愛されぬ婦人の嘆きとする。このように作者を男性と見るか、女性と見るか二説あるわけで、それによって諸家の説も分かれるが、威儀棣棣といい、慍于群小といえば、士人の作か、婦人としてもしかるべく身分の人であろう。賢者が小人の讒を受けるのを憤る死であると言う説もあるというが、ともあれ心あるものが小人に苦しめられ、訴える所のない深い悲しみを詠っているのであるという。その憂いの何故かは知るべくもない。
2 孔子為魯攝相、朝七日而誅少正卯。門人進問曰:「夫少正卯魯之聞人也、夫子為政而始誅之、得無失乎、」孔子曰:「居、吾語女其故。人有惡者五、而盜竊不與焉:一曰:心達而險;二曰:行辟而堅;三曰:言偽而辯;四曰:記醜而博;五曰:順非而澤--此五者有一於人、則不得免於君子之誅、而少正卯兼有之。故居處足以聚徒成群、言談足飾邪營眾、強足以反是獨立、此小人之桀雄也、不可不誅也。是以湯誅尹諧、文王誅潘止、周公誅管叔、太公誅華仕、管仲誅付里乙、子產誅鄧析史付、此七子者、皆異世同心、不可不誅也。《詩》曰:『憂心悄悄、慍於群小。』小人成群、斯足憂也。」
「あの少正卯は魯の国の名士です。先生が政治を取って第一番目に彼を誅罰せられましたことは、立派なやり方でしょうか」
と問うた。孔子は、
「まあ、坐れ、そのわけを話してやろう。人間であればしてはならない悪いことが五つあるが、盗みはこれに入らない。その第一は、心が物事によく通じていて陰険であること。第二は行いが偏って頑ななこと。第三は嘘つきなくせに雄弁なこと。第四は悪い事ばかりよく記憶していること。第五は悪いことに従って外面を美しく見せることである。この五つのことが一つでも人にあると、君子からの誅罰を逃れることのできないものである。それなのに少正卯はその全部を兼ね備えていた。だから彼の居宅では、よくない人々を集め、乱をなす群衆をつくることができ、彼の弁舌はよこしまなことでも言いつくろって民衆を騙すことができ、彼の勢力は正しいことに反対し、それでもって独立してゆけるほどである。これは小人たちの中での悪いほうの大将である。どうしても誅罰しなければならない。だから殷の湯王は尹諧を誅罰し、周の文王は潘止を誅罰し、周公は管叔を誅罰し、太公望の呂尚は華仕を誅罰し、斉の管仲は付里乙(ふりいつ)を誅罰し、鄭の子産は史付(しふ)を誅罰した。この七人は時代は違うが同じように悪い心をもっていたので、どうしても誅罰せねばならなかった。『詩経〔邶風(はいふう)・柏舟(はくしゅう)篇〕』に『憂いの心で一杯である。多くのつまらない人どもに怒られることを』とある。小人どもが群れをなすと、憂い悲しむべきことなのである」と言った。
詩経 邶風(はいふう) 柏舟(はくしゅう)篇
汎彼柏舟、亦汎其流、耿耿不寐、如有隱憂、微我無酒、以敖以遊
〔読み〕汎たる彼の柏舟、亦た汎として其れ流る、耿耿として寐ねられず、隱憂あるが如し、我に酒の以て敖(ごう)し、以て遊する無きに微(あら)ず
〔訳〕流れに浮かぶ柏(ひ)の舟は/よるべもなく漂うている/深い憂いが胸に満ち/うとうとと夜も眠られぬ/心の思いを忘れて遊ぶ/酒もないではないけれど
〔読み〕我が心 鑒(かがみ)に匪(あら)ず、以て茹(い)る可からず、亦た兄弟有れども、以て據る可からず、薄らく言(ここ)に往き愬(つぐ)れば、彼の怒りに逢ふ
〔訳〕鏡でもない私の心に/人の思いは計られぬ/よし兄弟が在ればとて/何の頼りになるものか/かりに往って訴えても/却って怒られるばかりなのだ
我心匪石、不可轉也、我心匪席、不可卷也、威儀棣棣、不可選也
〔読み〕我が心 石に匪ず、轉がす可からざる也、我心 席(むしろ)に匪ず、卷く可からざる也、威儀(いぎ)棣棣(ていてい)として、選ぶ可からざる也
〔訳〕石ではない私の心を/頃がして移すことはできぬ/蓆でもない私の心を/巻いて収めることはできぬ/恐れることのない態度で/自分を枉げることはできぬのだ
憂心悄悄、慍于群小、覯閔既多、受侮不少、靜言思之、寤辟有摽
〔読み〕憂心 悄悄として、群小に慍(うら)まる、閔(うれひ)に覯(あ)ふこと既に多く、侮を受くること少なからず、靜かに言に之を思ひ、寤めて辟(むねう)つこと摽たる有り
〔訳〕心の憂いは果もない/つまらぬ者に憎まれて/辛い思いも重なれば/侮られたのも幾度か/醒めて静かに思う時/胸を辟(な)で摽(う)つばかりなのだ
日居月諸、胡迭而微、心之憂矣、如匪澣衣、靜言思之、不能奮飛
〔読み〕日や 月や、胡(なん)ぞ迭(かへ)って微なるや、心の憂ひ、澣(あら)はざる衣の如し、靜かに言に之を思ひ、奮ひ飛ぶこと能はず
〔訳〕ああ 日よ月よ/なぜ互いに欠けるのか/この心の憂わしさは/汚れた衣(きもの)を着ているようだ/静かに思い悩みつつ/飛び立ちかねる鳥ならぬ身は
※衛の頃侯〔(?~BC855年)の時、仁者は不遇で、小人が君の側にあった。その不遇な仁人の詩であると言う。『列女伝』では衛の寡夫人の詩であると、朱子は夫に愛されぬ婦人の嘆きとする。このように作者を男性と見るか、女性と見るか二説あるわけで、それによって諸家の説も分かれるが、威儀棣棣といい、慍于群小といえば、士人の作か、婦人としてもしかるべく身分の人であろう。賢者が小人の讒を受けるのを憤る死であると言う説もあるというが、ともあれ心あるものが小人に苦しめられ、訴える所のない深い悲しみを詠っているのであるという。その憂いの何故かは知るべくもない。
ウュブニュースより
 北朝鮮の金正日総書記が死去 現地指導の途中、69歳 ―― 【北京共同】朝鮮中央通信は19日、北朝鮮の最高指導者で国防委員会委員長の金正日総書記=朝鮮人民軍最高司令官=が17日、現地指導に向かう列車の中で死去したと報じた。急性心筋梗塞を起こしたとしている。建国からほぼ半世紀、同国を率いた父親の故金日成主席から権力を継承し、親子2代にわたり統治した。/北朝鮮は独自の社会主義体制の支柱を失い、後継者の三男、金正恩氏を中心とした統治体制確立や核・ミサイル問題の行方が焦点となる。日本など周辺国を含めた東アジア情勢が重大な岐路に立たされるのは必至だ。 (2011/12/19 12:49 【共同通信】)
北朝鮮の金正日総書記が死去 現地指導の途中、69歳 ―― 【北京共同】朝鮮中央通信は19日、北朝鮮の最高指導者で国防委員会委員長の金正日総書記=朝鮮人民軍最高司令官=が17日、現地指導に向かう列車の中で死去したと報じた。急性心筋梗塞を起こしたとしている。建国からほぼ半世紀、同国を率いた父親の故金日成主席から権力を継承し、親子2代にわたり統治した。/北朝鮮は独自の社会主義体制の支柱を失い、後継者の三男、金正恩氏を中心とした統治体制確立や核・ミサイル問題の行方が焦点となる。日本など周辺国を含めた東アジア情勢が重大な岐路に立たされるのは必至だ。 (2011/12/19 12:49 【共同通信】)
荀子の宥坐篇第二十八以下は荀子とその弟子が諸事の伝聞した諸事を記録したものと言う。宥坐篇は篇主の第一節に座右の器〔有坐〕を論じていることから付いた篇名と言われる。
荀子 宥坐篇第二十八 より
1 孔子觀於魯桓公之廟、有欹器焉、孔子問於守廟者曰:「此為何器?」守廟者曰:「此蓋為宥坐之器、」孔子曰:「吾聞宥坐之器者、虛則欹、中則正、滿則覆。」孔子顧謂弟子曰:「注水焉。」弟子挹水而注之。中而正、滿而覆、虛而欹、孔子喟然而歎曰:「吁!惡有滿而不覆者哉!」子路曰:「敢問持滿有道乎?」孔子曰:「聰明聖知、守之以愚;功被天下、守之以讓;勇力撫世、守之以怯、富有四海、守之以謙:此所謂挹而損之之道也。」
 孔子が魯の国の桓公の霊廟(みたまや)を拝観したときに、傾いた器が置かれてあった。孔子が警備の役人に、
孔子が魯の国の桓公の霊廟(みたまや)を拝観したときに、傾いた器が置かれてあった。孔子が警備の役人に、
「これは何をする器ですか」
と問うと、その役人は、
「これは多分座右の戒めの器だと思います」
と答えた。孔子は、
「座右の戒めの器というものは、中が空であるときには傾き、半分ぐらい入ったときには真っ直ぐになり、一杯入ったときにはひっくり返ると聞いています」
と言った。そこで孔子が弟子たちにふりかえり、
「水を入れなさい」
と言った。弟子が水をくんで器の中にそそぐと、ちょうど半分で真っ直ぐになり、一杯入れるとひっくり返り、からにすると傾いた。孔子はため息をして、
「ああ、一杯になり満ち溢(あふ)れるようになってひっくり返らないものがどこにあろうか」
と感嘆した。子路が、
「満ち溢れた状態を維持する方法がありましょうか、どうぞお教え下さい」
と言った。孔子は、
「世間にまれな賢さの人があれば、馬鹿者のような風をしてそれを守り、功業が天下にゆきわたるほどあるときは、人に譲るということによってそれを守り、勇気が世間に響きわたる程あるときは、臆病な風でそれを守り、世界中の財産を持っているときは、へりくだった風でそれをまもってゆく、これが所謂(いわゆる)おさえて少なめにするやり方(最高の状態にならないように余裕を残しておく)である」
と言った。
荀子の宥坐篇第二十八以下は荀子とその弟子が諸事の伝聞した諸事を記録したものと言う。宥坐篇は篇主の第一節に座右の器〔有坐〕を論じていることから付いた篇名と言われる。
荀子 宥坐篇第二十八 より
1 孔子觀於魯桓公之廟、有欹器焉、孔子問於守廟者曰:「此為何器?」守廟者曰:「此蓋為宥坐之器、」孔子曰:「吾聞宥坐之器者、虛則欹、中則正、滿則覆。」孔子顧謂弟子曰:「注水焉。」弟子挹水而注之。中而正、滿而覆、虛而欹、孔子喟然而歎曰:「吁!惡有滿而不覆者哉!」子路曰:「敢問持滿有道乎?」孔子曰:「聰明聖知、守之以愚;功被天下、守之以讓;勇力撫世、守之以怯、富有四海、守之以謙:此所謂挹而損之之道也。」
「これは何をする器ですか」
と問うと、その役人は、
「これは多分座右の戒めの器だと思います」
と答えた。孔子は、
「座右の戒めの器というものは、中が空であるときには傾き、半分ぐらい入ったときには真っ直ぐになり、一杯入ったときにはひっくり返ると聞いています」
と言った。そこで孔子が弟子たちにふりかえり、
「水を入れなさい」
と言った。弟子が水をくんで器の中にそそぐと、ちょうど半分で真っ直ぐになり、一杯入れるとひっくり返り、からにすると傾いた。孔子はため息をして、
「ああ、一杯になり満ち溢(あふ)れるようになってひっくり返らないものがどこにあろうか」
と感嘆した。子路が、
「満ち溢れた状態を維持する方法がありましょうか、どうぞお教え下さい」
と言った。孔子は、
「世間にまれな賢さの人があれば、馬鹿者のような風をしてそれを守り、功業が天下にゆきわたるほどあるときは、人に譲るということによってそれを守り、勇気が世間に響きわたる程あるときは、臆病な風でそれを守り、世界中の財産を持っているときは、へりくだった風でそれをまもってゆく、これが所謂(いわゆる)おさえて少なめにするやり方(最高の状態にならないように余裕を残しておく)である」
と言った。
ウェブニュースより
日本の中高生が首相を風刺「野田る」「鳩る」「菅る」とは=中国 ―― 日本の若者は政治への関心が薄いと言われる。しかし最近、大修館書店が中高生に「国語辞典に載せたい新しい動詞」を募集したところ、意外にも数多くの新しい動詞が集められた。これらの動詞は首相の名前を動詞形にしたもので、中高生たちの政治家に対する深い理解が表われていた。中国メディアの中国評論新聞網が17日付で報じた。
 ■政治(日本) - サーチナ・トピックス
■政治(日本) - サーチナ・トピックス
募集には野田佳彦首相の名前を動詞形とした「野田(のだ)る」との言葉が寄せられ、その意味は「ドジョウのように泥臭くがんばる」、「スピーチに長けているが、中身がない」ものという。/そのほか、「小沢(おざわ)る」という言葉は、「裏で操ることに長ける」、「部下がたくさんいる」、「責任逃れをする」、「肝心な時に捜し出せない」などの意味だという。「無責任なことを言う」、「話すたびに内容が変わる」、「悪いと思わずにうそをつく」という「鳩(はと)る」なども寄せられた。/さらに「いつまでも地位を譲らない」、「何もせずにだらだらしている」、「無意味に粘る」という意味で、菅直人前首相から取られた「菅(かん)る」、また「暴言で相手を攻撃する」、「法律用語を用いてクロをシロだと言いくるめる」という意味の仙谷元官房長官に由来する「仙谷(せんごく)る」という動詞も寄せられたという。/記事は、「これらの動詞は政治家たちの言行を実にするどく描写しており、日本の若者たちが本当は政治に注意を払っていることが分かる」と指摘。しかし、これらの新しい動詞が国語辞典に記載されるかどうかは現時点では定かではなく、審査結果を待つ必要があると報じた。 (searchina 2011/12/18(日) 10:23)
日本の中高生が首相を風刺「野田る」「鳩る」「菅る」とは=中国 ―― 日本の若者は政治への関心が薄いと言われる。しかし最近、大修館書店が中高生に「国語辞典に載せたい新しい動詞」を募集したところ、意外にも数多くの新しい動詞が集められた。これらの動詞は首相の名前を動詞形にしたもので、中高生たちの政治家に対する深い理解が表われていた。中国メディアの中国評論新聞網が17日付で報じた。
募集には野田佳彦首相の名前を動詞形とした「野田(のだ)る」との言葉が寄せられ、その意味は「ドジョウのように泥臭くがんばる」、「スピーチに長けているが、中身がない」ものという。/そのほか、「小沢(おざわ)る」という言葉は、「裏で操ることに長ける」、「部下がたくさんいる」、「責任逃れをする」、「肝心な時に捜し出せない」などの意味だという。「無責任なことを言う」、「話すたびに内容が変わる」、「悪いと思わずにうそをつく」という「鳩(はと)る」なども寄せられた。/さらに「いつまでも地位を譲らない」、「何もせずにだらだらしている」、「無意味に粘る」という意味で、菅直人前首相から取られた「菅(かん)る」、また「暴言で相手を攻撃する」、「法律用語を用いてクロをシロだと言いくるめる」という意味の仙谷元官房長官に由来する「仙谷(せんごく)る」という動詞も寄せられたという。/記事は、「これらの動詞は政治家たちの言行を実にするどく描写しており、日本の若者たちが本当は政治に注意を払っていることが分かる」と指摘。しかし、これらの新しい動詞が国語辞典に記載されるかどうかは現時点では定かではなく、審査結果を待つ必要があると報じた。 (searchina 2011/12/18(日) 10:23)
ウェブニュースより
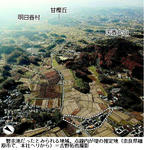
 日本書紀記述の「磐余池」の堤跡など出土…奈良・橿原 ―― 奈良県橿原市東池尻町で、「日本書紀」や「万葉集」に登場する人工池「磐余池(いわれいけ)」の遺構とみられる堤跡と大型建物跡(6世紀後半)などが出土したと、市教委が15日発表した。池のほとりでは聖徳太子の父・用明(ようめい)天皇(在位585~587年)が宮殿を営んだとされ、建物跡はその一部との見方が出ている。飛鳥時代(7世紀)より前の天皇の宮殿は確認されておらず、最古の宮殿跡の可能性もある。/一帯は大和三山・天香久山(あまのかぐやま)の北にあたる藤原京跡の一角。「池」のつく地名が多いことや地形などから池の候補地とされていた。10月から道路工事に伴って発掘したところ、盛り土をした長さ81メートル、幅8メートル、高さ2メートルの堤跡を確認した。/周辺の地形などから、堤は「へ」の字状で、最大幅55メートル、高さ3メートル、長さ約330メートルと推定。複数の谷の水をダムのようにせき止め、南北約600メートル、東西約700メートルの範囲に、手の形をした面積8万7500平方メートルの池を形成したらしい。平安時代までは存在したとみられる。/堤跡の上では大型建物跡1棟(東西4メートル、南北17.5メートル以上)など建物6棟や塀跡2列が見つかった。/日本書紀には、磐余池は5世紀前半に履中(りちゅう)天皇が造り、585年には用明天皇が池のほとりに「磐余池辺双槻宮(いわれいけべのなみつきのみや)」を設けたとある。万葉集でも大津皇子(みこ)の辞世の歌に登場する。これまで最古の人工池は7世紀前半の狭山池(大阪府大阪狭山市、現存)とされるが、今回の遺構はこれを遡る。/和田萃(あつむ)・京都教育大名誉教授(古代史)の話「堤は天香久山を望めるなど眺めがよい所で、池は灌漑(かんがい)用だけでなく観賞用でもあったのだろう。大型建物は用明天皇の宮殿の一角と想定でき、一帯が大和王権にとって重要な場所だったことがわかる」 (2011年12月16日 読売新聞)
日本書紀記述の「磐余池」の堤跡など出土…奈良・橿原 ―― 奈良県橿原市東池尻町で、「日本書紀」や「万葉集」に登場する人工池「磐余池(いわれいけ)」の遺構とみられる堤跡と大型建物跡(6世紀後半)などが出土したと、市教委が15日発表した。池のほとりでは聖徳太子の父・用明(ようめい)天皇(在位585~587年)が宮殿を営んだとされ、建物跡はその一部との見方が出ている。飛鳥時代(7世紀)より前の天皇の宮殿は確認されておらず、最古の宮殿跡の可能性もある。/一帯は大和三山・天香久山(あまのかぐやま)の北にあたる藤原京跡の一角。「池」のつく地名が多いことや地形などから池の候補地とされていた。10月から道路工事に伴って発掘したところ、盛り土をした長さ81メートル、幅8メートル、高さ2メートルの堤跡を確認した。/周辺の地形などから、堤は「へ」の字状で、最大幅55メートル、高さ3メートル、長さ約330メートルと推定。複数の谷の水をダムのようにせき止め、南北約600メートル、東西約700メートルの範囲に、手の形をした面積8万7500平方メートルの池を形成したらしい。平安時代までは存在したとみられる。/堤跡の上では大型建物跡1棟(東西4メートル、南北17.5メートル以上)など建物6棟や塀跡2列が見つかった。/日本書紀には、磐余池は5世紀前半に履中(りちゅう)天皇が造り、585年には用明天皇が池のほとりに「磐余池辺双槻宮(いわれいけべのなみつきのみや)」を設けたとある。万葉集でも大津皇子(みこ)の辞世の歌に登場する。これまで最古の人工池は7世紀前半の狭山池(大阪府大阪狭山市、現存)とされるが、今回の遺構はこれを遡る。/和田萃(あつむ)・京都教育大名誉教授(古代史)の話「堤は天香久山を望めるなど眺めがよい所で、池は灌漑(かんがい)用だけでなく観賞用でもあったのだろう。大型建物は用明天皇の宮殿の一角と想定でき、一帯が大和王権にとって重要な場所だったことがわかる」 (2011年12月16日 読売新聞)
日本書紀 巻十二 去来穂別天皇(いざほわけのすめらみこと)〔履中天皇〕より
二年の春正月(むつき)の丙午の朔己酉に、瑞齒別皇子(みつはわけのみこ)を立てて儲君(ひつぎのみこ)とす。
冬十月(かむなづき)に、磐余に都つくる。是の時に當りて、平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね)・蘇我満智宿禰(そがのまちのすくね)・物部伊莒大連(もののべのいこふのおおむらじ)・圓〔つぶら、豆夫羅〕大使夫主(おほみ)、共に國事(くにのこと)を執れり。
十一月に、磐余池(いわれのいけ)をつくる。
三年の冬十一月(しもつき)の丙寅の朔辛未に、天皇(すめらみこと)、兩枝船(ふたまたぶね)を磐余市磯池(いわれのいちしのいけ)に泛(うか)べたまう。皇妃(みめ)と各分ち乘りて遊宴(あそ)びたまふ。膳臣余磯(かしわでのおみあれし)、酒獻(たてまつ)る。時に櫻の花、御盞(おほみさかづき)に落(おちい)れり。天皇、異(あやし)びたまひて、則ち物部長眞膽連(もののべのながまいのむらじ)を召して、詔して曰はく、「是の花、非時(ときじく)にして來れり。其れ何處(いどこ)の花ならむ。汝(いまし)、自ら求むべし」とのたまふ。是に長眞膽連、獨り花を尋ねて、掖上室山(わきのかみのむろのやま)に獲(え)て、獻る。天皇、其の希有(めずら)しきことを歡びて、即ち宮の名としたまふ。故、磐余稚櫻宮(いわれのわかさくらのみや)と謂(まう)す。其れ此の縁なり。是の日に、長眞膽連の本姓(もとのかばね)を改めて、稚櫻部造(わかざくらのみやっこ)と曰(い)ふ。又、膳臣余磯(かしわでのおみあれし)を號(なづ)けて、稚櫻部臣(わかさくらべのおみ)と曰ふ。
〔訳〕磐余の稚桜の宮
二年の春一月四日、瑞齒別皇子を立てて皇太子とした。
冬十月磐余に都を作った。このとき、平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね)・蘇我満智宿禰(そがのまちのすくね)・物部伊莒大連(もののべのいこふのおおむらじ)・圓大使夫主(つぶらおほみ)らは、共に国の政治に携わった。
十一月磐余の池を作った。
三年冬十一月六日、天皇は兩股船を磐余の市磯池に浮かべられた。后とそれぞれの船に分乗して遊ばれた。膳臣(かしわでのおみ)の余磯(あれし)が酒を奉った。そのとき桜の花びらが盃に散った。天皇は怪しまれて、物部長真胆連(もののべのながいのむらじ)を召して、詔して「この花は咲くべき時でないに散ってきた。何処の花だろうか。お前が探して来い」といわれた。長真胆連は独り花を尋ねて、掖上(わきのかみ)の室山で、花を手に入れて奉った。天皇は其の珍しいことを喜んで、宮の名とされた。磐余若桜宮(いわれのわかざくらのみや)というのはこれがそのもとである。この日、長真胆連の本姓を改めて、稚桜部造とし、膳臣余磯を名付けて稚桜部臣とされた。
大津皇子(おおつのみこ、663~686年)は天武天皇の皇子。母は天智天皇皇女の大田皇女。妃は天智天皇皇女の山辺皇女。686年(朱鳥元年)9月に天武天皇が崩御すると、1ヶ月も経たない10月2日に親友の川島皇子の密告により、謀反の意有りとされて捕えられ、翌日磐余(いわれ)にある訳語田(おさだ)の自邸で死を賜ったのである。
大津皇子の死を被(たま)はりし時、
磐余(いはれ)の池の堤にして涙を流して作らす御歌一首
ももづたふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ (万葉集巻3、416)
【釈】磐余(いわれ)の池に鳴く鴨を見るのも今日限りで、私は死ぬのだろうか。
 五言臨終一絶 〔懐風藻〕
五言臨終一絶 〔懐風藻〕
金烏西舎(きんうせいしゃ)に臨(てら)ひ
鼓声短命(こせいたんめい)を催(うなが)す
泉路(せんろ)賓主(ひんしゅ)無し
此の夕(ゆうべ)家を離(さかり)て向かふ
(訳)太陽は西に傾き家々を照らし、夕刻を告げる太鼓の音は、短命を急がすかのように聞こえる。黄泉の道には客も主人もなくただ一人、夕べには家を離れて死出の旅に出るのか・・・。
万葉集にある大伯皇女(おおくのひめみこ)の歌
神風の伊勢の国にもあらましを何しか来けむ 君もあらなくに(巻2-163)
(訳)こんなことなら伊勢の国にいたのに。どうして都に帰ってきてしまったのだろう。あなたがいるわけでもないのに
※かつて、横浜在住のIN氏に贈って貰った大津皇子の伝記「飛鳥はふぶき」(山本藤枝著・ポブラ社刊)を読んだことを思い出し、再読すべく本棚の隅に誇り塗れて本を取り出した。
日本書紀 巻十二 去来穂別天皇(いざほわけのすめらみこと)〔履中天皇〕より
二年の春正月(むつき)の丙午の朔己酉に、瑞齒別皇子(みつはわけのみこ)を立てて儲君(ひつぎのみこ)とす。
冬十月(かむなづき)に、磐余に都つくる。是の時に當りて、平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね)・蘇我満智宿禰(そがのまちのすくね)・物部伊莒大連(もののべのいこふのおおむらじ)・圓〔つぶら、豆夫羅〕大使夫主(おほみ)、共に國事(くにのこと)を執れり。
十一月に、磐余池(いわれのいけ)をつくる。
三年の冬十一月(しもつき)の丙寅の朔辛未に、天皇(すめらみこと)、兩枝船(ふたまたぶね)を磐余市磯池(いわれのいちしのいけ)に泛(うか)べたまう。皇妃(みめ)と各分ち乘りて遊宴(あそ)びたまふ。膳臣余磯(かしわでのおみあれし)、酒獻(たてまつ)る。時に櫻の花、御盞(おほみさかづき)に落(おちい)れり。天皇、異(あやし)びたまひて、則ち物部長眞膽連(もののべのながまいのむらじ)を召して、詔して曰はく、「是の花、非時(ときじく)にして來れり。其れ何處(いどこ)の花ならむ。汝(いまし)、自ら求むべし」とのたまふ。是に長眞膽連、獨り花を尋ねて、掖上室山(わきのかみのむろのやま)に獲(え)て、獻る。天皇、其の希有(めずら)しきことを歡びて、即ち宮の名としたまふ。故、磐余稚櫻宮(いわれのわかさくらのみや)と謂(まう)す。其れ此の縁なり。是の日に、長眞膽連の本姓(もとのかばね)を改めて、稚櫻部造(わかざくらのみやっこ)と曰(い)ふ。又、膳臣余磯(かしわでのおみあれし)を號(なづ)けて、稚櫻部臣(わかさくらべのおみ)と曰ふ。
〔訳〕磐余の稚桜の宮
二年の春一月四日、瑞齒別皇子を立てて皇太子とした。
冬十月磐余に都を作った。このとき、平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね)・蘇我満智宿禰(そがのまちのすくね)・物部伊莒大連(もののべのいこふのおおむらじ)・圓大使夫主(つぶらおほみ)らは、共に国の政治に携わった。
十一月磐余の池を作った。
三年冬十一月六日、天皇は兩股船を磐余の市磯池に浮かべられた。后とそれぞれの船に分乗して遊ばれた。膳臣(かしわでのおみ)の余磯(あれし)が酒を奉った。そのとき桜の花びらが盃に散った。天皇は怪しまれて、物部長真胆連(もののべのながいのむらじ)を召して、詔して「この花は咲くべき時でないに散ってきた。何処の花だろうか。お前が探して来い」といわれた。長真胆連は独り花を尋ねて、掖上(わきのかみ)の室山で、花を手に入れて奉った。天皇は其の珍しいことを喜んで、宮の名とされた。磐余若桜宮(いわれのわかざくらのみや)というのはこれがそのもとである。この日、長真胆連の本姓を改めて、稚桜部造とし、膳臣余磯を名付けて稚桜部臣とされた。
大津皇子(おおつのみこ、663~686年)は天武天皇の皇子。母は天智天皇皇女の大田皇女。妃は天智天皇皇女の山辺皇女。686年(朱鳥元年)9月に天武天皇が崩御すると、1ヶ月も経たない10月2日に親友の川島皇子の密告により、謀反の意有りとされて捕えられ、翌日磐余(いわれ)にある訳語田(おさだ)の自邸で死を賜ったのである。
大津皇子の死を被(たま)はりし時、
磐余(いはれ)の池の堤にして涙を流して作らす御歌一首
ももづたふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ (万葉集巻3、416)
【釈】磐余(いわれ)の池に鳴く鴨を見るのも今日限りで、私は死ぬのだろうか。
金烏西舎(きんうせいしゃ)に臨(てら)ひ
鼓声短命(こせいたんめい)を催(うなが)す
泉路(せんろ)賓主(ひんしゅ)無し
此の夕(ゆうべ)家を離(さかり)て向かふ
(訳)太陽は西に傾き家々を照らし、夕刻を告げる太鼓の音は、短命を急がすかのように聞こえる。黄泉の道には客も主人もなくただ一人、夕べには家を離れて死出の旅に出るのか・・・。
万葉集にある大伯皇女(おおくのひめみこ)の歌
神風の伊勢の国にもあらましを何しか来けむ 君もあらなくに(巻2-163)
(訳)こんなことなら伊勢の国にいたのに。どうして都に帰ってきてしまったのだろう。あなたがいるわけでもないのに
※かつて、横浜在住のIN氏に贈って貰った大津皇子の伝記「飛鳥はふぶき」(山本藤枝著・ポブラ社刊)を読んだことを思い出し、再読すべく本棚の隅に誇り塗れて本を取り出した。
荀子 大略篇 第二十七 より
78 子貢問於孔子曰:「賜倦於學矣、願息事君。」孔子曰:「《詩》云:『溫恭朝夕、執事有恪。』事君難、事君焉可息哉!」「然則、賜願息事親。」孔子曰:「《詩》云:『孝子不匱、永錫爾類。』事親難、事親焉可息哉!」「然則賜願息於妻子。」孔子曰:「《詩》云:『刑于寡妻、至于兄弟、以御於家邦。』妻子難、妻子焉可息哉!」「然則賜願息於朋友。」孔子曰:「《詩》云:『朋友攸攝、攝以威儀。』朋友難、朋友焉可息哉!」「然則賜願息耕。」孔子曰:「《詩》云:『晝爾于茅、宵爾索綯、亟其乘屋、其始播百穀。』耕難、耕焉可息哉!」「然則賜無息者乎?」孔子曰:「望其壙、皋如也、顛如也、鬲如也、此則知所息矣。」子貢曰:「大哉!死乎!君子息焉、小人休焉。」
子貢が孔子に、
「私は学問をすることに飽きました。君に仕えることによって休息したいと思いますが、どうでしょうか」
とたずねた。孔子は、
「『詩経〔商頌・那篇〕』に『朝から晩までおだやかでうやうやしく慎んで国事を処理する』とある。君に仕えることは難しい仕事である。どうして君に仕えて休息などとれようか」
と答えた。
「それならば親に仕えることによって休息したいと思いますがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・既酔篇〕』に『孝子は手をつくしてゆきわたらない所がないようにするものである。だからいつまでもお前に幸福が与えられるのだ』とある。親に仕えることはむつかしい仕事である。どうして親に仕えて休息などとれようか」
と答えた。
「それでは妻子と一緒にいることで休息をとりたいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・思斉篇〕』に『自分が模範となって妻を従わせ、それを兄弟にまでおし及ぼし、それによって家と国を治めてゆく』とある。妻子と一緒にいるのはむつかしい仕事である。妻子と一緒にいてどうして休息がとれようか」
と答えた。
「それでは友達の側で休息したいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・既酔編〕』に『友達は互いに助け合うものであり、立派な態度で助け合うものである』とある。友達と交わるのはむつかしいことである。どうして友達の側で休息などできようか」
と答えた。
「それでは田畑を耕作したいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔豳風(ひんふう)・七月篇〕』に『昼はお前は野で茅(ちがや)を刈れ、夜はお前は縄をなえ、早く屋根をふけ、多くの穀物の種をまけ』とある。農耕は忙しく辛い仕事である。どうして農耕によって休息ができようか」
と答えた。
 「そうすると私には休息するところがないのでしょうか」
「そうすると私には休息するところがないのでしょうか」
と言うと、孔子は、
「遥かに墓の盛土を見ると、高々としているし、こんもりしているし、釜をふせたようだ。ここが休息する所であることが分るだろう」
と答えた。子貢は、
「死というものは偉大なものだ、君子も小人もそこで休息するのか」
と言った。
HOLY SONNETS 10.(死よ 驕るなかれ)
Death, be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadful, for thou art not so ;
For those, whom thou think'st thou dost overthrow,
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.
From rest and sleep, which but thy pictures be,
Much pleasure, then from thee much more must flow,
And soonest our best men with thee do go,
Rest of their bones, and soul's delivery.
Thou'rt slave to Fate, chance, kings, and desperate men,
And dost with poison, war, and sickness dwell,
And poppy, or charms can make us sleep as well,
And better than thy stroke ; why swell'st thou then ?
One short sleep past, we wake eternally,
And Death shall be no more ; Death, thou shalt die.
 死よ驕るなかれ 汝を力強く恐ろしいと
死よ驕るなかれ 汝を力強く恐ろしいと
いう者もいるが 決してそうではない
汝が倒したと考える者は 死にはしない
おろかな死よ 汝は私を殺せないのだ
汝の似姿たる休息と安眠からは
より大きな喜びが生まれ出てくる
最も優れたものが死を急ぐのは
骨に安らぎを与え 魂を開放させるため
汝は運命や偶然、王侯や絶望した人の奴隷
汝は牢獄、戦争、疫病の隣人
芥子粒や呪文も同じように人を眠らせる
汝の一撃よりもよく だから威張ることはない
束の間の眠りの後我々は永遠に甦る
そこにはもはや死はない 死よ 汝こそが死ぬのだ
78 子貢問於孔子曰:「賜倦於學矣、願息事君。」孔子曰:「《詩》云:『溫恭朝夕、執事有恪。』事君難、事君焉可息哉!」「然則、賜願息事親。」孔子曰:「《詩》云:『孝子不匱、永錫爾類。』事親難、事親焉可息哉!」「然則賜願息於妻子。」孔子曰:「《詩》云:『刑于寡妻、至于兄弟、以御於家邦。』妻子難、妻子焉可息哉!」「然則賜願息於朋友。」孔子曰:「《詩》云:『朋友攸攝、攝以威儀。』朋友難、朋友焉可息哉!」「然則賜願息耕。」孔子曰:「《詩》云:『晝爾于茅、宵爾索綯、亟其乘屋、其始播百穀。』耕難、耕焉可息哉!」「然則賜無息者乎?」孔子曰:「望其壙、皋如也、顛如也、鬲如也、此則知所息矣。」子貢曰:「大哉!死乎!君子息焉、小人休焉。」
子貢が孔子に、
「私は学問をすることに飽きました。君に仕えることによって休息したいと思いますが、どうでしょうか」
とたずねた。孔子は、
「『詩経〔商頌・那篇〕』に『朝から晩までおだやかでうやうやしく慎んで国事を処理する』とある。君に仕えることは難しい仕事である。どうして君に仕えて休息などとれようか」
と答えた。
「それならば親に仕えることによって休息したいと思いますがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・既酔篇〕』に『孝子は手をつくしてゆきわたらない所がないようにするものである。だからいつまでもお前に幸福が与えられるのだ』とある。親に仕えることはむつかしい仕事である。どうして親に仕えて休息などとれようか」
と答えた。
「それでは妻子と一緒にいることで休息をとりたいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・思斉篇〕』に『自分が模範となって妻を従わせ、それを兄弟にまでおし及ぼし、それによって家と国を治めてゆく』とある。妻子と一緒にいるのはむつかしい仕事である。妻子と一緒にいてどうして休息がとれようか」
と答えた。
「それでは友達の側で休息したいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・既酔編〕』に『友達は互いに助け合うものであり、立派な態度で助け合うものである』とある。友達と交わるのはむつかしいことである。どうして友達の側で休息などできようか」
と答えた。
「それでは田畑を耕作したいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔豳風(ひんふう)・七月篇〕』に『昼はお前は野で茅(ちがや)を刈れ、夜はお前は縄をなえ、早く屋根をふけ、多くの穀物の種をまけ』とある。農耕は忙しく辛い仕事である。どうして農耕によって休息ができようか」
と答えた。
と言うと、孔子は、
「遥かに墓の盛土を見ると、高々としているし、こんもりしているし、釜をふせたようだ。ここが休息する所であることが分るだろう」
と答えた。子貢は、
「死というものは偉大なものだ、君子も小人もそこで休息するのか」
と言った。
HOLY SONNETS 10.(死よ 驕るなかれ)
Death, be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadful, for thou art not so ;
For those, whom thou think'st thou dost overthrow,
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.
From rest and sleep, which but thy pictures be,
Much pleasure, then from thee much more must flow,
And soonest our best men with thee do go,
Rest of their bones, and soul's delivery.
Thou'rt slave to Fate, chance, kings, and desperate men,
And dost with poison, war, and sickness dwell,
And poppy, or charms can make us sleep as well,
And better than thy stroke ; why swell'st thou then ?
One short sleep past, we wake eternally,
And Death shall be no more ; Death, thou shalt die.
いう者もいるが 決してそうではない
汝が倒したと考える者は 死にはしない
おろかな死よ 汝は私を殺せないのだ
汝の似姿たる休息と安眠からは
より大きな喜びが生まれ出てくる
最も優れたものが死を急ぐのは
骨に安らぎを与え 魂を開放させるため
汝は運命や偶然、王侯や絶望した人の奴隷
汝は牢獄、戦争、疫病の隣人
芥子粒や呪文も同じように人を眠らせる
汝の一撃よりもよく だから威張ることはない
束の間の眠りの後我々は永遠に甦る
そこにはもはや死はない 死よ 汝こそが死ぬのだ
プロフィール
ハンドルネーム:
目高 拙痴无
年齢:
93
誕生日:
1932/02/04
自己紹介:
くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。
sechin@nethome.ne.jp です。
sechin@nethome.ne.jp です。
カレンダー
| 04 | 2025/05 | 06 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新コメント
[enken 02/23]
[中村東樹 02/04]
[m、m 02/04]
[爺の姪 01/13]
[レンマ学(メタ数学) 01/02]
[m.m 10/12]
[爺の姪 10/01]
[あは♡ 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター