瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り
ウェブニュースより
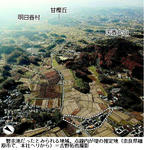
 日本書紀記述の「磐余池」の堤跡など出土…奈良・橿原 ―― 奈良県橿原市東池尻町で、「日本書紀」や「万葉集」に登場する人工池「磐余池(いわれいけ)」の遺構とみられる堤跡と大型建物跡(6世紀後半)などが出土したと、市教委が15日発表した。池のほとりでは聖徳太子の父・用明(ようめい)天皇(在位585~587年)が宮殿を営んだとされ、建物跡はその一部との見方が出ている。飛鳥時代(7世紀)より前の天皇の宮殿は確認されておらず、最古の宮殿跡の可能性もある。/一帯は大和三山・天香久山(あまのかぐやま)の北にあたる藤原京跡の一角。「池」のつく地名が多いことや地形などから池の候補地とされていた。10月から道路工事に伴って発掘したところ、盛り土をした長さ81メートル、幅8メートル、高さ2メートルの堤跡を確認した。/周辺の地形などから、堤は「へ」の字状で、最大幅55メートル、高さ3メートル、長さ約330メートルと推定。複数の谷の水をダムのようにせき止め、南北約600メートル、東西約700メートルの範囲に、手の形をした面積8万7500平方メートルの池を形成したらしい。平安時代までは存在したとみられる。/堤跡の上では大型建物跡1棟(東西4メートル、南北17.5メートル以上)など建物6棟や塀跡2列が見つかった。/日本書紀には、磐余池は5世紀前半に履中(りちゅう)天皇が造り、585年には用明天皇が池のほとりに「磐余池辺双槻宮(いわれいけべのなみつきのみや)」を設けたとある。万葉集でも大津皇子(みこ)の辞世の歌に登場する。これまで最古の人工池は7世紀前半の狭山池(大阪府大阪狭山市、現存)とされるが、今回の遺構はこれを遡る。/和田萃(あつむ)・京都教育大名誉教授(古代史)の話「堤は天香久山を望めるなど眺めがよい所で、池は灌漑(かんがい)用だけでなく観賞用でもあったのだろう。大型建物は用明天皇の宮殿の一角と想定でき、一帯が大和王権にとって重要な場所だったことがわかる」 (2011年12月16日 読売新聞)
日本書紀記述の「磐余池」の堤跡など出土…奈良・橿原 ―― 奈良県橿原市東池尻町で、「日本書紀」や「万葉集」に登場する人工池「磐余池(いわれいけ)」の遺構とみられる堤跡と大型建物跡(6世紀後半)などが出土したと、市教委が15日発表した。池のほとりでは聖徳太子の父・用明(ようめい)天皇(在位585~587年)が宮殿を営んだとされ、建物跡はその一部との見方が出ている。飛鳥時代(7世紀)より前の天皇の宮殿は確認されておらず、最古の宮殿跡の可能性もある。/一帯は大和三山・天香久山(あまのかぐやま)の北にあたる藤原京跡の一角。「池」のつく地名が多いことや地形などから池の候補地とされていた。10月から道路工事に伴って発掘したところ、盛り土をした長さ81メートル、幅8メートル、高さ2メートルの堤跡を確認した。/周辺の地形などから、堤は「へ」の字状で、最大幅55メートル、高さ3メートル、長さ約330メートルと推定。複数の谷の水をダムのようにせき止め、南北約600メートル、東西約700メートルの範囲に、手の形をした面積8万7500平方メートルの池を形成したらしい。平安時代までは存在したとみられる。/堤跡の上では大型建物跡1棟(東西4メートル、南北17.5メートル以上)など建物6棟や塀跡2列が見つかった。/日本書紀には、磐余池は5世紀前半に履中(りちゅう)天皇が造り、585年には用明天皇が池のほとりに「磐余池辺双槻宮(いわれいけべのなみつきのみや)」を設けたとある。万葉集でも大津皇子(みこ)の辞世の歌に登場する。これまで最古の人工池は7世紀前半の狭山池(大阪府大阪狭山市、現存)とされるが、今回の遺構はこれを遡る。/和田萃(あつむ)・京都教育大名誉教授(古代史)の話「堤は天香久山を望めるなど眺めがよい所で、池は灌漑(かんがい)用だけでなく観賞用でもあったのだろう。大型建物は用明天皇の宮殿の一角と想定でき、一帯が大和王権にとって重要な場所だったことがわかる」 (2011年12月16日 読売新聞)
日本書紀 巻十二 去来穂別天皇(いざほわけのすめらみこと)〔履中天皇〕より
二年の春正月(むつき)の丙午の朔己酉に、瑞齒別皇子(みつはわけのみこ)を立てて儲君(ひつぎのみこ)とす。
冬十月(かむなづき)に、磐余に都つくる。是の時に當りて、平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね)・蘇我満智宿禰(そがのまちのすくね)・物部伊莒大連(もののべのいこふのおおむらじ)・圓〔つぶら、豆夫羅〕大使夫主(おほみ)、共に國事(くにのこと)を執れり。
十一月に、磐余池(いわれのいけ)をつくる。
三年の冬十一月(しもつき)の丙寅の朔辛未に、天皇(すめらみこと)、兩枝船(ふたまたぶね)を磐余市磯池(いわれのいちしのいけ)に泛(うか)べたまう。皇妃(みめ)と各分ち乘りて遊宴(あそ)びたまふ。膳臣余磯(かしわでのおみあれし)、酒獻(たてまつ)る。時に櫻の花、御盞(おほみさかづき)に落(おちい)れり。天皇、異(あやし)びたまひて、則ち物部長眞膽連(もののべのながまいのむらじ)を召して、詔して曰はく、「是の花、非時(ときじく)にして來れり。其れ何處(いどこ)の花ならむ。汝(いまし)、自ら求むべし」とのたまふ。是に長眞膽連、獨り花を尋ねて、掖上室山(わきのかみのむろのやま)に獲(え)て、獻る。天皇、其の希有(めずら)しきことを歡びて、即ち宮の名としたまふ。故、磐余稚櫻宮(いわれのわかさくらのみや)と謂(まう)す。其れ此の縁なり。是の日に、長眞膽連の本姓(もとのかばね)を改めて、稚櫻部造(わかざくらのみやっこ)と曰(い)ふ。又、膳臣余磯(かしわでのおみあれし)を號(なづ)けて、稚櫻部臣(わかさくらべのおみ)と曰ふ。
〔訳〕磐余の稚桜の宮
二年の春一月四日、瑞齒別皇子を立てて皇太子とした。
冬十月磐余に都を作った。このとき、平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね)・蘇我満智宿禰(そがのまちのすくね)・物部伊莒大連(もののべのいこふのおおむらじ)・圓大使夫主(つぶらおほみ)らは、共に国の政治に携わった。
十一月磐余の池を作った。
三年冬十一月六日、天皇は兩股船を磐余の市磯池に浮かべられた。后とそれぞれの船に分乗して遊ばれた。膳臣(かしわでのおみ)の余磯(あれし)が酒を奉った。そのとき桜の花びらが盃に散った。天皇は怪しまれて、物部長真胆連(もののべのながいのむらじ)を召して、詔して「この花は咲くべき時でないに散ってきた。何処の花だろうか。お前が探して来い」といわれた。長真胆連は独り花を尋ねて、掖上(わきのかみ)の室山で、花を手に入れて奉った。天皇は其の珍しいことを喜んで、宮の名とされた。磐余若桜宮(いわれのわかざくらのみや)というのはこれがそのもとである。この日、長真胆連の本姓を改めて、稚桜部造とし、膳臣余磯を名付けて稚桜部臣とされた。
大津皇子(おおつのみこ、663~686年)は天武天皇の皇子。母は天智天皇皇女の大田皇女。妃は天智天皇皇女の山辺皇女。686年(朱鳥元年)9月に天武天皇が崩御すると、1ヶ月も経たない10月2日に親友の川島皇子の密告により、謀反の意有りとされて捕えられ、翌日磐余(いわれ)にある訳語田(おさだ)の自邸で死を賜ったのである。
大津皇子の死を被(たま)はりし時、
磐余(いはれ)の池の堤にして涙を流して作らす御歌一首
ももづたふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ (万葉集巻3、416)
【釈】磐余(いわれ)の池に鳴く鴨を見るのも今日限りで、私は死ぬのだろうか。
 五言臨終一絶 〔懐風藻〕
五言臨終一絶 〔懐風藻〕
金烏西舎(きんうせいしゃ)に臨(てら)ひ
鼓声短命(こせいたんめい)を催(うなが)す
泉路(せんろ)賓主(ひんしゅ)無し
此の夕(ゆうべ)家を離(さかり)て向かふ
(訳)太陽は西に傾き家々を照らし、夕刻を告げる太鼓の音は、短命を急がすかのように聞こえる。黄泉の道には客も主人もなくただ一人、夕べには家を離れて死出の旅に出るのか・・・。
万葉集にある大伯皇女(おおくのひめみこ)の歌
神風の伊勢の国にもあらましを何しか来けむ 君もあらなくに(巻2-163)
(訳)こんなことなら伊勢の国にいたのに。どうして都に帰ってきてしまったのだろう。あなたがいるわけでもないのに
※かつて、横浜在住のIN氏に贈って貰った大津皇子の伝記「飛鳥はふぶき」(山本藤枝著・ポブラ社刊)を読んだことを思い出し、再読すべく本棚の隅に誇り塗れて本を取り出した。
日本書紀 巻十二 去来穂別天皇(いざほわけのすめらみこと)〔履中天皇〕より
二年の春正月(むつき)の丙午の朔己酉に、瑞齒別皇子(みつはわけのみこ)を立てて儲君(ひつぎのみこ)とす。
冬十月(かむなづき)に、磐余に都つくる。是の時に當りて、平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね)・蘇我満智宿禰(そがのまちのすくね)・物部伊莒大連(もののべのいこふのおおむらじ)・圓〔つぶら、豆夫羅〕大使夫主(おほみ)、共に國事(くにのこと)を執れり。
十一月に、磐余池(いわれのいけ)をつくる。
三年の冬十一月(しもつき)の丙寅の朔辛未に、天皇(すめらみこと)、兩枝船(ふたまたぶね)を磐余市磯池(いわれのいちしのいけ)に泛(うか)べたまう。皇妃(みめ)と各分ち乘りて遊宴(あそ)びたまふ。膳臣余磯(かしわでのおみあれし)、酒獻(たてまつ)る。時に櫻の花、御盞(おほみさかづき)に落(おちい)れり。天皇、異(あやし)びたまひて、則ち物部長眞膽連(もののべのながまいのむらじ)を召して、詔して曰はく、「是の花、非時(ときじく)にして來れり。其れ何處(いどこ)の花ならむ。汝(いまし)、自ら求むべし」とのたまふ。是に長眞膽連、獨り花を尋ねて、掖上室山(わきのかみのむろのやま)に獲(え)て、獻る。天皇、其の希有(めずら)しきことを歡びて、即ち宮の名としたまふ。故、磐余稚櫻宮(いわれのわかさくらのみや)と謂(まう)す。其れ此の縁なり。是の日に、長眞膽連の本姓(もとのかばね)を改めて、稚櫻部造(わかざくらのみやっこ)と曰(い)ふ。又、膳臣余磯(かしわでのおみあれし)を號(なづ)けて、稚櫻部臣(わかさくらべのおみ)と曰ふ。
〔訳〕磐余の稚桜の宮
二年の春一月四日、瑞齒別皇子を立てて皇太子とした。
冬十月磐余に都を作った。このとき、平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね)・蘇我満智宿禰(そがのまちのすくね)・物部伊莒大連(もののべのいこふのおおむらじ)・圓大使夫主(つぶらおほみ)らは、共に国の政治に携わった。
十一月磐余の池を作った。
三年冬十一月六日、天皇は兩股船を磐余の市磯池に浮かべられた。后とそれぞれの船に分乗して遊ばれた。膳臣(かしわでのおみ)の余磯(あれし)が酒を奉った。そのとき桜の花びらが盃に散った。天皇は怪しまれて、物部長真胆連(もののべのながいのむらじ)を召して、詔して「この花は咲くべき時でないに散ってきた。何処の花だろうか。お前が探して来い」といわれた。長真胆連は独り花を尋ねて、掖上(わきのかみ)の室山で、花を手に入れて奉った。天皇は其の珍しいことを喜んで、宮の名とされた。磐余若桜宮(いわれのわかざくらのみや)というのはこれがそのもとである。この日、長真胆連の本姓を改めて、稚桜部造とし、膳臣余磯を名付けて稚桜部臣とされた。
大津皇子(おおつのみこ、663~686年)は天武天皇の皇子。母は天智天皇皇女の大田皇女。妃は天智天皇皇女の山辺皇女。686年(朱鳥元年)9月に天武天皇が崩御すると、1ヶ月も経たない10月2日に親友の川島皇子の密告により、謀反の意有りとされて捕えられ、翌日磐余(いわれ)にある訳語田(おさだ)の自邸で死を賜ったのである。
大津皇子の死を被(たま)はりし時、
磐余(いはれ)の池の堤にして涙を流して作らす御歌一首
ももづたふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ (万葉集巻3、416)
【釈】磐余(いわれ)の池に鳴く鴨を見るのも今日限りで、私は死ぬのだろうか。
金烏西舎(きんうせいしゃ)に臨(てら)ひ
鼓声短命(こせいたんめい)を催(うなが)す
泉路(せんろ)賓主(ひんしゅ)無し
此の夕(ゆうべ)家を離(さかり)て向かふ
(訳)太陽は西に傾き家々を照らし、夕刻を告げる太鼓の音は、短命を急がすかのように聞こえる。黄泉の道には客も主人もなくただ一人、夕べには家を離れて死出の旅に出るのか・・・。
万葉集にある大伯皇女(おおくのひめみこ)の歌
神風の伊勢の国にもあらましを何しか来けむ 君もあらなくに(巻2-163)
(訳)こんなことなら伊勢の国にいたのに。どうして都に帰ってきてしまったのだろう。あなたがいるわけでもないのに
※かつて、横浜在住のIN氏に贈って貰った大津皇子の伝記「飛鳥はふぶき」(山本藤枝著・ポブラ社刊)を読んだことを思い出し、再読すべく本棚の隅に誇り塗れて本を取り出した。
この記事にコメントする
プロフィール
ハンドルネーム:
目高 拙痴无
年齢:
93
誕生日:
1932/02/04
自己紹介:
くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。
sechin@nethome.ne.jp です。
sechin@nethome.ne.jp です。
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
最新コメント
[enken 02/23]
[中村東樹 02/04]
[m、m 02/04]
[爺の姪 01/13]
[レンマ学(メタ数学) 01/02]
[m.m 10/12]
[爺の姪 10/01]
[あは♡ 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター