瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り
彼岸明けを明日に控えた本日はマイチの満中陰(四十九日忌)である。中陰(ちゅういん)または中有(ちゅうう)とは、仏教で人が死んでからの49日間を指す。死者があの世へ旅立つ期間。四十九日。死者が生と死・陰と陽の狭間に居るため中陰というのだそうだ。彼は二河白道を突っ切って彼岸に達したことであろう。

 期せずしてマイチと同期のアコから絵葉書が届いた。
期せずしてマイチと同期のアコから絵葉書が届いた。
古いアルバムから塾友同期「花のニッパチ(昭和28年生まれ)」の高校卒業記念の会を上野池之端の東天紅で催したとき、不忍池で撮った写真を取り出して、スキャンしてみた。
 蒿里曲 漢・樂府
蒿里曲 漢・樂府
蒿里誰家地、 蒿里 誰(た)が家の 地ぞ、
聚斂魂魄無賢愚。 魂魄を聚斂して 賢愚無し。
鬼伯一何相催促、 鬼伯 一に何ぞ 相ひ 催促し、
人命不得少踟蹰。 人命 少(しばら)くも 踟蹰(ちちゅう)するを得ず。
〔訳〕黄泉の国は 誰の土地
魂はここに集まる 賢愚の区別なく
鬼の首領(かしら)の催促の何と厳しく
人の命は 少しの猶予も 許されぬ
古いアルバムから塾友同期「花のニッパチ(昭和28年生まれ)」の高校卒業記念の会を上野池之端の東天紅で催したとき、不忍池で撮った写真を取り出して、スキャンしてみた。
蒿里誰家地、 蒿里 誰(た)が家の 地ぞ、
聚斂魂魄無賢愚。 魂魄を聚斂して 賢愚無し。
鬼伯一何相催促、 鬼伯 一に何ぞ 相ひ 催促し、
人命不得少踟蹰。 人命 少(しばら)くも 踟蹰(ちちゅう)するを得ず。
〔訳〕黄泉の国は 誰の土地
魂はここに集まる 賢愚の区別なく
鬼の首領(かしら)の催促の何と厳しく
人の命は 少しの猶予も 許されぬ
昨日、彼岸の中日に門司のJT氏より訃報が入った。
 水門会のAT氏が亡くなったそうだ。午後1時頃、介護に来たヘルパーさんが、自宅で倒れている所を発見したという。前日19日に、横浜のTK氏より電話があり、AT氏の噂をしていたばかりだ。
水門会のAT氏が亡くなったそうだ。午後1時頃、介護に来たヘルパーさんが、自宅で倒れている所を発見したという。前日19日に、横浜のTK氏より電話があり、AT氏の噂をしていたばかりだ。
かれは、随分前から透析治療を受けていたと聞く。JT氏の話によると脳梗塞で倒れたと言うことだ。
明日はわが身、心から冥福を祈るばかりだ。 合掌
薤露歌 漢・無名氏
薤上露、 薤上の 露、
何易晞。 何ぞ 晞(かわ)き 易(やす)き。
露晞明朝更復落、 露 晞(かわ)けば 明朝 更に復(ま)た 落つ、
人死一去何時歸。 人 死して 一たび去れば 何(いづ)れの時にか 歸らん。
 〔訳〕薤(おおにら)の上におりた露の
〔訳〕薤(おおにら)の上におりた露の
何とたちまちかわくことか
露はたとえかわいても 明日の朝にはまたおりる
人は一たび死んでしまえば もとにもどるもどる時はない
かれは、随分前から透析治療を受けていたと聞く。JT氏の話によると脳梗塞で倒れたと言うことだ。
明日はわが身、心から冥福を祈るばかりだ。 合掌
薤露歌 漢・無名氏
薤上露、 薤上の 露、
何易晞。 何ぞ 晞(かわ)き 易(やす)き。
露晞明朝更復落、 露 晞(かわ)けば 明朝 更に復(ま)た 落つ、
人死一去何時歸。 人 死して 一たび去れば 何(いづ)れの時にか 歸らん。
何とたちまちかわくことか
露はたとえかわいても 明日の朝にはまたおりる
人は一たび死んでしまえば もとにもどるもどる時はない
本日は彼岸の中日、すなわち春分の日。
煩悩や迷いに満ちたこの世をこちら側の岸『此岸(しがん)』と言うのに対して、「煩悩を脱した悟りの境地」にあるあの世ことを『彼岸』というのだそうだ。春分の日〔秋分の日も〕は昼と夜の長さが同じになり、仏教的には「さとり」と「迷い」の境地であり「現世」と「浄土」の接する日として昔から仏教行事が行われている。日本で初めて彼岸会(ひがんえ)が行われたのは「大同元年〔806年〕崇道天皇の奉為に諸国国分寺の僧として春秋二仲別七日金剛般若経を読まわしむ」と「日本後紀」に記されているという。
 彼岸について説明しているものとして「二河白道(にがびゃくどう)」の例えがある。「はるばる西をめざしてきた旅人の前に二つの河が現れた。南に火の河、北に水の河が現れる。旅人は東に逃げようとするが途中に悪者や獣が待ち構えていた。旅人は進退窮まったが、東の岸からは西に進めという励ましの声、西の道からは迷わずに進めという声が聞こえてきた。旅人は心を一筋に一心不乱に進み、ようやく西の岸にたどりつくことができた」というものであるが、ここでは水の河はむさぼりの心やとらわれの心を表し、火の河は怒りや憎しみの心を表しているのだという。つまり河は現世の人間の姿を表現し、東の岸は現世〔此岸〕で西の岸は極楽(彼岸)を表す。「彼岸」とは現世の此岸から涅槃の彼岸に至る到彼岸を表すものである。彼岸は中日をさかいに前後三日間あわせて一週間を彼岸の日というものだという。
彼岸について説明しているものとして「二河白道(にがびゃくどう)」の例えがある。「はるばる西をめざしてきた旅人の前に二つの河が現れた。南に火の河、北に水の河が現れる。旅人は東に逃げようとするが途中に悪者や獣が待ち構えていた。旅人は進退窮まったが、東の岸からは西に進めという励ましの声、西の道からは迷わずに進めという声が聞こえてきた。旅人は心を一筋に一心不乱に進み、ようやく西の岸にたどりつくことができた」というものであるが、ここでは水の河はむさぼりの心やとらわれの心を表し、火の河は怒りや憎しみの心を表しているのだという。つまり河は現世の人間の姿を表現し、東の岸は現世〔此岸〕で西の岸は極楽(彼岸)を表す。「彼岸」とは現世の此岸から涅槃の彼岸に至る到彼岸を表すものである。彼岸は中日をさかいに前後三日間あわせて一週間を彼岸の日というものだという。
今朝のウェブニュースより
小沢元代表:「政権挫折狙う不当捜査」 最後まで特捜批判 ――「特捜部は不当な捜査で検察審査会の強制起訴を誘導した」。東京地裁での19日の最終弁論で、民主党の小沢一郎元代表(69)はこれまでと同様、東京地検特捜部への捜査批判を展開し、自らの潔白を主張した。昨年10月の初公判から5カ月余り。政治資金規正法違反(虚偽記載)での強制起訴後、「法廷で真実を述べる」と話した小沢元代表の法廷での主張は国民に理解されたのか。政界実力者への審判は4月26日に下される。
「私を強制捜査することで政権交代を阻止し、強制起訴することで新政権を挫折させようとした」。弁護人の最終弁論に引き続き行われた最終意見陳述で、小沢元代表は力のこもった低い声で約10分間をかけ、用意した書面を読み上げた。/書面では強制起訴に至った経緯について「(大阪地検特捜部の前田恒彦元検事の)証拠改ざん事件を上回る悪質さで、小沢有罪ありきの虚偽の捜査報告書を検察審に提供した」とし、特捜部が起訴議決を強力に誘導したと痛烈に批判。最大の争点だった元秘書3人との共謀についても「絶対にない」と断言した。その上で「東日本大震災からの復興は本格化していない。日本の経済・社会の立て直しは一刻の猶予も許されない」と政治家としての立場を強調して締めくくった。
小沢元代表の弁護団は閉廷後に司法記者クラブで記者会見。主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は「(有罪を立証する)証拠が不足しており、最終弁論に向けて議論をすればするほど無罪の確信が深まった」と自信を見せた。また弁護士が検察官役を務めた特異な裁判を振り返り、「後半になると検察官のようになってきて強引な主張も散見されたが、(同じ弁護士としての)信頼感があった」と感想を述べた。
一方、指定弁護士の大室俊三弁護士も取材に応じ、「無罪を主張する場合、積極的に対峙(たいじ)する事実を述べるが、(弁護側の主張には)それが少ない印象だった」と話し、有罪判決に向けた自信をうかがわせた。 毎日新聞 2012年3月19日 20時55分(最終更新 3月19日 22時28分)
 スカイツリーの麓に海の神秘満載の「すみだ水族館」がオープン! ―― 5月22日(火)のグランドオープンに向け、ますますの盛り上がりを見せている東京スカイツリーとその周辺地域・東京スカイツリータウン。3月19日には、そんな同タウン内でスカイツリーと同日オープンする都市型水族館「すみだ水族館」の記者説明会が開催され、会場にはマスコットキャラクターのソラカラちゃんとテッペンペンも駆けつけた。
スカイツリーの麓に海の神秘満載の「すみだ水族館」がオープン! ―― 5月22日(火)のグランドオープンに向け、ますますの盛り上がりを見せている東京スカイツリーとその周辺地域・東京スカイツリータウン。3月19日には、そんな同タウン内でスカイツリーと同日オープンする都市型水族館「すみだ水族館」の記者説明会が開催され、会場にはマスコットキャラクターのソラカラちゃんとテッペンペンも駆けつけた。
「すみだ水族館」は、独創的な展示方法にこだわり、開業から8年近く経った今でも高い集客率を維持し続けている「新江ノ島水族館」を手がけたオリックス不動産が開発に携わった施設だけあり、今の時代に即した最新技術や展示方法が数多く導入されている。なかでも人工海水製造システムは画期的で、水槽内の生物に快適な環境を提供できるだけでなく、大型車両による海水運搬のコストカットやCO2排出量の削減など、様々な面でのメリットも期待されているという。
また館内には、水を取り巻く自然の景色を水槽内に凝縮し、光合成の瞬間を確認することができる「水のきらめき 自然水景」や、色々な種類のクラゲが飼育されている「ゆりかごの連なりPart1 水の記憶 クラゲ」、美しいサンゴ礁を360度全方向から鑑賞できる4連のスクエア型水槽「光と水のはぐくみ サンゴ礁」など、見せ方にこだわった展示ブースが多数設置。さらに“東京諸島の海”がテーマの大型水槽「いのちのゆりかご・水の恵み 東京大水槽」や、約50mのスロープで東京湾や伊豆諸島、小笠原諸島に生息する生き物たちの姿が見られる「つながるいのち 東京湾・東京諸島」、国内最大級の屋内解放プール型水槽でペンギンやオットセイを間近で見ることができる「水といのちの戯れペンギン・オットセイ」といった大規模なブースもあるので、これらも見逃せないポイントだ。
東京スカイツリーと並び同タウンの注目スポットになること間違いなしの「すみだ水族館」。4月1日(日)より、通常の2回分の入場料金で1年間に何回でも入場することができるお得な年間パスポートも発売されるので、魚たちに癒されたい人は年間パスポートを購入し、何度も足繁く通ってみてはいかがだろうか。
■「すみだ水族館」 オープン日:5月22日(火) 営業時間:9:00~21:00 休館日:なし
一般料金:大人2000円、高校生500円、中小学生1000円、幼児(3歳以上)600円
年間パスポート:大人4000円、高校生3000円、中小学生2000円、幼児(3歳以上)1200円※4月1日(日)より先行発売 (2012年3月19日 東京ウォーカー)
煩悩や迷いに満ちたこの世をこちら側の岸『此岸(しがん)』と言うのに対して、「煩悩を脱した悟りの境地」にあるあの世ことを『彼岸』というのだそうだ。春分の日〔秋分の日も〕は昼と夜の長さが同じになり、仏教的には「さとり」と「迷い」の境地であり「現世」と「浄土」の接する日として昔から仏教行事が行われている。日本で初めて彼岸会(ひがんえ)が行われたのは「大同元年〔806年〕崇道天皇の奉為に諸国国分寺の僧として春秋二仲別七日金剛般若経を読まわしむ」と「日本後紀」に記されているという。
今朝のウェブニュースより
小沢元代表:「政権挫折狙う不当捜査」 最後まで特捜批判 ――「特捜部は不当な捜査で検察審査会の強制起訴を誘導した」。東京地裁での19日の最終弁論で、民主党の小沢一郎元代表(69)はこれまでと同様、東京地検特捜部への捜査批判を展開し、自らの潔白を主張した。昨年10月の初公判から5カ月余り。政治資金規正法違反(虚偽記載)での強制起訴後、「法廷で真実を述べる」と話した小沢元代表の法廷での主張は国民に理解されたのか。政界実力者への審判は4月26日に下される。
「私を強制捜査することで政権交代を阻止し、強制起訴することで新政権を挫折させようとした」。弁護人の最終弁論に引き続き行われた最終意見陳述で、小沢元代表は力のこもった低い声で約10分間をかけ、用意した書面を読み上げた。/書面では強制起訴に至った経緯について「(大阪地検特捜部の前田恒彦元検事の)証拠改ざん事件を上回る悪質さで、小沢有罪ありきの虚偽の捜査報告書を検察審に提供した」とし、特捜部が起訴議決を強力に誘導したと痛烈に批判。最大の争点だった元秘書3人との共謀についても「絶対にない」と断言した。その上で「東日本大震災からの復興は本格化していない。日本の経済・社会の立て直しは一刻の猶予も許されない」と政治家としての立場を強調して締めくくった。
小沢元代表の弁護団は閉廷後に司法記者クラブで記者会見。主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は「(有罪を立証する)証拠が不足しており、最終弁論に向けて議論をすればするほど無罪の確信が深まった」と自信を見せた。また弁護士が検察官役を務めた特異な裁判を振り返り、「後半になると検察官のようになってきて強引な主張も散見されたが、(同じ弁護士としての)信頼感があった」と感想を述べた。
一方、指定弁護士の大室俊三弁護士も取材に応じ、「無罪を主張する場合、積極的に対峙(たいじ)する事実を述べるが、(弁護側の主張には)それが少ない印象だった」と話し、有罪判決に向けた自信をうかがわせた。 毎日新聞 2012年3月19日 20時55分(最終更新 3月19日 22時28分)
「すみだ水族館」は、独創的な展示方法にこだわり、開業から8年近く経った今でも高い集客率を維持し続けている「新江ノ島水族館」を手がけたオリックス不動産が開発に携わった施設だけあり、今の時代に即した最新技術や展示方法が数多く導入されている。なかでも人工海水製造システムは画期的で、水槽内の生物に快適な環境を提供できるだけでなく、大型車両による海水運搬のコストカットやCO2排出量の削減など、様々な面でのメリットも期待されているという。
また館内には、水を取り巻く自然の景色を水槽内に凝縮し、光合成の瞬間を確認することができる「水のきらめき 自然水景」や、色々な種類のクラゲが飼育されている「ゆりかごの連なりPart1 水の記憶 クラゲ」、美しいサンゴ礁を360度全方向から鑑賞できる4連のスクエア型水槽「光と水のはぐくみ サンゴ礁」など、見せ方にこだわった展示ブースが多数設置。さらに“東京諸島の海”がテーマの大型水槽「いのちのゆりかご・水の恵み 東京大水槽」や、約50mのスロープで東京湾や伊豆諸島、小笠原諸島に生息する生き物たちの姿が見られる「つながるいのち 東京湾・東京諸島」、国内最大級の屋内解放プール型水槽でペンギンやオットセイを間近で見ることができる「水といのちの戯れペンギン・オットセイ」といった大規模なブースもあるので、これらも見逃せないポイントだ。
東京スカイツリーと並び同タウンの注目スポットになること間違いなしの「すみだ水族館」。4月1日(日)より、通常の2回分の入場料金で1年間に何回でも入場することができるお得な年間パスポートも発売されるので、魚たちに癒されたい人は年間パスポートを購入し、何度も足繁く通ってみてはいかがだろうか。
■「すみだ水族館」 オープン日:5月22日(火) 営業時間:9:00~21:00 休館日:なし
一般料金:大人2000円、高校生500円、中小学生1000円、幼児(3歳以上)600円
年間パスポート:大人4000円、高校生3000円、中小学生2000円、幼児(3歳以上)1200円※4月1日(日)より先行発売 (2012年3月19日 東京ウォーカー)
淺草では17日・18日の土・日に、「舟渡御」と呼ばれる舟祭りが行われた。これは、初夏に行われる、三社祭の起源ともいうべきもので、浅草神社のホームページによれば、
 「江戸時代には、御縁日である3月18日の大祭前夜(17日)浅草神社の御神体がお移りになられた一之宮・二之宮・三之宮三基の御神輿を観音本堂外陣に『お堂上げ』にて安置し、観音様と三社の三人の神様に共に一晩を過ごして頂きました。また、この時には、『神事びんざさら舞(現在都民俗無形文化財)』が堂前の舞台で奉演されています。/翌大祭当日(18日)には、各町会より山車が観音本堂前に参詣の上、各々の趣向でその絢爛・豪華さを競い合い芸能を演じ、随身門(現在の二天門)を出て自分の町へ帰りました。/その後、御神輿三基が「お堂下げ」にて本堂外陣から降ろされると、一之宮を先頭に浅草御門(現在の浅草橋際)の舟乗り場迄担ぎ運ばれました。そして待機している大森(品川)在住の漁師によって供奉される舟に各御神輿が乗せられ、浅草川(現隅田川)を漕ぎ上がって駒形岸或いは花川戸岸から上陸の後、浅草神社に担ぎ帰られたと云われています。/当時は浅草寺と一体となった行事で、『観音祭』又は『浅草祭』とも呼ばれてもいましたが、江戸末期にとある理由により廃絶し、昭和の時代に一度斎行されたものの、明治以降は御神輿が氏子各町を渡御するのみとなりました」
「江戸時代には、御縁日である3月18日の大祭前夜(17日)浅草神社の御神体がお移りになられた一之宮・二之宮・三之宮三基の御神輿を観音本堂外陣に『お堂上げ』にて安置し、観音様と三社の三人の神様に共に一晩を過ごして頂きました。また、この時には、『神事びんざさら舞(現在都民俗無形文化財)』が堂前の舞台で奉演されています。/翌大祭当日(18日)には、各町会より山車が観音本堂前に参詣の上、各々の趣向でその絢爛・豪華さを競い合い芸能を演じ、随身門(現在の二天門)を出て自分の町へ帰りました。/その後、御神輿三基が「お堂下げ」にて本堂外陣から降ろされると、一之宮を先頭に浅草御門(現在の浅草橋際)の舟乗り場迄担ぎ運ばれました。そして待機している大森(品川)在住の漁師によって供奉される舟に各御神輿が乗せられ、浅草川(現隅田川)を漕ぎ上がって駒形岸或いは花川戸岸から上陸の後、浅草神社に担ぎ帰られたと云われています。/当時は浅草寺と一体となった行事で、『観音祭』又は『浅草祭』とも呼ばれてもいましたが、江戸末期にとある理由により廃絶し、昭和の時代に一度斎行されたものの、明治以降は御神輿が氏子各町を渡御するのみとなりました」
とある。
今朝のウェブニュースより、


 浅草:三社祭発祥700年、隅田川で54年ぶり舟渡御 ―― 三社祭700年を記念して54年ぶりに復活した「舟渡御」。中央奥は東京スカイツリー= 東京・浅草の三社祭の発祥から今年で700年という節目を記念し、18日、神輿(みこし)を船に乗せて隅田川を進む「舟渡御(ふなとぎょ)」が54年ぶりに行われた。あいにくの小雨交じりの天気だったが、多くの見物客が両岸から見守った。/舟渡御は江戸時代まで続いていた伝統行事だが、やがて途絶え、浅草寺本堂が再建された記念として1958年に行われたのが最後になっていた。/隅田川から観音像を引き揚げた漁師の兄弟ら3人を神様とまつったのが起源で、神輿を乗せた和船や屋形船の船団約20隻が、隅田川の桜橋から両国橋の約3キロの間を往復した。/5月の三社祭は勇壮さで知られ、初夏の風物詩だが、昨年は東日本大震災の影響で神輿の練り歩きが中止された。今年は浅草から約1キロの東京スカイツリーの開業も5月22日に控えており、下町の期待は高まっている。 毎日新聞 2012年3月18日 20時35分(最終更新 3月18日 21時26分)
浅草:三社祭発祥700年、隅田川で54年ぶり舟渡御 ―― 三社祭700年を記念して54年ぶりに復活した「舟渡御」。中央奥は東京スカイツリー= 東京・浅草の三社祭の発祥から今年で700年という節目を記念し、18日、神輿(みこし)を船に乗せて隅田川を進む「舟渡御(ふなとぎょ)」が54年ぶりに行われた。あいにくの小雨交じりの天気だったが、多くの見物客が両岸から見守った。/舟渡御は江戸時代まで続いていた伝統行事だが、やがて途絶え、浅草寺本堂が再建された記念として1958年に行われたのが最後になっていた。/隅田川から観音像を引き揚げた漁師の兄弟ら3人を神様とまつったのが起源で、神輿を乗せた和船や屋形船の船団約20隻が、隅田川の桜橋から両国橋の約3キロの間を往復した。/5月の三社祭は勇壮さで知られ、初夏の風物詩だが、昨年は東日本大震災の影響で神輿の練り歩きが中止された。今年は浅草から約1キロの東京スカイツリーの開業も5月22日に控えており、下町の期待は高まっている。 毎日新聞 2012年3月18日 20時35分(最終更新 3月18日 21時26分)
とある。
今朝のウェブニュースより、
今朝届いた ヤント氏の メールに曰く、
 「日高 節夫 様/貴ブログで「大木あまり」さんの紹介記事を拝見しました。/文中に「平出 隆」のことに触れて彼が 今朝届いた ヤント氏の メールに曰く、
「日高 節夫 様/貴ブログで「大木あまり」さんの紹介記事を拝見しました。/文中に「平出 隆」のことに触れて彼が 今朝届いた ヤント氏の メールに曰く、
「日高 節夫 様/貴ブログで「大木あまり」さんの紹介記事を拝見しました。/文中に「平出 隆」のことに触れて彼が『大木あまり』さんのファンであることや、今は亡き御姉上様が隆を応援してくれていたことなど何か縁を感じます。/角川の雑誌に大きく扱われているところを拝見したりホームページを検索してみて、俳人『大木あまり』さんのご活躍ぶりがうかがえます。/「あまり」さんの写真を見ていると、どこか貴君の御母上様に似ているように思いました。叔母と姪の関係ですから当然でしょうが……。小生が御母上様にお目にかかったのは貴宅に押しかけていた高校生のころで60年以上も昔のことですから記憶はおぼろげですが小生の網膜にはそのように焼きついています。/MY」
「日高 節夫 様/貴ブログで「大木あまり」さんの紹介記事を拝見しました。/文中に「平出 隆」のことに触れて彼が『大木あまり』さんのファンであることや、今は亡き御姉上様が隆を応援してくれていたことなど何か縁を感じます。/角川の雑誌に大きく扱われているところを拝見したりホームページを検索してみて、俳人『大木あまり』さんのご活躍ぶりがうかがえます。/「あまり」さんの写真を見ていると、どこか貴君の御母上様に似ているように思いました。叔母と姪の関係ですから当然でしょうが……。小生が御母上様にお目にかかったのは貴宅に押しかけていた高校生のころで60年以上も昔のことですから記憶はおぼろげですが小生の網膜にはそのように焼きついています。/MY」
先だって、いとこのYF女史から電話があり、妹の「大木あまり」が角川の月刊雑誌『俳句』3月号に大きく扱われているとのこと。あまりさんは本名を章栄(ふみえ)さんといい、私は伯父の法事などで数えるほどしか逢ったことがないが、伯母(あまりさんの母上)が俳句をやっていたこともあって、俳句を始めたらしい。俳号の「あまり」について「わたし、大木家の末っ子であまり者だったので、 あまり としたのよ」と聞いたことがある。猫が大好きで、家の近くには狸が出没しこれが可愛くて仕方ないと話してくれた。水門会のヤント氏の甥であり、福岡市でクリニックを開く私の甥とは小倉高校で同期生である平出隆氏(1950年~、詩人・エッセイスト)は、あまり女史のファンであると聞く。また、昨年暮れに他界した私の実姉は息子の高校同期である平出隆氏が小倉高校時代だった頃からのファンで平出氏の作品は、できるだけ求めたと聞く。何かしらの因縁を感じ、通販で『俳句』3月号を注文した。昨日その『俳句』3月号が届いた。カラー口絵3枚が巻頭をを飾り、5ページに亙って「大木あまり」女史が取り扱われていた。この4月に初孫の結婚式で上京する予定だった姉は、「今度の上京では あまりさん にも会えるといいわね」と言っていた。姉の遺影の前に早速この『俳句』3月号を供えた。



『俳句』3月号 46ページから
 火を使う
火を使う
青踏といふは闘う一歩かな
あかきもの花壇に咲いて卒業歌
蝶のごと生くるは難し火を使う
対当でゐよう春暮の鴉とは
春夕焼街の向こうに街があり
『俳句』3月号 47ページから
 視線の先
視線の先
掲出の写真は、昭和六十一年(一九八六)の四月、東京千駄ヶ谷区民会館にて牧羊社の十二人の『精鋭句集シリーズ』刊行祝賀会のときに撮影されたものである(十二人は長谷川櫂・田中裕明・夏石番矢・西村和子・島谷征良・大屋達治・能村研三・林桂・大庭紫達・保坂敏子・和田耕三郎・大木あまり)。現在俳壇で活躍されている錚々たる方々だ。また、この解に会に出席された方も片山由美子さんをはじめ、現俳壇を担う方たちであった。
この写真で、私があらぬ方を見ているのは、パーティ会場の出入り口が気になっていたからだ。なかなか田中裕明さんがいらっしゃらないので心配していたのだった。そして、やっと現れた裕明さんは大分遅れてきたにもかかわらず、汗を拭きつつ堂々と挨拶された。その時の印象を作家の倉橋由美子さんが、「あの方、大物ね」とおっしゃったことを、昨日の事のように覚えている。
遅れて来た裕明さんが十二人の中で一番早く逝かれたことが、今もって信じられない。しかし、この1枚の写真の中には、ゆたかな時間が流れたくさんの思い出がある。自分らしい俳句をもとめて、悩みながら歩いてきた歳月の中で、一番輝いている写真なのである。
※『精鋭句集シリーズ』全12巻(牧羊社 1985年)とは、
大木あまり『火のいろに』、大庭紫逢 『氷室』、大屋達治『絢鸞』、島谷征良『鵬程』、田中裕明『花間一壺』、夏石番矢『メトロポリティック』、西村和子『窓』、能村研三『海神(ネプチューン)』、長谷川櫂『古志』、林桂『銅の時代』、保坂敏子『芽山椒』、和田耕三郎『午餐』
 ※片山由美子:昭和27年千葉県生まれ。「狩」同人。平成2年第5回俳句研究賞受賞。/句集に『天弓』、『風待月』、『季語別 片山由美子句集』ほか。/評論集に『定本現代俳句女流百人』、『俳句を読むということ』(俳人協会評論賞受賞)など。ほかに対談集『俳句の生まれる場所』、エッセイ集『鳥のように風のように』などがある。
※片山由美子:昭和27年千葉県生まれ。「狩」同人。平成2年第5回俳句研究賞受賞。/句集に『天弓』、『風待月』、『季語別 片山由美子句集』ほか。/評論集に『定本現代俳句女流百人』、『俳句を読むということ』(俳人協会評論賞受賞)など。ほかに対談集『俳句の生まれる場所』、エッセイ集『鳥のように風のように』などがある。
 ※田中裕明(1959~2004年):大阪府大阪市生まれ。大阪府立北野高等学校在学中に波多野爽波に師事し、俳誌「青」に参加。1979年、「青」新人賞受賞、1981年、「青」賞受賞。1982年、京都大学工学部卒業、村田製作所に勤務。この年、角川俳句賞を最年少で受賞(作品「童子の夢」50句にて)。1991年、「青」碧鐘賞受賞、波多野爽波死去、「青」終刊。1992年、「水無瀬野」を創刊、2000年、主宰誌「ゆう」を創刊。2004年、骨髄性白血病による肺炎で永眠。
※田中裕明(1959~2004年):大阪府大阪市生まれ。大阪府立北野高等学校在学中に波多野爽波に師事し、俳誌「青」に参加。1979年、「青」新人賞受賞、1981年、「青」賞受賞。1982年、京都大学工学部卒業、村田製作所に勤務。この年、角川俳句賞を最年少で受賞(作品「童子の夢」50句にて)。1991年、「青」碧鐘賞受賞、波多野爽波死去、「青」終刊。1992年、「水無瀬野」を創刊、2000年、主宰誌「ゆう」を創刊。2004年、骨髄性白血病による肺炎で永眠。
 ※倉橋由美子(1935~2005年):(1935-2005)高知県生れ。明治大学仏文科に在学中の1960(昭和35)年、同校の学長賞に応募した小説「パルタイ」が入選。選者の平野謙に文芸時評で推奨され、また芥川賞候補ともなった同作で、1961年の女流文学者賞を受賞。1963年には、その作家活動により田村俊子賞を受けた。『スミヤキストQの冒険』『アマノン国往還記』『大人のための残酷童話』『交歓』などの作品がある。
※倉橋由美子(1935~2005年):(1935-2005)高知県生れ。明治大学仏文科に在学中の1960(昭和35)年、同校の学長賞に応募した小説「パルタイ」が入選。選者の平野謙に文芸時評で推奨され、また芥川賞候補ともなった同作で、1961年の女流文学者賞を受賞。1963年には、その作家活動により田村俊子賞を受けた。『スミヤキストQの冒険』『アマノン国往還記』『大人のための残酷童話』『交歓』などの作品がある。
『俳句』3月号 46ページから
青踏といふは闘う一歩かな
あかきもの花壇に咲いて卒業歌
蝶のごと生くるは難し火を使う
対当でゐよう春暮の鴉とは
春夕焼街の向こうに街があり
『俳句』3月号 47ページから
掲出の写真は、昭和六十一年(一九八六)の四月、東京千駄ヶ谷区民会館にて牧羊社の十二人の『精鋭句集シリーズ』刊行祝賀会のときに撮影されたものである(十二人は長谷川櫂・田中裕明・夏石番矢・西村和子・島谷征良・大屋達治・能村研三・林桂・大庭紫達・保坂敏子・和田耕三郎・大木あまり)。現在俳壇で活躍されている錚々たる方々だ。また、この解に会に出席された方も片山由美子さんをはじめ、現俳壇を担う方たちであった。
この写真で、私があらぬ方を見ているのは、パーティ会場の出入り口が気になっていたからだ。なかなか田中裕明さんがいらっしゃらないので心配していたのだった。そして、やっと現れた裕明さんは大分遅れてきたにもかかわらず、汗を拭きつつ堂々と挨拶された。その時の印象を作家の倉橋由美子さんが、「あの方、大物ね」とおっしゃったことを、昨日の事のように覚えている。
遅れて来た裕明さんが十二人の中で一番早く逝かれたことが、今もって信じられない。しかし、この1枚の写真の中には、ゆたかな時間が流れたくさんの思い出がある。自分らしい俳句をもとめて、悩みながら歩いてきた歳月の中で、一番輝いている写真なのである。
※『精鋭句集シリーズ』全12巻(牧羊社 1985年)とは、
大木あまり『火のいろに』、大庭紫逢 『氷室』、大屋達治『絢鸞』、島谷征良『鵬程』、田中裕明『花間一壺』、夏石番矢『メトロポリティック』、西村和子『窓』、能村研三『海神(ネプチューン)』、長谷川櫂『古志』、林桂『銅の時代』、保坂敏子『芽山椒』、和田耕三郎『午餐』
「第2次早大事件60周年記念の集い」への参加の案内状が来た。
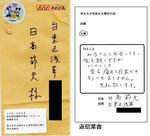


第2次早大事件とは、昭和27(1952)年5月8日午後4時頃、早大で第2次早大事件が発生した。神楽坂署私服・山本昭三巡査を文学部校舎に監禁。救援の警官隊と座り込み学生1500名が10時間にわたって対峙した。9日午前1時過ぎ、武力行使。未明、多くの活動家たちが再結集、都下大学の学生をまじえ数千人の抗議集会となった。日本共産党は、「座り込み」を「消極的で敗北主義的な戦術」と批判、メーデー参加者逮捕にきた刑事を監禁、奪還にきた警察と衝突、学生に多数の負傷者がでた事件を指すらしい。
私が早大に入学したのは昭和28(1953)年で、この事件に関しては耳にしただけでじかに接してはいないし、当時の学生運動は派閥の争いに終始していて、あまりいい印象は残っていない。それに此処のところ歩行困難に陥っているので、欠席の返事を出した。
因みに、昭和25(1950)年10月17日、早大で第1次早大事件といわれる闘争が起こっている。全学連はゼネストを決行せよとの指令を出し、全学連の呼びかけで早大構内で全都集会が開かれた。大学当局と警察は学生の「平和と大学擁護大会」を弾圧、学生143名が逮捕された。10月17日の闘争は大会戦術の手違いと、予想以上に凶暴化した警察の手によって、かってない官権との大衝突事件となったという。
第2次早大事件とは、昭和27(1952)年5月8日午後4時頃、早大で第2次早大事件が発生した。神楽坂署私服・山本昭三巡査を文学部校舎に監禁。救援の警官隊と座り込み学生1500名が10時間にわたって対峙した。9日午前1時過ぎ、武力行使。未明、多くの活動家たちが再結集、都下大学の学生をまじえ数千人の抗議集会となった。日本共産党は、「座り込み」を「消極的で敗北主義的な戦術」と批判、メーデー参加者逮捕にきた刑事を監禁、奪還にきた警察と衝突、学生に多数の負傷者がでた事件を指すらしい。
私が早大に入学したのは昭和28(1953)年で、この事件に関しては耳にしただけでじかに接してはいないし、当時の学生運動は派閥の争いに終始していて、あまりいい印象は残っていない。それに此処のところ歩行困難に陥っているので、欠席の返事を出した。
因みに、昭和25(1950)年10月17日、早大で第1次早大事件といわれる闘争が起こっている。全学連はゼネストを決行せよとの指令を出し、全学連の呼びかけで早大構内で全都集会が開かれた。大学当局と警察は学生の「平和と大学擁護大会」を弾圧、学生143名が逮捕された。10月17日の闘争は大会戦術の手違いと、予想以上に凶暴化した警察の手によって、かってない官権との大衝突事件となったという。
昨夜9時を少し過ぎた頃、テレビがピーと鳴ると同時に揺れを感じた。テレビ画面はすぐに地震報道にに変わりそれにに拠ると、千葉県沖合いを震源とするらしい。いやはやテレビ報道の即時報道にはその速さに全く驚いた。
 今朝のウェブニュースによると、
今朝のウェブニュースによると、
千葉県・茨城県で震度5強 ―― 14日午後9時5分ごろ、千葉県東方沖を震源とするマグニチュード6.1の地震があり、▽千葉県銚子市と茨城県神栖市で震度5強を観測したほか、▽震度5弱を千葉県旭市と茨城県日立市で観測しました。/また、水戸市や千葉市中央区、栃木県真岡市、埼玉県宮代町、それに福島県玉川村などで震度4を観測し、東京・中央区や品川区、神奈川県横浜市中区、新潟県南魚沼市、それに山梨県忍野村などで震度3を観測しました。/このほか、東北と関東甲信越、静岡県の各地で震度2や1の揺れを観測しました。/この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、被害の心配はありません。/気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県東方沖で、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されています。/また、気象庁は、観測データを分析した結果、震源の深さを10キロから15キロに修正しました。/この地震で、震度3を観測した千葉県木更津市の消防本部によりますと、長須賀地区に住む69歳の女性が自宅で寝ていて携帯電話の緊急地震速報のアラーム音を止めようと床に手をついたところ、右手首を骨折したということです。
女性は病院で手当を受けて帰宅したということです。/震度5強と5弱を観測した自治体では、ビルのガラスが割れるなどの被害が出ています。/震度5強を観測した銚子市によりますと、銚子市竹町で倉庫の2階部分のモルタルの壁がはがれ落ちたほか、中央町でビルの1階部分のガラスが割れるなどあわせて3棟の建物で一部損壊の被害がありました。/また、銚子市榊町と前宿町、それに柴崎町で住宅の石造りの塀やブロック塀が倒れる被害が3件あったということです。/これまでに市内ではけが人の情報は入っていないということです。
また、同じく震度5強を観測した茨城県の神栖市では、コンビニエンスストアの瓶が倒れて割れたり、ホテルのエレベーターが停止し一時、中に閉じ込められたりしましたがけが人の情報は入っていないということです。
気象庁“余震活動に注意を”/気象庁の永井章地震津波監視課長は、記者会見で「今回の地震は去年の巨大地震の余震と考えられる。地震活動は活発で、今後、1週間程度は震度4前後の余震が続くおそれがあり、注意してほしい」と話しました。/また永井課長は「夕方に三陸沖で起きた地震との関連は分からない。ただ、巨大地震の震源域とその周辺での地震活動は活発で、年単位で続く可能性がある。特に福島県の沖合や茨城北部から銚子にかけての地域では比較的大きな規模の地震が起きているので注意してほしい」と話しています。 (NHK NEWS Web 3月15日 1時32分)
相次ぐ地震に住民不安隠せず「いつまで続くのか」 ―― 14日午後6時過ぎから同9時過ぎにかけて、三陸沖と千葉県沖を震源地に相次いだ震度5強~4の地震。北海道と青森県では津波の到達が観測され、大きな揺れがあった沿岸部では高台への避難が行われるなど、不安が広がった。気象庁によると、千葉県沖の地震は東日本大震災の余震とみられ、今後1週間程度は最大震度4程度の余震に注意が必要という。
千葉で1人骨折、塀倒壊: 震度5強を観測した千葉県銚子市では突然、下から突き上げるような揺れがきて、その後、緩い横揺れが1分ほど続いたという。/この地震で千葉県は同日深夜、木更津市の女性(69)が右手首骨折の重傷を負ったと発表した。消防などによると、女性は携帯電話の緊急地震速報を伝える音を消そうとした際、床に右手をついて骨折した。そのほか同県内では、3カ所で民家のブロック塀が倒壊する被害が出た。/銚子市犬若の「民宿三浦」の経営者、三浦治男さん(52)は「海まで30メートルしかないので津波が心配だった」と緊張した様子。しかし、「まもなく心配ないということでほっとした。今日は宿泊客がいなくてよかった」と安堵(あんど)していた。/同市の居酒屋経営の女性(50)は「転落防止策を講じていたので、ボトルなどが棚から落ちることはなかった。ただ、津波がくるかもしれないと心配だった」と話した。「お客さんは慌てていた。携帯電話がつながらず、店の固定電話から家族の安否を確認していた」と語った。
成田国際空港会社広報室(同県成田市)によると、地震後に2本ある滑走路を一時閉鎖して点検したが異常はなかったという。
陸前高田「嫌な思い出が…」: 午後6時すぎ、約8カ月ぶりに発令された津波注意報に、岩手県の被災地に緊張が走った。/陸前高田市役所では、注意報の発令とともに災害対策本部を設置。防災無線での注意喚起や、各地域に避難者を受け入れる地区本部立ち上げの準備など、緊迫した雰囲気に包まれた。/市内で飲食店を営む吉田宏さん(47)は、厨房(ちゅうぼう)で、テレビから聞こえる注意報の発令のサイレンに思わず身構えた。高台の仮設店舗に同市で一番早く店を再開させた吉田さんだが、市中心部の店は昨年の津波で流された。店員を早く帰宅させるため、通常より2時間早い閉店を決め、出前も断った。/1年前、スーパーの屋上で救助を待ち、一晩を過ごした店員は平静を装いながらも震えが止まらない。「サイレンを聞いた瞬間、嫌な思い出がよみがえる。何事もないことを祈るだけ」と気遣った。/市内では、道路閉鎖や住民の避難誘導のため、消防団員らが消防車や地区本部で待機。テレビのニュースに聞き入った。浸水地域に居住していた多くの住民は高台の仮設住宅に避難しているものの、同市街地は地盤沈下に加えて防波堤や防潮堤の本格復旧が進んでおらず、ほとんど水面と変わらない高さの土地もある。消防団員の千田孝司さん(46)は「どんな小さい津波でも、何が起こるかわからない」と不安を口にした。/同市の米崎小仮設住宅から近くの地区本部に避難した田中舘艶子さん(77)は「1年たっても落ち着かない。いつまで続くかと思うと大変」と苦笑い。/市職員の高橋一成さん(44)も「防潮堤などができるまで数年の間は、気が緩められない状況が続く。住民の方には警戒心を忘れないようにしてほしい」と話していた。 (産経ニュース 2012.3.15 07:06)
千葉県・茨城県で震度5強 ―― 14日午後9時5分ごろ、千葉県東方沖を震源とするマグニチュード6.1の地震があり、▽千葉県銚子市と茨城県神栖市で震度5強を観測したほか、▽震度5弱を千葉県旭市と茨城県日立市で観測しました。/また、水戸市や千葉市中央区、栃木県真岡市、埼玉県宮代町、それに福島県玉川村などで震度4を観測し、東京・中央区や品川区、神奈川県横浜市中区、新潟県南魚沼市、それに山梨県忍野村などで震度3を観測しました。/このほか、東北と関東甲信越、静岡県の各地で震度2や1の揺れを観測しました。/この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、被害の心配はありません。/気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県東方沖で、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されています。/また、気象庁は、観測データを分析した結果、震源の深さを10キロから15キロに修正しました。/この地震で、震度3を観測した千葉県木更津市の消防本部によりますと、長須賀地区に住む69歳の女性が自宅で寝ていて携帯電話の緊急地震速報のアラーム音を止めようと床に手をついたところ、右手首を骨折したということです。
女性は病院で手当を受けて帰宅したということです。/震度5強と5弱を観測した自治体では、ビルのガラスが割れるなどの被害が出ています。/震度5強を観測した銚子市によりますと、銚子市竹町で倉庫の2階部分のモルタルの壁がはがれ落ちたほか、中央町でビルの1階部分のガラスが割れるなどあわせて3棟の建物で一部損壊の被害がありました。/また、銚子市榊町と前宿町、それに柴崎町で住宅の石造りの塀やブロック塀が倒れる被害が3件あったということです。/これまでに市内ではけが人の情報は入っていないということです。
また、同じく震度5強を観測した茨城県の神栖市では、コンビニエンスストアの瓶が倒れて割れたり、ホテルのエレベーターが停止し一時、中に閉じ込められたりしましたがけが人の情報は入っていないということです。
気象庁“余震活動に注意を”/気象庁の永井章地震津波監視課長は、記者会見で「今回の地震は去年の巨大地震の余震と考えられる。地震活動は活発で、今後、1週間程度は震度4前後の余震が続くおそれがあり、注意してほしい」と話しました。/また永井課長は「夕方に三陸沖で起きた地震との関連は分からない。ただ、巨大地震の震源域とその周辺での地震活動は活発で、年単位で続く可能性がある。特に福島県の沖合や茨城北部から銚子にかけての地域では比較的大きな規模の地震が起きているので注意してほしい」と話しています。 (NHK NEWS Web 3月15日 1時32分)
相次ぐ地震に住民不安隠せず「いつまで続くのか」 ―― 14日午後6時過ぎから同9時過ぎにかけて、三陸沖と千葉県沖を震源地に相次いだ震度5強~4の地震。北海道と青森県では津波の到達が観測され、大きな揺れがあった沿岸部では高台への避難が行われるなど、不安が広がった。気象庁によると、千葉県沖の地震は東日本大震災の余震とみられ、今後1週間程度は最大震度4程度の余震に注意が必要という。
千葉で1人骨折、塀倒壊: 震度5強を観測した千葉県銚子市では突然、下から突き上げるような揺れがきて、その後、緩い横揺れが1分ほど続いたという。/この地震で千葉県は同日深夜、木更津市の女性(69)が右手首骨折の重傷を負ったと発表した。消防などによると、女性は携帯電話の緊急地震速報を伝える音を消そうとした際、床に右手をついて骨折した。そのほか同県内では、3カ所で民家のブロック塀が倒壊する被害が出た。/銚子市犬若の「民宿三浦」の経営者、三浦治男さん(52)は「海まで30メートルしかないので津波が心配だった」と緊張した様子。しかし、「まもなく心配ないということでほっとした。今日は宿泊客がいなくてよかった」と安堵(あんど)していた。/同市の居酒屋経営の女性(50)は「転落防止策を講じていたので、ボトルなどが棚から落ちることはなかった。ただ、津波がくるかもしれないと心配だった」と話した。「お客さんは慌てていた。携帯電話がつながらず、店の固定電話から家族の安否を確認していた」と語った。
成田国際空港会社広報室(同県成田市)によると、地震後に2本ある滑走路を一時閉鎖して点検したが異常はなかったという。
陸前高田「嫌な思い出が…」: 午後6時すぎ、約8カ月ぶりに発令された津波注意報に、岩手県の被災地に緊張が走った。/陸前高田市役所では、注意報の発令とともに災害対策本部を設置。防災無線での注意喚起や、各地域に避難者を受け入れる地区本部立ち上げの準備など、緊迫した雰囲気に包まれた。/市内で飲食店を営む吉田宏さん(47)は、厨房(ちゅうぼう)で、テレビから聞こえる注意報の発令のサイレンに思わず身構えた。高台の仮設店舗に同市で一番早く店を再開させた吉田さんだが、市中心部の店は昨年の津波で流された。店員を早く帰宅させるため、通常より2時間早い閉店を決め、出前も断った。/1年前、スーパーの屋上で救助を待ち、一晩を過ごした店員は平静を装いながらも震えが止まらない。「サイレンを聞いた瞬間、嫌な思い出がよみがえる。何事もないことを祈るだけ」と気遣った。/市内では、道路閉鎖や住民の避難誘導のため、消防団員らが消防車や地区本部で待機。テレビのニュースに聞き入った。浸水地域に居住していた多くの住民は高台の仮設住宅に避難しているものの、同市街地は地盤沈下に加えて防波堤や防潮堤の本格復旧が進んでおらず、ほとんど水面と変わらない高さの土地もある。消防団員の千田孝司さん(46)は「どんな小さい津波でも、何が起こるかわからない」と不安を口にした。/同市の米崎小仮設住宅から近くの地区本部に避難した田中舘艶子さん(77)は「1年たっても落ち着かない。いつまで続くかと思うと大変」と苦笑い。/市職員の高橋一成さん(44)も「防潮堤などができるまで数年の間は、気が緩められない状況が続く。住民の方には警戒心を忘れないようにしてほしい」と話していた。 (産経ニュース 2012.3.15 07:06)
「日高先生へ /前略/昔々ある小学校に夏波ちゃんという女の子がいました。/夏波ちゃんは同級生達から「や~いお前の叔父さん失踪してやんの~!」/「お前オレよりビンボーで偏差値も低いくせに利口ぶるな!」などと言われ心が何度も折れそうになりましたが、そんな私の事をやさしく見守ってくれた男の子がN君、Y君たちです。/悩んでいる私を励ましてくれたのかなっちゃんです(現在心理学の先生をしておられます)。/日高先生やお友達、白馬に乗った王子様に守られているので、今とても幸せに暮らしています。/そしてこれからどんな事がおきようとも、何度倒れようとも自分が持っている技術をどこまでも磨いて行こうと心に固く誓いました。/今もなおみんなの力を集め日本経済の復活をねらっています。/「All Japan」どころではなく「All Earth」で立ち向かってゆかなければ地球の滅亡が近く感じられるからです…… ゴミとの戦いは続く……/ 以上 かなみ作のな~んちゃって昔話でした。
近いうちに先生の所へ遊びに行きたいと言うか、お会いしたいです。/道子先生にも宜しくお伝え下さい。/唐突な手紙ですみませんでした
 (汗)/漢字も忘れてしまったし、敬語の使い方もハチャメチャになってしまいました…… /乱筆乱文お許し下さい。/かしこ 2012年3月12日(月) KYより
(汗)/漢字も忘れてしまったし、敬語の使い方もハチャメチャになってしまいました…… /乱筆乱文お許し下さい。/かしこ 2012年3月12日(月) KYより
今日は東京大空襲から67年目。
 言問橋西詰の隅田公園入口にある『東京大空襲戦災犠牲者追悼碑』の説明案内板には
言問橋西詰の隅田公園入口にある『東京大空襲戦災犠牲者追悼碑』の説明案内板には
「隅田公園のこの一帯は、 昭和20年3月10日の東京大空襲により亡くなられた数多くの方々を仮埋葬した場所である。 第二次世界大戦(太平洋戦争)中の空襲により被災した台東区民(当時下谷区民、浅草区民)は多数に及んだ。亡くなられた多くの方々の遺体は、区内の公園等に仮埋葬され、戦後荼毘に付され東京慰霊堂(隅田区)に納骨された。 戦後四十年、この不幸な出来事や忌まわしい記憶も、年毎に薄れ、平和な繁栄のもとに忘れ去られようとしている。いま、本区は、数少ない資料をたどり、区民からの貴重な情報に基づく戦災死者名簿を調整するとともに、この地に碑を建立した。」とある。さらに碑の横に置いてある『言問橋の縁石』の説明版には「ここに置かれているコンクリート塊は1992年言問橋の欄干を改修した際に、 その基部の縁石を切り取ったものです。1945年3月10日、東京大空襲のとき、言問橋は猛火に見舞われ、 大勢の人が犠牲になりました。この縁石は当時の痛ましい出来事の記念石として、ここに保存するものです。」と書かれている。
ウェブニュースより
 母と子の戦場:3・10東京大空襲/上 息子抱き、火の粉走る川へ ―― ◇燃える街、逃げ惑った末に いかだに泳ぎ着き、助けられた 「戦争加担した」しょく罪に体験語る
母と子の戦場:3・10東京大空襲/上 息子抱き、火の粉走る川へ ―― ◇燃える街、逃げ惑った末に いかだに泳ぎ着き、助けられた 「戦争加担した」しょく罪に体験語る
「炎が吹き付けられる中、1歳3カ月の息子を背負って逃げました。突然、背中の子がギャーッと異常な声を上げたんです。見ると口の中で火の粉が燃えていた」
被害が大きかった東京都江東区に建てられた東京大空襲・戦災資料センター。橋本代志子さん(90)は、小学生の子どもたちの食い入るようなまなざしを受け、時折声を詰まらせながらあの夜のことを語った。
× × ×
一家は、両国近くに8人で暮らしていた。メリヤス工場を営む両親のもと、4人姉妹の長女として育った橋本さんは、跡取りとして夫を迎え長男に恵まれた。初孫で、娘ばかりの家に生まれた久しぶりの男の子。祖父母の愛情を一身に集め「博、博」とかわいがられた。「暗い時代、博は両親の唯一の生きがいだった」。橋本さんは振り返る。
何もかもが不足していた。日々の食べ物に事欠き、橋本さんは母乳が出なかった。母乳が出ない証明書を医師からもらい、町会長の印を受け、区役所に届けて初めて粉ミルクが買えた。量が足りず穀類の粉を混ぜて飲ませた。おしめにする布もなく、親戚中から古い浴衣を集めて縫った。
午後になると町内を歩き回り、空を見上げるのが日課だった。風呂を沸かすまきが不足し、営業している銭湯は数少ない。煙突から煙が出ている銭湯を見つけては、息子をおぶって行った。「丸々とした赤ちゃんなんかいなかった」と橋本さん。銭湯の洗い場でもせっけんやタオルから目が離せない。うっかりすると盗まれてしまうからだ。赤ちゃんとのんびり湯船につかることなどできなかった。小さくなったせっけんをそっと泡立て、大切に使った。
1945年3月9日夜、軍務に就いていた夫は近隣の国民学校に駐屯していて不在だった。1歳だった博さんは、久しぶりに入浴してぐっすり眠っていた。
深夜、警報が鳴った。両親と3人の妹、博さんを背負った橋本さんは防空壕に避難した。B29の爆音がおなかに響いた。子を抱いて身を縮めた橋本さんに、外を見に行った父が叫んだ。
「いつもの空襲と違う」
壕の外は真昼のような明るさで、強風にあおられて火の粉が吹雪のように吹き付けた。ガスバーナーの炎を四方から浴びるようだった。逃げ惑う群衆で道はあふれ、妹(17)を見失った。妹は5升炊きの大きな釜を抱えており、手をつなげていなかった。「お姉ちゃん、待っててー」。2度ほど聞こえた叫び声が、最後となった。
炎にあおられ逃げ場を失った人々で、竪川に架かる三之橋は身動きできなかった。かまどの中にいるような熱さ。橋の中央では人が生きながら焼かれていた。母は橋の際に橋本さんと博さんらを引き寄せ、ねんねこをかぶせその上に身を伏せた。さらに父が覆いかぶさり、火に耐えようとした。
橋本さんの髪がちりちりと音を立て、きな臭いにおいがした。頭巾のない人たちの多くは、髪に火がつき、転げ回っていた。
「代志子、川へ飛び込め」。父が叫んだ。「飛び込め、飛び込め」。ためらう橋本さんに、父は激しい声で繰り返した。母は頭巾を脱ぎ、橋本さんにかぶせた。白髪交じりの髪が熱風で逆立っていた。無言で見つめる悲しげな母の顔を、70年近くたった今も忘れられない。
息子をぎゅっと抱きしめ、川へ飛び込んだ。猛烈な熱さの中から冷たい水に入り、肌が刺されるように痛んだ。水面を火の粉が走り、頭や顔に絶えず水をかけないといられなかった。古式泳法を習っていた橋本さんは、流れてきたいかだ目がけて泳ぎ、赤ん坊を乗せた。「この子の命だけは救いたい」。その一心だった。
いかだで流されていると、男性2人が乗った小舟が近づき、助けてくれた。川の中からずっとうめき声が聞こえ、人が水中に沈むのも見た。両親と17歳の妹の消息はついにわからない。遺骨代わりに、三之橋のたもとの砂を持ち帰った。
橋本さんらは、疎開のため用意していた千葉県の家に身を寄せた。よちよち歩いていた博さんは一時歩けなくなり、黒い便を毎日した。もうだめかもしれないと覚悟したが、無事に育ってくれた。戦後、2児に恵まれた橋本さんはいま、博さん一家と暮らし、6人の孫、2人のひ孫にも恵まれた。
× × ×
茶色く変色しボロボロになった「妊産婦手帳」を、橋本さんは大切に保管している。腹立たしいのは、出産予定日が「生産予定日」と記されていることだ。「女性は子どもを生産する機械だったのか」。当時は気づかなかった一文に、女性と子どもが置かれていた立場を思う。
東京大空襲・戦災資料センターで体験を語ることは、作家の早乙女勝元さんに誘われ10年前から始めた。空襲体験を話す前日は、今でも眠れない。もう話したくないとも思う。
でも「大人だった自分も戦争に加担した」しょく罪の気持ちが、橋本さんを突き動かしている。勝つために、国の命令に従い我慢したことが、大切な家族を死なせることにつながったのではないか。首に茶色く残るやけどの痕のように、後悔は消えない。
資料センターで話し終えると、子どもたちに折り紙で作った「羽ばたく鶴」を手渡している。「多くの命が失われた中で生き残り、生きることの素晴らしさをしみじみ感じる。子どもたちには命の大切さを伝えたい」
× × ×
一夜にして10万人の命が失われた67年前の東京大空襲。今年もまた3月10日が巡ってくる。子を背負い猛火をくぐった2人の母の証言を聞いた。【木村葉子】 毎日新聞 2012年3月8日 東京朝刊
母と子の戦場:3・10東京大空襲/下 背中の娘に生かされた ―― ◇川に落ち、ずぶぬれで一夜/翌朝、動かぬ口に母乳含ませる/戦後は児童施設で数百人の「母」に
 くすんだ色の展示物が多い中、ひときわ鮮やかな一角が目を引く。赤い着物と、赤い毛糸のチョッキ。東京大空襲・戦災資料センター(東京都江東区)には、鎌田十六(とむ)さん(99)の娘の早苗さんが、3月10日の東京大空襲の夜に着ていた着物が飾られている。襟元のぼんぼんは、早苗さんがよくしゃぶっていたという。
くすんだ色の展示物が多い中、ひときわ鮮やかな一角が目を引く。赤い着物と、赤い毛糸のチョッキ。東京大空襲・戦災資料センター(東京都江東区)には、鎌田十六(とむ)さん(99)の娘の早苗さんが、3月10日の東京大空襲の夜に着ていた着物が飾られている。襟元のぼんぼんは、早苗さんがよくしゃぶっていたという。
母におぶわれた早苗さんは猛火をくぐり、冷たい川に落ちた。過酷な逃避は生後6カ月の小さな命を奪った。鎌田さんはこの晩、恋愛結婚をした八つ年下の夫と母も亡くした。幸せな結婚生活は、3年しか続かなかった。
× × ×
「まだ生まれていないのか」
逆子のため陣痛は2日間に及び、いきむ力もなくなった鎌田さんを見た産院の院長は、驚いた。1944年の夏。当時まだ一般的ではなかった帝王切開の手術を受けた。駆けつけた夫は、「手術も病室も一番いいものにしてください」と頼み込んだ。
真夏の暑さもあって傷口は化膿(かのう)し、子どもと一緒に1カ月も入院した。1等個室は居心地がよく、看護婦の対応も丁寧だった。娘が次第に愛らしさを増すのがうれしかった。「お人形さんみたい」。すやすや眠る初孫の顔をのぞき込んで、母は繰り返した。子煩悩の夫は、家にいる時は片時も早苗さんを離さなかった。せきも鼻水も出ていないのに「風邪かもしれない」と、病院に連れていった。
× × ×
灯火管制で町は暗闇に包まれていた。1945年に入ってから、東京は夜も昼も空襲があった。鎌田さんはおぶった娘に月を見せ、「今夜も無事でありますように」と手を合わせた。
3月9日深夜、空襲が始まった。火の手は人の体も吹き飛ばすような強い風にあおられて広がり、住んでいた浅草・蔵前も火の海になった。鎌田さんは早苗さんを背負い、70歳を超えた母とおしめを入れたかばんは、夫が守ってくれた。
人波に流されて、隅田川のほとりに来た。火の粉と煙が吹きつけ目が開けられない。数歩進んでつまずき、川の中に頭から落ちた。水音に気づいた夫も、川に飛び込んだ。
冷たい水が肌を刺す。ずっと寝ていた早苗さんは、細い泣き声を上げた。鎌田さんは眠気に襲われた。「このまま寝ていれば、冷たさを忘れられるだろう」
はっと我に返った。「早苗はどうなる」。川の中に横倒しになった大八車があった。「子どもを何とかして」。声を振り絞ると、誰かが荷台に上げてくれた。
気を失っている間に夜は明けた。ずぶぬれで凍えた体は動かない。多くの遺体がくすぶる焼け野原を歩き出した。避難所の学校にたどりつき、保健婦に子どもの様子を尋ねた。
「亡くなっています。赤ちゃんの分まで元気になって」。静かな声だった。
人があふれる教室で娘を下ろした。鼻や額に点々とやけどがあるが、寝ているようだった。一晩飲ませず球のように張った乳房から、冷たい口元に母乳を絞り入れた。
夫の遺体は1週間後に川から見つかり、母の死は焼けた衣類の一部で確認した。「私が助かったのは、早苗をおぶっていて背中がぬれなかったから」。鎌田さんはそう思っている。
× × ×
翌年の3月。上野の地下道は人いきれでむっとした暑さだった。焼け出された人が足の踏み場もないほど寝ていた。ぼろぼろの服をまとったさみしげな子どもたちが、家族を亡くした自分の姿と重なった。
この光景が忘れられず、子どもの世話をする仕事につこうと思った。東京都内の児童養護施設で、保母として働くことになった。70歳まで勤め上げ、育てた子どもは数百人に上る。
戦後すぐに働いた養育院では、90畳の大部屋に子どもたちが布団を4列に敷いて寝ていた。ある晩鎌田さんは、訪ねてきた知人にベッドを譲り、子どもの布団に滑り込んだことがある。「隣で寝たでしょ。うれしかったよ」と言われた。その子の笑顔はずっと胸に残っている。
「施設の子」と言われぬよう、しつけには気を配った。ほうきの持ち方やほこりの集め方、人の目を見てあいさつすること……。厳しく言い含めた。4~5歳の子どもが幼い子の入浴を手伝うのを見ると、「甘えたい盛りなのに」とふびんに思う気持ちがこみ上げた。
住み込みで働く鎌田さんの居室には、「お母さん」「お母さん」と子どもの出入りがしょっちゅうあった。24時間休みはなく、だれかが風邪をひけば一気に広まり、休日も返上だ。鎌田さんは当時を振り返る。「いくらしんどくても、子どもといればつらいことは吹き飛んでしまった」
 子を持つ人からの再婚話を何回か持ちかけられた。でも「自分の子が育てられなかったのに、人様の大事な子どもは育てられない」と断り続けた。早苗さんを背負った重みや抱いた時の感覚は、忘れられない。
子を持つ人からの再婚話を何回か持ちかけられた。でも「自分の子が育てられなかったのに、人様の大事な子どもは育てられない」と断り続けた。早苗さんを背負った重みや抱いた時の感覚は、忘れられない。
鎌田さんはいま都内で妹と暮らしている。写真館で撮った早苗さんの写真は空襲で焼けてしまった。娘が生きていた唯一の証しである着物を、’07年に戦災資料センターに寄贈したとき、鎌田さんは願った。
「もう二度と、早苗のような子が出る世の中になりませんように」【木村葉子】 毎日新聞 2012年3月9日 東京朝刊
「隅田公園のこの一帯は、 昭和20年3月10日の東京大空襲により亡くなられた数多くの方々を仮埋葬した場所である。 第二次世界大戦(太平洋戦争)中の空襲により被災した台東区民(当時下谷区民、浅草区民)は多数に及んだ。亡くなられた多くの方々の遺体は、区内の公園等に仮埋葬され、戦後荼毘に付され東京慰霊堂(隅田区)に納骨された。 戦後四十年、この不幸な出来事や忌まわしい記憶も、年毎に薄れ、平和な繁栄のもとに忘れ去られようとしている。いま、本区は、数少ない資料をたどり、区民からの貴重な情報に基づく戦災死者名簿を調整するとともに、この地に碑を建立した。」とある。さらに碑の横に置いてある『言問橋の縁石』の説明版には「ここに置かれているコンクリート塊は1992年言問橋の欄干を改修した際に、 その基部の縁石を切り取ったものです。1945年3月10日、東京大空襲のとき、言問橋は猛火に見舞われ、 大勢の人が犠牲になりました。この縁石は当時の痛ましい出来事の記念石として、ここに保存するものです。」と書かれている。
ウェブニュースより
「炎が吹き付けられる中、1歳3カ月の息子を背負って逃げました。突然、背中の子がギャーッと異常な声を上げたんです。見ると口の中で火の粉が燃えていた」
被害が大きかった東京都江東区に建てられた東京大空襲・戦災資料センター。橋本代志子さん(90)は、小学生の子どもたちの食い入るようなまなざしを受け、時折声を詰まらせながらあの夜のことを語った。
× × ×
一家は、両国近くに8人で暮らしていた。メリヤス工場を営む両親のもと、4人姉妹の長女として育った橋本さんは、跡取りとして夫を迎え長男に恵まれた。初孫で、娘ばかりの家に生まれた久しぶりの男の子。祖父母の愛情を一身に集め「博、博」とかわいがられた。「暗い時代、博は両親の唯一の生きがいだった」。橋本さんは振り返る。
何もかもが不足していた。日々の食べ物に事欠き、橋本さんは母乳が出なかった。母乳が出ない証明書を医師からもらい、町会長の印を受け、区役所に届けて初めて粉ミルクが買えた。量が足りず穀類の粉を混ぜて飲ませた。おしめにする布もなく、親戚中から古い浴衣を集めて縫った。
午後になると町内を歩き回り、空を見上げるのが日課だった。風呂を沸かすまきが不足し、営業している銭湯は数少ない。煙突から煙が出ている銭湯を見つけては、息子をおぶって行った。「丸々とした赤ちゃんなんかいなかった」と橋本さん。銭湯の洗い場でもせっけんやタオルから目が離せない。うっかりすると盗まれてしまうからだ。赤ちゃんとのんびり湯船につかることなどできなかった。小さくなったせっけんをそっと泡立て、大切に使った。
1945年3月9日夜、軍務に就いていた夫は近隣の国民学校に駐屯していて不在だった。1歳だった博さんは、久しぶりに入浴してぐっすり眠っていた。
深夜、警報が鳴った。両親と3人の妹、博さんを背負った橋本さんは防空壕に避難した。B29の爆音がおなかに響いた。子を抱いて身を縮めた橋本さんに、外を見に行った父が叫んだ。
「いつもの空襲と違う」
壕の外は真昼のような明るさで、強風にあおられて火の粉が吹雪のように吹き付けた。ガスバーナーの炎を四方から浴びるようだった。逃げ惑う群衆で道はあふれ、妹(17)を見失った。妹は5升炊きの大きな釜を抱えており、手をつなげていなかった。「お姉ちゃん、待っててー」。2度ほど聞こえた叫び声が、最後となった。
炎にあおられ逃げ場を失った人々で、竪川に架かる三之橋は身動きできなかった。かまどの中にいるような熱さ。橋の中央では人が生きながら焼かれていた。母は橋の際に橋本さんと博さんらを引き寄せ、ねんねこをかぶせその上に身を伏せた。さらに父が覆いかぶさり、火に耐えようとした。
橋本さんの髪がちりちりと音を立て、きな臭いにおいがした。頭巾のない人たちの多くは、髪に火がつき、転げ回っていた。
「代志子、川へ飛び込め」。父が叫んだ。「飛び込め、飛び込め」。ためらう橋本さんに、父は激しい声で繰り返した。母は頭巾を脱ぎ、橋本さんにかぶせた。白髪交じりの髪が熱風で逆立っていた。無言で見つめる悲しげな母の顔を、70年近くたった今も忘れられない。
息子をぎゅっと抱きしめ、川へ飛び込んだ。猛烈な熱さの中から冷たい水に入り、肌が刺されるように痛んだ。水面を火の粉が走り、頭や顔に絶えず水をかけないといられなかった。古式泳法を習っていた橋本さんは、流れてきたいかだ目がけて泳ぎ、赤ん坊を乗せた。「この子の命だけは救いたい」。その一心だった。
いかだで流されていると、男性2人が乗った小舟が近づき、助けてくれた。川の中からずっとうめき声が聞こえ、人が水中に沈むのも見た。両親と17歳の妹の消息はついにわからない。遺骨代わりに、三之橋のたもとの砂を持ち帰った。
橋本さんらは、疎開のため用意していた千葉県の家に身を寄せた。よちよち歩いていた博さんは一時歩けなくなり、黒い便を毎日した。もうだめかもしれないと覚悟したが、無事に育ってくれた。戦後、2児に恵まれた橋本さんはいま、博さん一家と暮らし、6人の孫、2人のひ孫にも恵まれた。
× × ×
茶色く変色しボロボロになった「妊産婦手帳」を、橋本さんは大切に保管している。腹立たしいのは、出産予定日が「生産予定日」と記されていることだ。「女性は子どもを生産する機械だったのか」。当時は気づかなかった一文に、女性と子どもが置かれていた立場を思う。
東京大空襲・戦災資料センターで体験を語ることは、作家の早乙女勝元さんに誘われ10年前から始めた。空襲体験を話す前日は、今でも眠れない。もう話したくないとも思う。
でも「大人だった自分も戦争に加担した」しょく罪の気持ちが、橋本さんを突き動かしている。勝つために、国の命令に従い我慢したことが、大切な家族を死なせることにつながったのではないか。首に茶色く残るやけどの痕のように、後悔は消えない。
資料センターで話し終えると、子どもたちに折り紙で作った「羽ばたく鶴」を手渡している。「多くの命が失われた中で生き残り、生きることの素晴らしさをしみじみ感じる。子どもたちには命の大切さを伝えたい」
× × ×
一夜にして10万人の命が失われた67年前の東京大空襲。今年もまた3月10日が巡ってくる。子を背負い猛火をくぐった2人の母の証言を聞いた。【木村葉子】 毎日新聞 2012年3月8日 東京朝刊
母と子の戦場:3・10東京大空襲/下 背中の娘に生かされた ―― ◇川に落ち、ずぶぬれで一夜/翌朝、動かぬ口に母乳含ませる/戦後は児童施設で数百人の「母」に
母におぶわれた早苗さんは猛火をくぐり、冷たい川に落ちた。過酷な逃避は生後6カ月の小さな命を奪った。鎌田さんはこの晩、恋愛結婚をした八つ年下の夫と母も亡くした。幸せな結婚生活は、3年しか続かなかった。
× × ×
「まだ生まれていないのか」
逆子のため陣痛は2日間に及び、いきむ力もなくなった鎌田さんを見た産院の院長は、驚いた。1944年の夏。当時まだ一般的ではなかった帝王切開の手術を受けた。駆けつけた夫は、「手術も病室も一番いいものにしてください」と頼み込んだ。
真夏の暑さもあって傷口は化膿(かのう)し、子どもと一緒に1カ月も入院した。1等個室は居心地がよく、看護婦の対応も丁寧だった。娘が次第に愛らしさを増すのがうれしかった。「お人形さんみたい」。すやすや眠る初孫の顔をのぞき込んで、母は繰り返した。子煩悩の夫は、家にいる時は片時も早苗さんを離さなかった。せきも鼻水も出ていないのに「風邪かもしれない」と、病院に連れていった。
× × ×
灯火管制で町は暗闇に包まれていた。1945年に入ってから、東京は夜も昼も空襲があった。鎌田さんはおぶった娘に月を見せ、「今夜も無事でありますように」と手を合わせた。
3月9日深夜、空襲が始まった。火の手は人の体も吹き飛ばすような強い風にあおられて広がり、住んでいた浅草・蔵前も火の海になった。鎌田さんは早苗さんを背負い、70歳を超えた母とおしめを入れたかばんは、夫が守ってくれた。
人波に流されて、隅田川のほとりに来た。火の粉と煙が吹きつけ目が開けられない。数歩進んでつまずき、川の中に頭から落ちた。水音に気づいた夫も、川に飛び込んだ。
冷たい水が肌を刺す。ずっと寝ていた早苗さんは、細い泣き声を上げた。鎌田さんは眠気に襲われた。「このまま寝ていれば、冷たさを忘れられるだろう」
はっと我に返った。「早苗はどうなる」。川の中に横倒しになった大八車があった。「子どもを何とかして」。声を振り絞ると、誰かが荷台に上げてくれた。
気を失っている間に夜は明けた。ずぶぬれで凍えた体は動かない。多くの遺体がくすぶる焼け野原を歩き出した。避難所の学校にたどりつき、保健婦に子どもの様子を尋ねた。
「亡くなっています。赤ちゃんの分まで元気になって」。静かな声だった。
人があふれる教室で娘を下ろした。鼻や額に点々とやけどがあるが、寝ているようだった。一晩飲ませず球のように張った乳房から、冷たい口元に母乳を絞り入れた。
夫の遺体は1週間後に川から見つかり、母の死は焼けた衣類の一部で確認した。「私が助かったのは、早苗をおぶっていて背中がぬれなかったから」。鎌田さんはそう思っている。
× × ×
翌年の3月。上野の地下道は人いきれでむっとした暑さだった。焼け出された人が足の踏み場もないほど寝ていた。ぼろぼろの服をまとったさみしげな子どもたちが、家族を亡くした自分の姿と重なった。
この光景が忘れられず、子どもの世話をする仕事につこうと思った。東京都内の児童養護施設で、保母として働くことになった。70歳まで勤め上げ、育てた子どもは数百人に上る。
戦後すぐに働いた養育院では、90畳の大部屋に子どもたちが布団を4列に敷いて寝ていた。ある晩鎌田さんは、訪ねてきた知人にベッドを譲り、子どもの布団に滑り込んだことがある。「隣で寝たでしょ。うれしかったよ」と言われた。その子の笑顔はずっと胸に残っている。
「施設の子」と言われぬよう、しつけには気を配った。ほうきの持ち方やほこりの集め方、人の目を見てあいさつすること……。厳しく言い含めた。4~5歳の子どもが幼い子の入浴を手伝うのを見ると、「甘えたい盛りなのに」とふびんに思う気持ちがこみ上げた。
住み込みで働く鎌田さんの居室には、「お母さん」「お母さん」と子どもの出入りがしょっちゅうあった。24時間休みはなく、だれかが風邪をひけば一気に広まり、休日も返上だ。鎌田さんは当時を振り返る。「いくらしんどくても、子どもといればつらいことは吹き飛んでしまった」
鎌田さんはいま都内で妹と暮らしている。写真館で撮った早苗さんの写真は空襲で焼けてしまった。娘が生きていた唯一の証しである着物を、’07年に戦災資料センターに寄贈したとき、鎌田さんは願った。
「もう二度と、早苗のような子が出る世の中になりませんように」【木村葉子】 毎日新聞 2012年3月9日 東京朝刊
プロフィール
ハンドルネーム:
目高 拙痴无
年齢:
93
誕生日:
1932/02/04
自己紹介:
くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。
sechin@nethome.ne.jp です。
sechin@nethome.ne.jp です。
カレンダー
| 04 | 2025/05 | 06 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新コメント
[enken 02/23]
[中村東樹 02/04]
[m、m 02/04]
[爺の姪 01/13]
[レンマ学(メタ数学) 01/02]
[m.m 10/12]
[爺の姪 10/01]
[あは♡ 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター