瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り
荀子 大略篇 第二十七 より
78 子貢問於孔子曰:「賜倦於學矣、願息事君。」孔子曰:「《詩》云:『溫恭朝夕、執事有恪。』事君難、事君焉可息哉!」「然則、賜願息事親。」孔子曰:「《詩》云:『孝子不匱、永錫爾類。』事親難、事親焉可息哉!」「然則賜願息於妻子。」孔子曰:「《詩》云:『刑于寡妻、至于兄弟、以御於家邦。』妻子難、妻子焉可息哉!」「然則賜願息於朋友。」孔子曰:「《詩》云:『朋友攸攝、攝以威儀。』朋友難、朋友焉可息哉!」「然則賜願息耕。」孔子曰:「《詩》云:『晝爾于茅、宵爾索綯、亟其乘屋、其始播百穀。』耕難、耕焉可息哉!」「然則賜無息者乎?」孔子曰:「望其壙、皋如也、顛如也、鬲如也、此則知所息矣。」子貢曰:「大哉!死乎!君子息焉、小人休焉。」
子貢が孔子に、
「私は学問をすることに飽きました。君に仕えることによって休息したいと思いますが、どうでしょうか」
とたずねた。孔子は、
「『詩経〔商頌・那篇〕』に『朝から晩までおだやかでうやうやしく慎んで国事を処理する』とある。君に仕えることは難しい仕事である。どうして君に仕えて休息などとれようか」
と答えた。
「それならば親に仕えることによって休息したいと思いますがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・既酔篇〕』に『孝子は手をつくしてゆきわたらない所がないようにするものである。だからいつまでもお前に幸福が与えられるのだ』とある。親に仕えることはむつかしい仕事である。どうして親に仕えて休息などとれようか」
と答えた。
「それでは妻子と一緒にいることで休息をとりたいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・思斉篇〕』に『自分が模範となって妻を従わせ、それを兄弟にまでおし及ぼし、それによって家と国を治めてゆく』とある。妻子と一緒にいるのはむつかしい仕事である。妻子と一緒にいてどうして休息がとれようか」
と答えた。
「それでは友達の側で休息したいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・既酔編〕』に『友達は互いに助け合うものであり、立派な態度で助け合うものである』とある。友達と交わるのはむつかしいことである。どうして友達の側で休息などできようか」
と答えた。
「それでは田畑を耕作したいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔豳風(ひんふう)・七月篇〕』に『昼はお前は野で茅(ちがや)を刈れ、夜はお前は縄をなえ、早く屋根をふけ、多くの穀物の種をまけ』とある。農耕は忙しく辛い仕事である。どうして農耕によって休息ができようか」
と答えた。
 「そうすると私には休息するところがないのでしょうか」
「そうすると私には休息するところがないのでしょうか」
と言うと、孔子は、
「遥かに墓の盛土を見ると、高々としているし、こんもりしているし、釜をふせたようだ。ここが休息する所であることが分るだろう」
と答えた。子貢は、
「死というものは偉大なものだ、君子も小人もそこで休息するのか」
と言った。
HOLY SONNETS 10.(死よ 驕るなかれ)
Death, be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadful, for thou art not so ;
For those, whom thou think'st thou dost overthrow,
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.
From rest and sleep, which but thy pictures be,
Much pleasure, then from thee much more must flow,
And soonest our best men with thee do go,
Rest of their bones, and soul's delivery.
Thou'rt slave to Fate, chance, kings, and desperate men,
And dost with poison, war, and sickness dwell,
And poppy, or charms can make us sleep as well,
And better than thy stroke ; why swell'st thou then ?
One short sleep past, we wake eternally,
And Death shall be no more ; Death, thou shalt die.
 死よ驕るなかれ 汝を力強く恐ろしいと
死よ驕るなかれ 汝を力強く恐ろしいと
いう者もいるが 決してそうではない
汝が倒したと考える者は 死にはしない
おろかな死よ 汝は私を殺せないのだ
汝の似姿たる休息と安眠からは
より大きな喜びが生まれ出てくる
最も優れたものが死を急ぐのは
骨に安らぎを与え 魂を開放させるため
汝は運命や偶然、王侯や絶望した人の奴隷
汝は牢獄、戦争、疫病の隣人
芥子粒や呪文も同じように人を眠らせる
汝の一撃よりもよく だから威張ることはない
束の間の眠りの後我々は永遠に甦る
そこにはもはや死はない 死よ 汝こそが死ぬのだ
78 子貢問於孔子曰:「賜倦於學矣、願息事君。」孔子曰:「《詩》云:『溫恭朝夕、執事有恪。』事君難、事君焉可息哉!」「然則、賜願息事親。」孔子曰:「《詩》云:『孝子不匱、永錫爾類。』事親難、事親焉可息哉!」「然則賜願息於妻子。」孔子曰:「《詩》云:『刑于寡妻、至于兄弟、以御於家邦。』妻子難、妻子焉可息哉!」「然則賜願息於朋友。」孔子曰:「《詩》云:『朋友攸攝、攝以威儀。』朋友難、朋友焉可息哉!」「然則賜願息耕。」孔子曰:「《詩》云:『晝爾于茅、宵爾索綯、亟其乘屋、其始播百穀。』耕難、耕焉可息哉!」「然則賜無息者乎?」孔子曰:「望其壙、皋如也、顛如也、鬲如也、此則知所息矣。」子貢曰:「大哉!死乎!君子息焉、小人休焉。」
子貢が孔子に、
「私は学問をすることに飽きました。君に仕えることによって休息したいと思いますが、どうでしょうか」
とたずねた。孔子は、
「『詩経〔商頌・那篇〕』に『朝から晩までおだやかでうやうやしく慎んで国事を処理する』とある。君に仕えることは難しい仕事である。どうして君に仕えて休息などとれようか」
と答えた。
「それならば親に仕えることによって休息したいと思いますがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・既酔篇〕』に『孝子は手をつくしてゆきわたらない所がないようにするものである。だからいつまでもお前に幸福が与えられるのだ』とある。親に仕えることはむつかしい仕事である。どうして親に仕えて休息などとれようか」
と答えた。
「それでは妻子と一緒にいることで休息をとりたいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・思斉篇〕』に『自分が模範となって妻を従わせ、それを兄弟にまでおし及ぼし、それによって家と国を治めてゆく』とある。妻子と一緒にいるのはむつかしい仕事である。妻子と一緒にいてどうして休息がとれようか」
と答えた。
「それでは友達の側で休息したいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔大雅・既酔編〕』に『友達は互いに助け合うものであり、立派な態度で助け合うものである』とある。友達と交わるのはむつかしいことである。どうして友達の側で休息などできようか」
と答えた。
「それでは田畑を耕作したいのですがどうでしょうか」
と言うと、孔子は、
「『詩経〔豳風(ひんふう)・七月篇〕』に『昼はお前は野で茅(ちがや)を刈れ、夜はお前は縄をなえ、早く屋根をふけ、多くの穀物の種をまけ』とある。農耕は忙しく辛い仕事である。どうして農耕によって休息ができようか」
と答えた。
と言うと、孔子は、
「遥かに墓の盛土を見ると、高々としているし、こんもりしているし、釜をふせたようだ。ここが休息する所であることが分るだろう」
と答えた。子貢は、
「死というものは偉大なものだ、君子も小人もそこで休息するのか」
と言った。
HOLY SONNETS 10.(死よ 驕るなかれ)
Death, be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadful, for thou art not so ;
For those, whom thou think'st thou dost overthrow,
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.
From rest and sleep, which but thy pictures be,
Much pleasure, then from thee much more must flow,
And soonest our best men with thee do go,
Rest of their bones, and soul's delivery.
Thou'rt slave to Fate, chance, kings, and desperate men,
And dost with poison, war, and sickness dwell,
And poppy, or charms can make us sleep as well,
And better than thy stroke ; why swell'st thou then ?
One short sleep past, we wake eternally,
And Death shall be no more ; Death, thou shalt die.
いう者もいるが 決してそうではない
汝が倒したと考える者は 死にはしない
おろかな死よ 汝は私を殺せないのだ
汝の似姿たる休息と安眠からは
より大きな喜びが生まれ出てくる
最も優れたものが死を急ぐのは
骨に安らぎを与え 魂を開放させるため
汝は運命や偶然、王侯や絶望した人の奴隷
汝は牢獄、戦争、疫病の隣人
芥子粒や呪文も同じように人を眠らせる
汝の一撃よりもよく だから威張ることはない
束の間の眠りの後我々は永遠に甦る
そこにはもはや死はない 死よ 汝こそが死ぬのだ
PR
今朝のウェブニュースより、
 オリンパス上場廃止は回避 大王製紙も中間決算―― 巨額の損失隠しが発覚したオリンパスは、14日の提出期限までに決算報告書などを提出し、上場廃止をひとまず回避しました。/オリンパスが発表した今年度の中間連結決算は、黒字見込みから一転して323億円の赤字となりました。債務超過は回避したものの、自己資本比率は大幅に減らしました。東京証券取引所は今後、オリンパスの上場の是非を判断することになります。/また、巨額の借り入れをめぐり、前会長が逮捕された大王製紙も中間決算を発表しました。
オリンパス上場廃止は回避 大王製紙も中間決算―― 巨額の損失隠しが発覚したオリンパスは、14日の提出期限までに決算報告書などを提出し、上場廃止をひとまず回避しました。/オリンパスが発表した今年度の中間連結決算は、黒字見込みから一転して323億円の赤字となりました。債務超過は回避したものの、自己資本比率は大幅に減らしました。東京証券取引所は今後、オリンパスの上場の是非を判断することになります。/また、巨額の借り入れをめぐり、前会長が逮捕された大王製紙も中間決算を発表しました。
大王製紙・佐光正義社長:「決算発表が本日まで遅延して、株主をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心より深くおわび申し上げます」/中間決算は、井川前会長から資金を回収できない場合も想定し、貸倒引当金を計上したため、黒字の予想から赤字となりました。(TV asahi 5CH 12/15 00:05)
荀子 大略篇 第二十七 より
54 「義」與「利」者、人之所兩有也。雖堯舜不能去民之欲利;然而能使其欲利不克其好義也。雖桀紂不能去民之好義;然而能使其好義不勝其欲利也。故義勝利者為治世、利克義者為亂世。上重義則義克利、上重利則利克義。故天子不言多少、諸侯不言利害、大夫不言得喪、士不通貨財。有國之君不息牛羊、錯質之臣不息雞豚、冢卿不脩幣、大夫不為場園、從士以上皆羞利而不與民爭業、樂分施而恥積藏;然故民不困財、貧窶者有所竄其手。
 道義心と利己心とは、人であれば誰でも二つとも合わせもっているものである。尭や舜のような聖王でも民が利益を得たいという欲望をなくすることは出来ない。しかし利益を得たいという欲望を、道義にしたがわなければならないということ以上に強くならないようにさせたのである。これと反対に桀や紂のような悪王でも、民が道義に従わなければならないと思う心をなくすることはできない。しかし道義に従わなければならないという心を、利益を得たいという欲望以上に強くならないようにさせたのである。だから民の道義心が利己心より強いときは治まった世であり、利己心が道義心より強いときは乱れた世である。そうして君主が道義を重んずるときは、民の道義心は利己心より強くなり、君主が利益を重んずるときには、民の利己心が道義心より強くなる。だから天子は多いとか少ないとか言わない。諸侯は利益とか損害のことを言わず、大夫は得を下とか損をしたとか言わず、士は貨財を通じて商人のように利殖をしないのである。また国君は牛や羊を畜産しない。贈り物を捧げて臣下となった者は鶏や豚を飼育せず、上卿は破れた蘺(まがき)を自分で修理せず、大夫は自分で畑仕事をせず、士より以上の身分の者は、みな利益を得ることを恥じて、民と同じ仕事をしないで、施し与えることを楽しみ、貯蓄することを恥とするのである。だから民も経済的に困窮することがなく、たとい貧窮な者でもそれなりに手をつけて仕事をすることのできる余地があるのである。
道義心と利己心とは、人であれば誰でも二つとも合わせもっているものである。尭や舜のような聖王でも民が利益を得たいという欲望をなくすることは出来ない。しかし利益を得たいという欲望を、道義にしたがわなければならないということ以上に強くならないようにさせたのである。これと反対に桀や紂のような悪王でも、民が道義に従わなければならないと思う心をなくすることはできない。しかし道義に従わなければならないという心を、利益を得たいという欲望以上に強くならないようにさせたのである。だから民の道義心が利己心より強いときは治まった世であり、利己心が道義心より強いときは乱れた世である。そうして君主が道義を重んずるときは、民の道義心は利己心より強くなり、君主が利益を重んずるときには、民の利己心が道義心より強くなる。だから天子は多いとか少ないとか言わない。諸侯は利益とか損害のことを言わず、大夫は得を下とか損をしたとか言わず、士は貨財を通じて商人のように利殖をしないのである。また国君は牛や羊を畜産しない。贈り物を捧げて臣下となった者は鶏や豚を飼育せず、上卿は破れた蘺(まがき)を自分で修理せず、大夫は自分で畑仕事をせず、士より以上の身分の者は、みな利益を得ることを恥じて、民と同じ仕事をしないで、施し与えることを楽しみ、貯蓄することを恥とするのである。だから民も経済的に困窮することがなく、たとい貧窮な者でもそれなりに手をつけて仕事をすることのできる余地があるのである。
大王製紙・佐光正義社長:「決算発表が本日まで遅延して、株主をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心より深くおわび申し上げます」/中間決算は、井川前会長から資金を回収できない場合も想定し、貸倒引当金を計上したため、黒字の予想から赤字となりました。(TV asahi 5CH 12/15 00:05)
荀子 大略篇 第二十七 より
54 「義」與「利」者、人之所兩有也。雖堯舜不能去民之欲利;然而能使其欲利不克其好義也。雖桀紂不能去民之好義;然而能使其好義不勝其欲利也。故義勝利者為治世、利克義者為亂世。上重義則義克利、上重利則利克義。故天子不言多少、諸侯不言利害、大夫不言得喪、士不通貨財。有國之君不息牛羊、錯質之臣不息雞豚、冢卿不脩幣、大夫不為場園、從士以上皆羞利而不與民爭業、樂分施而恥積藏;然故民不困財、貧窶者有所竄其手。
ここのところ、徘徊に出かけても1000mも歩かない内に腰が痛みだし、そのうち右脚の脹脛(ふくらはぎ)から膝関節にかけても痛み出し、30分間も歩けず帰宅する体たらく。婆様は医者に行けと言うが、それも面倒。痛いと言うと医者に行けと五月蝿いので、だんまりを決め込む始末である。
今朝、メールを開くとshinさんから、第96回院展の誘いのメールが入っていた。曰く、「日高さま/こんにちは。ご無沙汰しております。脹脛のご調子はいかがでしょうか。/こちらは、来年度の授業計画を立てることとか、なんとか元気です。/ところで、12月15日~28日横浜駅東口・そごう横浜店6階に、再興第96回院展が開催されます。招待券は2枚持っております。もしご興味がありましたら、いっしょに見に行きませんか。/見学が終わった後、忘年会を兼ねていっしょに食事でも。/21日以降なら、こちらは時間を作れます。/ではお返事いただければと思います。/シン@横浜」
 興味がないわけではないし、shinさんにも会いたいのだが、腰や脹脛、膝関節の様子もはかばかしくないので、断わりのメールを入れることにして、メールで出展作品の一部を見てみた。
興味がないわけではないし、shinさんにも会いたいのだが、腰や脹脛、膝関節の様子もはかばかしくないので、断わりのメールを入れることにして、メールで出展作品の一部を見てみた。
今朝、メールを開くとshinさんから、第96回院展の誘いのメールが入っていた。曰く、「日高さま/こんにちは。ご無沙汰しております。脹脛のご調子はいかがでしょうか。/こちらは、来年度の授業計画を立てることとか、なんとか元気です。/ところで、12月15日~28日横浜駅東口・そごう横浜店6階に、再興第96回院展が開催されます。招待券は2枚持っております。もしご興味がありましたら、いっしょに見に行きませんか。/見学が終わった後、忘年会を兼ねていっしょに食事でも。/21日以降なら、こちらは時間を作れます。/ではお返事いただければと思います。/シン@横浜」
今朝のウェブニュースより
中国の国宝「清明上河図」、来年東京に 初の国外展示 ―― 中国・北宋時代(960~1127年)の絵巻で、神品とたたえられる「清明上河図(せいめいじょうかず)」(張択端・画)が、日中国交正常化40周年の記念行事として東京国立博物館で来年開催される特別展「北京故宮博物院200選」(朝日新聞社など主催)に出品されることが決まった。北京の故宮博物院から東京国立博物館に12日、中国の国家文物局が出品を許可したと連絡が入った。中国から国外に出品されるのは初めて。
 「清明上河図」は縦24.8cm、長さ528cmの絹本製の図巻で、清明節(新暦では4月5日ごろ、中国では墓参りなどをする)の頃の北宋の都・開封(かいほう)(現在の河南省開封市)と郊外の風景を描いたとされる。
「清明上河図」は縦24.8cm、長さ528cmの絹本製の図巻で、清明節(新暦では4月5日ごろ、中国では墓参りなどをする)の頃の北宋の都・開封(かいほう)(現在の河南省開封市)と郊外の風景を描いたとされる。
郊外の川べりの風景や、荷を満載した船、街道、大小の店、行き交う馬やかごなどが、墨と淡彩で描かれる。登場人物は約800人。中国の風俗画の最高峰と言われ、国家一級文物(国宝)にも指定されている。 (asahi.com 2011年12月12日21時18分)
北宋は、汴梁〔べんりょう、河南省開封〕を帝都として、汴京または東京(とうけい)と呼び、洛陽を西京(せいけい)と呼んだ。その東京がもっとも繁栄した北宋第八代徽宗(きそう)皇帝の崇寧~宣和年間(1102~1125年)頃の姿を南宋の初期の紹興十七(1147)年に、孟元老なる人物が追懐して書いた『東京夢華録』には「清明節」について、次のように書いている。
清明節。都では普通冬至から百五日目を「大寒食」とした。
寒食の前日は「炊熟(すいじゅく)」と呼ばれる。粉で棗こ〔食偏に固〕飛燕を作り、柳の枝に串刺しにして門に刺し、これを「子推燕」と言った。十五歳になった少女たちは、多くこの日に笄を頭につけて成人式を行った。
 寒食の第三日が清明節である。新仏の墓には、みなこの日に墓参りに行き、都の者は郊外に繰り出した。公室は半月前に宮人に車馬を御陵にさしむけられ、、皇室の近親も諸陵に分遣されて祭祀が行われた。従者はみな紫の衫(ひとえ)に白絹の三角子(ひざあて)、青の行纏(きゃはん)を付けるが、これはすべて官給品である。また寒食節の日になると皇室は奉先寺道者院に車馬を出され、宮人たちの墓参りも行われた。車はみな金色に装い紺色の幔幕を張り、錦の額と珠簾をつけ、二組の綉扇(しゅうせん)と、薄絹の提灯を持ったものが前導した。
寒食の第三日が清明節である。新仏の墓には、みなこの日に墓参りに行き、都の者は郊外に繰り出した。公室は半月前に宮人に車馬を御陵にさしむけられ、、皇室の近親も諸陵に分遣されて祭祀が行われた。従者はみな紫の衫(ひとえ)に白絹の三角子(ひざあて)、青の行纏(きゃはん)を付けるが、これはすべて官給品である。また寒食節の日になると皇室は奉先寺道者院に車馬を出され、宮人たちの墓参りも行われた。車はみな金色に装い紺色の幔幕を張り、錦の額と珠簾をつけ、二組の綉扇(しゅうせん)と、薄絹の提灯を持ったものが前導した。
士庶(ひとびと)は郊外に向かう都の各門にぎっしりひしめき合い、紙馬〔しま、祭祀に用いる紙に描かれた神像で、祭が終わると焼く〕を売る店は、通りに紙馬を楼閣のように積み上げていた。郊外は何処も市のような賑わいで、それぞれ花木の下、あるいは庭園の中、皿・杯を並べ、互いに酒を酌み交わし、都の歌童や舞子たちも庭園・四阿(あずまや)に満ちて歌い躍り、日が暮れてやっと帰るのであった。めいめい団子・炊餅(むしもち)・黄胖〔にんぎょう、黄土をこねて作った泥人形〕・掉刀(なぎなた)、花や果物と、山亭(あずまや)での遊び道具、アヒルの卵と鶏の雛を携えてゆく。これを「門外土儀」という。轎子(こし)には楊柳やさまざまな花を屋根いっぱい飾り付け四方に垂らして日をさえぎった。これより三日間はみな都を出て墓参りをしたが、やはり〔冬至から〕百五日が一番さかんだった。
この節句のあいだ、城内の市では稠餳(みずあめ)・麦餻(むぎがし)・乳酪・乳餅(こうじどうふ)のたぐいを売った。
ゆったりと都の門をくぐれば、斜陽は御柳にさし、酔うて帰るわが庭には、明月が梨の花に光を投げるのだった。
なおこの日、禁衛兵の諸部隊が、隊列を整え馬に乗って軍楽を奏しながら都の四方に出た。これを「摔脚(しゅつきゃく)」という。その旗指物は美々しく、軍容は勇壮、人馬ともえりすぐりの精鋭で、また格別なみものの一つになっていた。 松村茂夫 訳 中国古典文学大系より
中国の国宝「清明上河図」、来年東京に 初の国外展示 ―― 中国・北宋時代(960~1127年)の絵巻で、神品とたたえられる「清明上河図(せいめいじょうかず)」(張択端・画)が、日中国交正常化40周年の記念行事として東京国立博物館で来年開催される特別展「北京故宮博物院200選」(朝日新聞社など主催)に出品されることが決まった。北京の故宮博物院から東京国立博物館に12日、中国の国家文物局が出品を許可したと連絡が入った。中国から国外に出品されるのは初めて。
郊外の川べりの風景や、荷を満載した船、街道、大小の店、行き交う馬やかごなどが、墨と淡彩で描かれる。登場人物は約800人。中国の風俗画の最高峰と言われ、国家一級文物(国宝)にも指定されている。 (asahi.com 2011年12月12日21時18分)
北宋は、汴梁〔べんりょう、河南省開封〕を帝都として、汴京または東京(とうけい)と呼び、洛陽を西京(せいけい)と呼んだ。その東京がもっとも繁栄した北宋第八代徽宗(きそう)皇帝の崇寧~宣和年間(1102~1125年)頃の姿を南宋の初期の紹興十七(1147)年に、孟元老なる人物が追懐して書いた『東京夢華録』には「清明節」について、次のように書いている。
清明節。都では普通冬至から百五日目を「大寒食」とした。
寒食の前日は「炊熟(すいじゅく)」と呼ばれる。粉で棗こ〔食偏に固〕飛燕を作り、柳の枝に串刺しにして門に刺し、これを「子推燕」と言った。十五歳になった少女たちは、多くこの日に笄を頭につけて成人式を行った。
士庶(ひとびと)は郊外に向かう都の各門にぎっしりひしめき合い、紙馬〔しま、祭祀に用いる紙に描かれた神像で、祭が終わると焼く〕を売る店は、通りに紙馬を楼閣のように積み上げていた。郊外は何処も市のような賑わいで、それぞれ花木の下、あるいは庭園の中、皿・杯を並べ、互いに酒を酌み交わし、都の歌童や舞子たちも庭園・四阿(あずまや)に満ちて歌い躍り、日が暮れてやっと帰るのであった。めいめい団子・炊餅(むしもち)・黄胖〔にんぎょう、黄土をこねて作った泥人形〕・掉刀(なぎなた)、花や果物と、山亭(あずまや)での遊び道具、アヒルの卵と鶏の雛を携えてゆく。これを「門外土儀」という。轎子(こし)には楊柳やさまざまな花を屋根いっぱい飾り付け四方に垂らして日をさえぎった。これより三日間はみな都を出て墓参りをしたが、やはり〔冬至から〕百五日が一番さかんだった。
この節句のあいだ、城内の市では稠餳(みずあめ)・麦餻(むぎがし)・乳酪・乳餅(こうじどうふ)のたぐいを売った。
ゆったりと都の門をくぐれば、斜陽は御柳にさし、酔うて帰るわが庭には、明月が梨の花に光を投げるのだった。
なおこの日、禁衛兵の諸部隊が、隊列を整え馬に乗って軍楽を奏しながら都の四方に出た。これを「摔脚(しゅつきゃく)」という。その旗指物は美々しく、軍容は勇壮、人馬ともえりすぐりの精鋭で、また格別なみものの一つになっていた。 松村茂夫 訳 中国古典文学大系より
荀子 大略篇第二十七 より
42 《易》曰:「復自道、何其咎?」春秋賢穆公、以為能變也。
 〔訳〕『易』〔小畜の卦九初の爻辞(こうじ)〕に「たといあやまちがあっても、元に反(かえ)り正道に従えば、どうしてとがめにあろうか」といっている。『春秋公羊伝』(文公十二年)で、「秦の穆公を賢人だと言っているのは、彼が自分のあやまちを悔いてよく改めることができたからである」と言っている。
〔訳〕『易』〔小畜の卦九初の爻辞(こうじ)〕に「たといあやまちがあっても、元に反(かえ)り正道に従えば、どうしてとがめにあろうか」といっている。『春秋公羊伝』(文公十二年)で、「秦の穆公を賢人だと言っているのは、彼が自分のあやまちを悔いてよく改めることができたからである」と言っている。
周易(第9卦)より
小畜、亨。密雲不雨、自我西郊。
彖曰、小畜柔得位、而上下應之、曰小畜。健而巽、剛中而志行、乃亨。密雲不雨、尚往也。自我西郊、施未行也。
象曰、風行天上、小畜;君子以懿文德。
〔読み〕
小畜は、享る。密雲あれどあめふらず、わが西郊よりす。
彖に曰く、小畜は柔、位を得て上下これに応ずるを、小畜と曰う。健にして巽(したが)い、剛中にして志行なわる。すなわち享るなり。密雲あれど雨ふらずとは、往くを尚(たっと)ぶなり。わが西郊よりすとは、施しいまだ行われざるなり。
象に曰く、風天上を行くは小畜なり。君子もって文徳を懿(よ)くす。
 〔解読〕
〔解読〕
小畜の小は陰、畜は畜(とど)むの意。一陰が五陽を引き畜(とど)める卦象に取る。また一陰が五陽を引き畜めるのであるから、その拘束力は弱く、したがって小(すこし)く畜める=小畜という意味にもなる。陽剛・君子の道はたとえ小しく畜められても、やがては享る。密雲は陰気の凝集、いまだ陽気と相和して雨ふらすに至らず、陰の方向たる西郊より湧きつつある。やがては雨ふって享る機会も来るであろう。
 ※なお易の卦辞は周の文王の作と言われる。してみれば密雲雨ふらずと云々とは、文王が羑里(ゆうり)に捕えられて易を書いたとき、わが志は天下経綸にあれど、今は君主たる殷の紂王と志相和せず、雨沢人民に及ばず、小しく畜められたる時なるかなという嘆息の意を寓したものとも見られる。
※なお易の卦辞は周の文王の作と言われる。してみれば密雲雨ふらずと云々とは、文王が羑里(ゆうり)に捕えられて易を書いたとき、わが志は天下経綸にあれど、今は君主たる殷の紂王と志相和せず、雨沢人民に及ばず、小しく畜められたる時なるかなという嘆息の意を寓したものとも見られる。
《彖伝》小畜は柔爻〔六四〕が正位を得て上下の陽爻がこれに応ずる象だから、小畜というのである。その徳が健(すこ)やか〔乾〕で巽(したが)い〔巽〕、二・五の剛爻が中位を占めて志が行われる。だから享るのである。密雲あれど雨ふらずというのは、陰気がさらに上進し陽気とわして雨となることを尚(たっと)ぶのである。わが西郊よりすというのは、雨沢の施しがまだ行われぬことをいうのである。
《象伝》風〔巽〕が天〔乾〕の上行くのが小畜である。風の恩沢がまだ人には及ばぬこの卦象にのっとって、君子はおのれの文章道徳を蓄積涵養し、やがてその施しのあまねからんことを期すべきである。
初九:復自道、何其咎、吉。
象曰、復自道、其義吉也。
九二:牽復、吉。
象曰、牽復在中、亦不自失也。
九三:輿說輻、夫妻反目。
象曰、夫妻反目、不能正室也。
六四:有孚、血去惕出、无咎。
象曰、有孚惕出、上合志也。
九五:有孚攣如、富以其鄰。
象曰、有孚攣如、不獨富也。
上九:既雨既處、尚德載、婦貞厲。月幾望、君子征凶。
象曰、既雨既處、德積載也。君子征凶、有所疑也
〔読み〕
初九。復(かえ)ること道による。何ぞそれ咎あらん。吉なり。
象に曰く、復ること道によるとは、その義吉なるなり。
九二。牽(ひ)きて復(かえ)る。吉なり。
象に曰く、牽きて復りて中に在り、またみずから失わざるなり。
九三。輿(くるま)幅(とこしばり)を説く。夫妻反目す。
象に曰く、夫妻反目すとは、室を正すこと能わざるなり。
六四。孚(まこと)あり。血(いたみ)去り惕(おそ)れ出づ。咎なし。
象に曰く、孚あり、惕れ出づとは、上、志を合わせばなり。
九五。孚ありて、攣如(れんにょ)たり。富その隣と以(とも)にす。
象に曰く、孚ありて、攣如たりとは、独り富めりとせざるなり。
上九。既に雨ふり既に処(お)る。徳を尚(たっと)びて載(み)つ。婦は貞なれども厲(あやう)し。月望に幾(ちか)し。君子も征けば凶なり。
象に曰く、既に雨ふり既に処るとは、徳積みて載てるなり。君子も征けば凶なりとは、疑わしきところあればなり。
〔解読〕
初九は剛陽居下、上卦に進もうとする志が強いが、正応たる六四の陰爻にひきとどめられ、引き返して正道を守るを得た。どうして咎のあるはずがあろう。吉である。
《象伝》復ること道によるというのは、その行いの正しさが吉なのである。
九二は剛陽居中、初九と牽きあって進みまた牽きあって引き返す。吉である。
《象伝》牽きあって引き返し中位に安んずるのであるから、みずからの守るべき道を失わないのである。
九三は過剛不中、上に進もうとしても六四に引きとどめられ進むことを得ない。たとえて言えば、車の幅〔よこしばり、輹に通ずる、車軸の上にあり車軸と車体を結ぶ革〕がほどけて車体と車輪が離ればなれになり、動かすことが出来ないようになったようなもの。しかも陽剛の身で陰柔に引きとどめられるのであるから心中おだやかならず、たとえて言えば夫妻の仲がしっかりゆかず反目しあうようなものである。
《象伝》夫妻反目すというのは、家庭を正しくおさめることができぬことである。
六四は卦中ただ一つの陰爻ながら正位に居り、しかも上の九五の助けがあるから、誠信をつくしてその人を頼れば、やがては受けた傷の痛みも去り、憂懼不安もなくなり、咎なきを得る。
《象伝》孚あり惕れ出づというのは、上の人が心をあわせてくれるからである。
九五は陽剛中正、誠信をつくし攣如(れんにょ)すなわちひとと手を執りあって事にあたる。富も独占しようとはせずその隣人(六四)と分け合うほどの心意気である。「富みてその隣を以(ひき)ゆ」とも読む。
《象伝》孚ありて攣如たりというのは、自分だけ富もうなどとは考えぬことである。
上九は卦極、小畜すなわち小〔陰〕が衆陽をひきとどめることも極点に達し、陰陽和合して今までの密雲雨ふらざる状態が終り、すでに雨ふり陰陽ともに安らかに処(お)ることを得る象。これは陽が陰を尊び、陰の徳が積もり積もって満ちたからに外ならぬ。しかし陰の徳が積もり満ちて陽をしのぐほどになるのは順当なことではない。たとえば妻たる者はいかに徳あればとて夫を制するような振舞いをしてはならぬであろう。だから妻としてこのような立場に在るものは、いかに貞正であっても危ういと言わねばならぬ。またたとえれば月が満月に近づき、その光が太陽とまぎらわしい状態とも言える。このような時期においては、君子も強引に進もうとすることは凶である。
《象伝》すでに雨ふりすでに処るというのは、陰の徳が積み重ねられて満ちたからである。君子も征(ゆ)けば凶というのは、陰〔小人〕の力が強くて陽〔君子〕とまぎらわしい状態だからである。
42 《易》曰:「復自道、何其咎?」春秋賢穆公、以為能變也。
周易(第9卦)より
小畜、亨。密雲不雨、自我西郊。
彖曰、小畜柔得位、而上下應之、曰小畜。健而巽、剛中而志行、乃亨。密雲不雨、尚往也。自我西郊、施未行也。
象曰、風行天上、小畜;君子以懿文德。
〔読み〕
小畜は、享る。密雲あれどあめふらず、わが西郊よりす。
彖に曰く、小畜は柔、位を得て上下これに応ずるを、小畜と曰う。健にして巽(したが)い、剛中にして志行なわる。すなわち享るなり。密雲あれど雨ふらずとは、往くを尚(たっと)ぶなり。わが西郊よりすとは、施しいまだ行われざるなり。
象に曰く、風天上を行くは小畜なり。君子もって文徳を懿(よ)くす。
小畜の小は陰、畜は畜(とど)むの意。一陰が五陽を引き畜(とど)める卦象に取る。また一陰が五陽を引き畜めるのであるから、その拘束力は弱く、したがって小(すこし)く畜める=小畜という意味にもなる。陽剛・君子の道はたとえ小しく畜められても、やがては享る。密雲は陰気の凝集、いまだ陽気と相和して雨ふらすに至らず、陰の方向たる西郊より湧きつつある。やがては雨ふって享る機会も来るであろう。
《彖伝》小畜は柔爻〔六四〕が正位を得て上下の陽爻がこれに応ずる象だから、小畜というのである。その徳が健(すこ)やか〔乾〕で巽(したが)い〔巽〕、二・五の剛爻が中位を占めて志が行われる。だから享るのである。密雲あれど雨ふらずというのは、陰気がさらに上進し陽気とわして雨となることを尚(たっと)ぶのである。わが西郊よりすというのは、雨沢の施しがまだ行われぬことをいうのである。
《象伝》風〔巽〕が天〔乾〕の上行くのが小畜である。風の恩沢がまだ人には及ばぬこの卦象にのっとって、君子はおのれの文章道徳を蓄積涵養し、やがてその施しのあまねからんことを期すべきである。
初九:復自道、何其咎、吉。
象曰、復自道、其義吉也。
九二:牽復、吉。
象曰、牽復在中、亦不自失也。
九三:輿說輻、夫妻反目。
象曰、夫妻反目、不能正室也。
六四:有孚、血去惕出、无咎。
象曰、有孚惕出、上合志也。
九五:有孚攣如、富以其鄰。
象曰、有孚攣如、不獨富也。
上九:既雨既處、尚德載、婦貞厲。月幾望、君子征凶。
象曰、既雨既處、德積載也。君子征凶、有所疑也
〔読み〕
初九。復(かえ)ること道による。何ぞそれ咎あらん。吉なり。
象に曰く、復ること道によるとは、その義吉なるなり。
九二。牽(ひ)きて復(かえ)る。吉なり。
象に曰く、牽きて復りて中に在り、またみずから失わざるなり。
九三。輿(くるま)幅(とこしばり)を説く。夫妻反目す。
象に曰く、夫妻反目すとは、室を正すこと能わざるなり。
六四。孚(まこと)あり。血(いたみ)去り惕(おそ)れ出づ。咎なし。
象に曰く、孚あり、惕れ出づとは、上、志を合わせばなり。
九五。孚ありて、攣如(れんにょ)たり。富その隣と以(とも)にす。
象に曰く、孚ありて、攣如たりとは、独り富めりとせざるなり。
上九。既に雨ふり既に処(お)る。徳を尚(たっと)びて載(み)つ。婦は貞なれども厲(あやう)し。月望に幾(ちか)し。君子も征けば凶なり。
象に曰く、既に雨ふり既に処るとは、徳積みて載てるなり。君子も征けば凶なりとは、疑わしきところあればなり。
〔解読〕
初九は剛陽居下、上卦に進もうとする志が強いが、正応たる六四の陰爻にひきとどめられ、引き返して正道を守るを得た。どうして咎のあるはずがあろう。吉である。
《象伝》復ること道によるというのは、その行いの正しさが吉なのである。
九二は剛陽居中、初九と牽きあって進みまた牽きあって引き返す。吉である。
《象伝》牽きあって引き返し中位に安んずるのであるから、みずからの守るべき道を失わないのである。
九三は過剛不中、上に進もうとしても六四に引きとどめられ進むことを得ない。たとえて言えば、車の幅〔よこしばり、輹に通ずる、車軸の上にあり車軸と車体を結ぶ革〕がほどけて車体と車輪が離ればなれになり、動かすことが出来ないようになったようなもの。しかも陽剛の身で陰柔に引きとどめられるのであるから心中おだやかならず、たとえて言えば夫妻の仲がしっかりゆかず反目しあうようなものである。
《象伝》夫妻反目すというのは、家庭を正しくおさめることができぬことである。
六四は卦中ただ一つの陰爻ながら正位に居り、しかも上の九五の助けがあるから、誠信をつくしてその人を頼れば、やがては受けた傷の痛みも去り、憂懼不安もなくなり、咎なきを得る。
《象伝》孚あり惕れ出づというのは、上の人が心をあわせてくれるからである。
九五は陽剛中正、誠信をつくし攣如(れんにょ)すなわちひとと手を執りあって事にあたる。富も独占しようとはせずその隣人(六四)と分け合うほどの心意気である。「富みてその隣を以(ひき)ゆ」とも読む。
《象伝》孚ありて攣如たりというのは、自分だけ富もうなどとは考えぬことである。
上九は卦極、小畜すなわち小〔陰〕が衆陽をひきとどめることも極点に達し、陰陽和合して今までの密雲雨ふらざる状態が終り、すでに雨ふり陰陽ともに安らかに処(お)ることを得る象。これは陽が陰を尊び、陰の徳が積もり積もって満ちたからに外ならぬ。しかし陰の徳が積もり満ちて陽をしのぐほどになるのは順当なことではない。たとえば妻たる者はいかに徳あればとて夫を制するような振舞いをしてはならぬであろう。だから妻としてこのような立場に在るものは、いかに貞正であっても危ういと言わねばならぬ。またたとえれば月が満月に近づき、その光が太陽とまぎらわしい状態とも言える。このような時期においては、君子も強引に進もうとすることは凶である。
《象伝》すでに雨ふりすでに処るというのは、陰の徳が積み重ねられて満ちたからである。君子も征(ゆ)けば凶というのは、陰〔小人〕の力が強くて陽〔君子〕とまぎらわしい状態だからである。
昨12月8日は、「太平洋戦争開戦の日」からちょうど70周年の日であった。
1941(昭和16)年12月8日午前3時19分(現地時間7日午前7時49分)、日本軍がハワイ・オアフ島・真珠湾のアメリカ軍基地を奇襲攻撃、3年9ヶ月に及ぶ大東亜戦争対米英戦(太平洋戦争)が勃発した。
 「12月8日午前零時を期して戦闘行動を開始せよ」という意味の暗号電文「ニイタカヤマノボレ1208」が船橋海軍無線電信所から送信され、戦艦アリゾナ等戦艦11隻を撃沈、400機近くの航空機を破壊して、攻撃の成功を告げる「トラトラトラ」という暗号文が打電されたという。
「12月8日午前零時を期して戦闘行動を開始せよ」という意味の暗号電文「ニイタカヤマノボレ1208」が船橋海軍無線電信所から送信され、戦艦アリゾナ等戦艦11隻を撃沈、400機近くの航空機を破壊して、攻撃の成功を告げる「トラトラトラ」という暗号文が打電されたという。
この作戦はあくまでも奇襲作戦であったというが、駐米大使らの怠慢から歴史に汚点を残す“だまし討ち”となった。ワシントンで交渉していた野村・来栖両大使がアメリカ側に、最後通牒を手渡してから攻撃を開始することになっていたというが、最後通牒の文書の作成が大幅に遅れたため、事実上、宣戦布告なき開戦となったのだという。アメリカは「リメンバー・パールハーバー」を戦争遂行の合言葉として、厭戦気分の米国民を鼓舞する結果となったのである。
 また、真珠湾攻撃の1時間5分前、日本陸軍第25軍第18師団は、宣戦布告なしで、不意討ち的にマレー半島のコタバルに上陸し、英軍と戦闘を開始。これは米の対日石油禁輸に対抗して「重要国防資源の獲得」を東南アジアに求め、更には援蒋(蒋介石・国民党政府への支援)ルート遮断を狙ったものであったという。
また、真珠湾攻撃の1時間5分前、日本陸軍第25軍第18師団は、宣戦布告なしで、不意討ち的にマレー半島のコタバルに上陸し、英軍と戦闘を開始。これは米の対日石油禁輸に対抗して「重要国防資源の獲得」を東南アジアに求め、更には援蒋(蒋介石・国民党政府への支援)ルート遮断を狙ったものであったという。
当時の日本では、「大詔奉戴日」と呼ばれた日となり、朝早くから流れる軍艦マーチの合間に、米国と戦闘状態に入ったニュースを胸躍らせながら聞いた多くの日本国民は期せずして一転、塗炭の苦しみを味わうことになったのである。
1941(昭和16)年12月8日午前3時19分(現地時間7日午前7時49分)、日本軍がハワイ・オアフ島・真珠湾のアメリカ軍基地を奇襲攻撃、3年9ヶ月に及ぶ大東亜戦争対米英戦(太平洋戦争)が勃発した。
この作戦はあくまでも奇襲作戦であったというが、駐米大使らの怠慢から歴史に汚点を残す“だまし討ち”となった。ワシントンで交渉していた野村・来栖両大使がアメリカ側に、最後通牒を手渡してから攻撃を開始することになっていたというが、最後通牒の文書の作成が大幅に遅れたため、事実上、宣戦布告なき開戦となったのだという。アメリカは「リメンバー・パールハーバー」を戦争遂行の合言葉として、厭戦気分の米国民を鼓舞する結果となったのである。
当時の日本では、「大詔奉戴日」と呼ばれた日となり、朝早くから流れる軍艦マーチの合間に、米国と戦闘状態に入ったニュースを胸躍らせながら聞いた多くの日本国民は期せずして一転、塗炭の苦しみを味わうことになったのである。
荀子「大略篇第二十七」は弟子達が荀子の言葉を雑録したもので、みなその要点だけを略擧しており、一つの事で篇名とすることが出来ないので、それらをすべて「大略」といったのだという。
荀子 大略篇 第二十七 より
34 易之咸、見夫婦。夫婦之道、不可不正也、君臣父子之本也。咸、感也、以高下下、以男下女、柔上而剛下。
〔訳〕
易の咸の卦は、夫婦のことをあらわしている。夫婦の道は正しくなければならない。それは君臣父子の根本であるからである。咸というのは感じあうことである。高いものが低いものの下にあり、男が女の下にあり、柔弱なものが剛強なものの上にあるからである。
周易〈第31卦〉より
咸:咸、亨、利貞、取女吉。
彖曰、咸、感也。柔上而剛下、二氣感應以相與、止而說、男下女、是以亨利貞、取女吉也。天地感而萬物化生、聖人感人心而天下和平、觀其所感、而天地萬物之情可見矣。
象曰、山上有澤、咸、君子以虛受人。
 〔読み〕
〔読み〕
咸:咸(かん)は享(とお)る。貞(ただ)しきに利(よろ)し。女を取(めと)るは吉なり。
彖(たん)に曰く、咸は感なり。柔上りて剛下り、二気感応してもって相い与(くみ)するなり。止まりて悦(よろこ)び、男は女に下る。ここをもって享(とお)り、貞(ただ)しきは利(よ)ろしく、女を取(めと)るは吉なり。天地感じて万物化生し、聖人人心を感ぜしめて、天下和平なり。その感ずるところを観て、天地万物の情見るべし。
象に曰く、山上に沢あるは咸なり。君子もって虚にして人に受く。
〔訳〕
咸(かん)は感、少男〔艮〕が少女〔兌〕に下り相感ずる卦象に取る。感応すればおのずから享通するが、たがいに貞正であることがよろしい。このようであれば妻をめとるにもきちである。
《彖傳》咸とは感である。柔〔兌〕が上り剛〔艮〕が下って、陰陽の気が感応し相和合するのである。止まって〔艮〕悦び〔兌〕、男〔艮〕が女〔兌〕に下る。なればこそ、享り、貞しくに利ろしく、女を取るのに吉なのである。およそ天地が相感ずることによって万物は化生し、聖人が人心を感じせしめれば、天下に和平がもたされる。その感応しあうところを見れば、おのずから天地万物の情が判るというものである。
《象傳》山〔艮〕の上に沢〔兌〕があるのが咸である。山の高きをもって沢の卑(ひく)きに下るこの卦象にのっとって、君子はおのれを空しくし人を受け容れることにつとめる。
周易 序卦傳 より
有天地然後有萬物、有萬物然後有男女、有男女然後有夫婦、有夫婦然後有父子、有父子然後有君臣、有君臣然後有上下、有上下然後禮義有所錯。
〔読み〕
天地ありて然る後に万物あり。万物ありて然る後に男女あり。男女ありて然る後に夫婦あり。夫婦ありて然る後に父子有り。父子有りて然る後に君臣あり。君臣ありて然る後に上下あり。上下ありて然る後に礼儀錯(お)くところあり。
〔訳〕
天地〔乾坤〕があって始めて万物が生み出され、万物があって始めて雌雄男女の性別が生じ、男女があって始めて夫婦という関係が成立し、夫婦があって始めて親子という関係が成立し、親子があって始めて君臣と言う関係が成立し、君臣があって始めて上下階級の差別も生ずるし、上下があって始めて礼儀が措きさだめられる。
荀子 大略篇 第二十七 より
34 易之咸、見夫婦。夫婦之道、不可不正也、君臣父子之本也。咸、感也、以高下下、以男下女、柔上而剛下。
〔訳〕
易の咸の卦は、夫婦のことをあらわしている。夫婦の道は正しくなければならない。それは君臣父子の根本であるからである。咸というのは感じあうことである。高いものが低いものの下にあり、男が女の下にあり、柔弱なものが剛強なものの上にあるからである。
周易〈第31卦〉より
咸:咸、亨、利貞、取女吉。
彖曰、咸、感也。柔上而剛下、二氣感應以相與、止而說、男下女、是以亨利貞、取女吉也。天地感而萬物化生、聖人感人心而天下和平、觀其所感、而天地萬物之情可見矣。
象曰、山上有澤、咸、君子以虛受人。
咸:咸(かん)は享(とお)る。貞(ただ)しきに利(よろ)し。女を取(めと)るは吉なり。
彖(たん)に曰く、咸は感なり。柔上りて剛下り、二気感応してもって相い与(くみ)するなり。止まりて悦(よろこ)び、男は女に下る。ここをもって享(とお)り、貞(ただ)しきは利(よ)ろしく、女を取(めと)るは吉なり。天地感じて万物化生し、聖人人心を感ぜしめて、天下和平なり。その感ずるところを観て、天地万物の情見るべし。
象に曰く、山上に沢あるは咸なり。君子もって虚にして人に受く。
〔訳〕
咸(かん)は感、少男〔艮〕が少女〔兌〕に下り相感ずる卦象に取る。感応すればおのずから享通するが、たがいに貞正であることがよろしい。このようであれば妻をめとるにもきちである。
《彖傳》咸とは感である。柔〔兌〕が上り剛〔艮〕が下って、陰陽の気が感応し相和合するのである。止まって〔艮〕悦び〔兌〕、男〔艮〕が女〔兌〕に下る。なればこそ、享り、貞しくに利ろしく、女を取るのに吉なのである。およそ天地が相感ずることによって万物は化生し、聖人が人心を感じせしめれば、天下に和平がもたされる。その感応しあうところを見れば、おのずから天地万物の情が判るというものである。
《象傳》山〔艮〕の上に沢〔兌〕があるのが咸である。山の高きをもって沢の卑(ひく)きに下るこの卦象にのっとって、君子はおのれを空しくし人を受け容れることにつとめる。
周易 序卦傳 より
有天地然後有萬物、有萬物然後有男女、有男女然後有夫婦、有夫婦然後有父子、有父子然後有君臣、有君臣然後有上下、有上下然後禮義有所錯。
〔読み〕
天地ありて然る後に万物あり。万物ありて然る後に男女あり。男女ありて然る後に夫婦あり。夫婦ありて然る後に父子有り。父子有りて然る後に君臣あり。君臣ありて然る後に上下あり。上下ありて然る後に礼儀錯(お)くところあり。
〔訳〕
天地〔乾坤〕があって始めて万物が生み出され、万物があって始めて雌雄男女の性別が生じ、男女があって始めて夫婦という関係が成立し、夫婦があって始めて親子という関係が成立し、親子があって始めて君臣と言う関係が成立し、君臣があって始めて上下階級の差別も生ずるし、上下があって始めて礼儀が措きさだめられる。
荀子 賦篇 第二十六 ―佹詩-
天下不治、請陳佹詩:天地易位、四時易鄉。列星殞墜、旦暮晦盲。幽闇登昭、日月下藏。公正無私、見謂從橫。志愛公利、重樓疏堂。無私罪人、憼革貳兵。道德純備、讒口將將。仁人絀約、敖暴擅彊。天下幽險、恐失世英。螭龍為蝘蜓、鴟梟為鳳凰。比干見刳、孔子拘匡。昭昭乎其知之明也、郁郁乎其遇時之不祥也、拂乎其欲禮義之大行也、闇乎天下之晦盲也、皓天不復、憂無疆也。千歲必反、古之常也。弟子勉學、天不忘也。聖人共手、時幾將矣。與愚以疑、願聞反辭。
其小歌曰:念彼遠方、何其塞矣、仁人絀約、暴人衍矣。忠臣危殆、讒人服矣。
天下乱れて 治まらず 変調詩にて 具陳せん。
天地の位 入れかわり 四時のめぐりは さかしまに 多くの星も おちおちに 朝夕すべて うす暗し。闇愚の者の 栄え居り 明知の君子 下にかくるる。公正無私を 縦横〔合従連衡のこと、権謀術策をもってするひと〕といい 公利はかるも 高楼作り なすという〔私慾をはかって高い大きな邸宅を構えていると言われる〕。罪人に私す ことなきに 甲兵備え いましめる〔罪人に対して公平に刑罰に処しているのに帰って人に憎まれて、武器を調え自ら警備している〕。道徳専ら 修むるも 讒言多く 来るなり。仁者屈して 困窮し 傲暴意を得 専擅(せんぜん)す〔人をあなどった乱暴者が得意になって、わがまま勝手なことをする〕。天下の暗危 かくならば 何ぞ用いん 賢人を。螭竜をみなし 蝘蜓とし〔螭竜のような高貴な神獣を蝘蜓(ヤモリ)だとおもう〕 鴟梟かえって 鳳凰ぞ〔いやしい鴟梟(ふくろう)を尊い鳳凰と思う――善悪の分らないことをいう〕。比干は心(むね)を 開かれて 孔子は 匡(きょう)に 捕わるる。昭昭として 明知なる 輝き見んと 願いしに 遂に不詳の 時に遇う。郁郁として 礼義こそ 大行せんと 望みしに かえって天下 くろぐろし。皓たる天は かえり来ず 憂いは常に 限りなし。千年経(ふ)れば 反えるとは 古よりの 常の道。弟子学のみ 勉めなば 天も忘れじ たすくらん。聖人手をば こまぬけど 時世再び めぐりこん。我れ愚かにて 疑えり。こい願わくは 更に反辞を いざ聞かん。小歌に曰く、
彼の遠方を 念えば何ぞ 険難ぞ 仁人屈して 困窮し 暴人意を得て はびこりぬ 忠臣常に 危殆にて 讒人のみが たのしめり。
琁、玉、瑤、珠、不知佩也、雜布與帛、不知異也。閭娵子奢、莫之媒也;嫫母力父、是之喜也。以盲為明、以聾為聰、以危為安、以吉為凶。嗚呼!上天!曷維其同!
 琁玉瑤珠(せんぎょくようしゅ)佩(お)ぶるを知らず 布錦混じるも 分くるを知らず。閭娵(りょしゅ)と子奢(ししゃ)には 媒(ばい)なすなくて 嫫母(ぼぼ)・刀父に 意を用う。盲者(めくら)を以て 明となし 聾者(つんぼ)を以て 聡となし 危険を以て 安しとし 吉事を以て 凶となす。ああ 上天 如何ぞこれに 讃同せんや。
琁玉瑤珠(せんぎょくようしゅ)佩(お)ぶるを知らず 布錦混じるも 分くるを知らず。閭娵(りょしゅ)と子奢(ししゃ)には 媒(ばい)なすなくて 嫫母(ぼぼ)・刀父に 意を用う。盲者(めくら)を以て 明となし 聾者(つんぼ)を以て 聡となし 危険を以て 安しとし 吉事を以て 凶となす。ああ 上天 如何ぞこれに 讃同せんや。
天下不治、請陳佹詩:天地易位、四時易鄉。列星殞墜、旦暮晦盲。幽闇登昭、日月下藏。公正無私、見謂從橫。志愛公利、重樓疏堂。無私罪人、憼革貳兵。道德純備、讒口將將。仁人絀約、敖暴擅彊。天下幽險、恐失世英。螭龍為蝘蜓、鴟梟為鳳凰。比干見刳、孔子拘匡。昭昭乎其知之明也、郁郁乎其遇時之不祥也、拂乎其欲禮義之大行也、闇乎天下之晦盲也、皓天不復、憂無疆也。千歲必反、古之常也。弟子勉學、天不忘也。聖人共手、時幾將矣。與愚以疑、願聞反辭。
其小歌曰:念彼遠方、何其塞矣、仁人絀約、暴人衍矣。忠臣危殆、讒人服矣。
天下乱れて 治まらず 変調詩にて 具陳せん。
天地の位 入れかわり 四時のめぐりは さかしまに 多くの星も おちおちに 朝夕すべて うす暗し。闇愚の者の 栄え居り 明知の君子 下にかくるる。公正無私を 縦横〔合従連衡のこと、権謀術策をもってするひと〕といい 公利はかるも 高楼作り なすという〔私慾をはかって高い大きな邸宅を構えていると言われる〕。罪人に私す ことなきに 甲兵備え いましめる〔罪人に対して公平に刑罰に処しているのに帰って人に憎まれて、武器を調え自ら警備している〕。道徳専ら 修むるも 讒言多く 来るなり。仁者屈して 困窮し 傲暴意を得 専擅(せんぜん)す〔人をあなどった乱暴者が得意になって、わがまま勝手なことをする〕。天下の暗危 かくならば 何ぞ用いん 賢人を。螭竜をみなし 蝘蜓とし〔螭竜のような高貴な神獣を蝘蜓(ヤモリ)だとおもう〕 鴟梟かえって 鳳凰ぞ〔いやしい鴟梟(ふくろう)を尊い鳳凰と思う――善悪の分らないことをいう〕。比干は心(むね)を 開かれて 孔子は 匡(きょう)に 捕わるる。昭昭として 明知なる 輝き見んと 願いしに 遂に不詳の 時に遇う。郁郁として 礼義こそ 大行せんと 望みしに かえって天下 くろぐろし。皓たる天は かえり来ず 憂いは常に 限りなし。千年経(ふ)れば 反えるとは 古よりの 常の道。弟子学のみ 勉めなば 天も忘れじ たすくらん。聖人手をば こまぬけど 時世再び めぐりこん。我れ愚かにて 疑えり。こい願わくは 更に反辞を いざ聞かん。小歌に曰く、
彼の遠方を 念えば何ぞ 険難ぞ 仁人屈して 困窮し 暴人意を得て はびこりぬ 忠臣常に 危殆にて 讒人のみが たのしめり。
琁、玉、瑤、珠、不知佩也、雜布與帛、不知異也。閭娵子奢、莫之媒也;嫫母力父、是之喜也。以盲為明、以聾為聰、以危為安、以吉為凶。嗚呼!上天!曷維其同!
荀子 賦篇 第二十六 ―箴―
有物於此、生於山阜、處於室堂。無知無巧、善治衣裳。不盜不竊、穿窬而行。日夜合離、以成文章。以能合從、又善連衡。下覆百姓、上飾帝王。功業甚博、不見賢良。時用則存、不用則亡。臣愚不識、敢請之王。
王曰:此夫始生鉅、其成功小者邪? 長其尾而銳其剽者邪? 頭銛達而尾趙繚者邪? 一往一來、結尾以為事。無羽無翼、反覆甚極。尾生而事起、尾邅而事已。簪以為父、管以為母。既以縫表、又以連裡:夫是之謂箴理。箴。
ここに物あり 山に生まるも 家に住みつき 智巧なけれど 裁縫上手 盗みせざるも 穴抜け巧み。離散合わせて 美飾を作る。縦を合わせて また横つらぬ 下民に着せて 帝王飾り。功の広大 隠して見せず。必要なれば あらわるも 用なきときは 身をかくす。我れ愚かにて わきまえず その何たるかを 王に聞く。
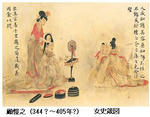 答えて曰く これはこれ 生まれは巨大 功なすときは 小なるものぞ。その尾は長く 先の鋭き ものならん。頭(かしら)先鋭 長くまつわる 尾あるもの。往来ごとに 結びつけては 事を成す。羽翼なくとも 反覆早し。尾生ずれば 仕事始まり 尾巡りてぞ 事終わる。錐を父とし 管を母とす。表終れば 裏も縫いつく これこそ箴理(しんり)なるものぞ。 ――箴――
答えて曰く これはこれ 生まれは巨大 功なすときは 小なるものぞ。その尾は長く 先の鋭き ものならん。頭(かしら)先鋭 長くまつわる 尾あるもの。往来ごとに 結びつけては 事を成す。羽翼なくとも 反覆早し。尾生ずれば 仕事始まり 尾巡りてぞ 事終わる。錐を父とし 管を母とす。表終れば 裏も縫いつく これこそ箴理(しんり)なるものぞ。 ――箴――
有物於此、生於山阜、處於室堂。無知無巧、善治衣裳。不盜不竊、穿窬而行。日夜合離、以成文章。以能合從、又善連衡。下覆百姓、上飾帝王。功業甚博、不見賢良。時用則存、不用則亡。臣愚不識、敢請之王。
王曰:此夫始生鉅、其成功小者邪? 長其尾而銳其剽者邪? 頭銛達而尾趙繚者邪? 一往一來、結尾以為事。無羽無翼、反覆甚極。尾生而事起、尾邅而事已。簪以為父、管以為母。既以縫表、又以連裡:夫是之謂箴理。箴。
ここに物あり 山に生まるも 家に住みつき 智巧なけれど 裁縫上手 盗みせざるも 穴抜け巧み。離散合わせて 美飾を作る。縦を合わせて また横つらぬ 下民に着せて 帝王飾り。功の広大 隠して見せず。必要なれば あらわるも 用なきときは 身をかくす。我れ愚かにて わきまえず その何たるかを 王に聞く。
プロフィール
ハンドルネーム:
目高 拙痴无
年齢:
93
誕生日:
1932/02/04
自己紹介:
くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。
sechin@nethome.ne.jp です。
sechin@nethome.ne.jp です。
カレンダー
| 12 | 2026/01 | 02 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新コメント
[enken 02/23]
[中村東樹 02/04]
[m、m 02/04]
[爺の姪 01/13]
[レンマ学(メタ数学) 01/02]
[m.m 10/12]
[爺の姪 10/01]
[あは♡ 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター
