瘋癲爺 拙痴无の戯言・放言・歯軋り
孟子 告子章句上 より
公都子曰:「告子曰:『性無善無不善也。』或曰:『性可以為善、可以為不善;是故文武興、則民好善;幽厲興、則民好暴。』或曰:『有性善、有性不善;是故以堯為君而有象、以瞽瞍為父而有舜;以紂為兄之子且以為君、而有微子啟、王子比干。』今曰『性善』、然則彼皆非與?」
打開字典顯示更多訊息 孟子曰:「乃若其情、則可以為善矣、乃所謂善也。若夫為不善、非才之罪也。惻隱之心、人皆有之;羞惡之心、人皆有之;恭敬之心、人皆有之;是非之心、人皆有之。惻隱之心、仁也;羞惡之心、義也;恭敬之心、禮也;是非之心、智也。仁義禮智、非由外鑠我也、我固有之也、弗思耳矣。故曰:『求則得之、舍則失之。』或相倍蓰而無算者、不能盡其才者也。《詩》曰:『天生蒸民、有物有則。民之秉夷、好是懿德。』孔子曰:『為此詩者、其知道乎!故有物必有則、民之秉夷也、故好是懿德。』」
〔訳〕
公都子が言った。
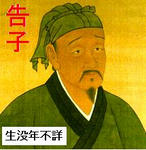

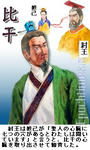
「告子は『人間の本性は善もなければ不善もない』と言い、ある人は『人間の本性は善をすることもできれば、不善をすることも出来る。だから文王・武王のような聖王が現れれば人民はみな善を好むようになり、幽王・厲王のような暴君が現れれば人民はみな乱暴なことを好むようになる』と言っております。また別の人は『本性の善い人もいれば善くない人もいる。だから聖天子尭の下にも象〔しょう、舜の異母弟〕のような悪人が出、瞽瞍〔こそう、舜の父〕のような悪人の子にも舜のような聖人が顕れ、また兄の子に紂王のような悪人を持ち、かつそれを君主としながら微子啓(びしけん)や、王子比干(ひかん)のような賢人が現れたのだ』と言います。ところが、先生は『人間の本性は善だ』とおっしゃるのですが、これらの意見はみな間違いでございますか」
孟子は言った。
「本性が物に触れて外に現れたもの、それが情であるが、そのごく自然に現れた心情のままに従って行動すれば、人は必ず善をするはずのものである。これがわたしの、『本性は善だ』という説である。たしかに人間は善くない事をするが、それは物欲にくらまされるためで、人間の素質の罪ではないのだ。憐れみの心は誰でも持っている。恥ずかしいと思う心も誰でも持っている。敬い慎む心や、是非を判別する心も誰でも持っている。この憐れみの心は仁であり、恥ずかしいと思う心は義であり、敬い慎む心は礼であり、是非を判別心は智であるのだ。仁義礼智の徳は決して外から鍍金(メッキ)されたものではなく、自分がもともと持っているものである。ただ人はぼんやりしていてそれに気付いていないだけだ。だからわたしは、『これらの徳は求めさえすれば得られるけれど、放っておけばなくなってしまうものだ』と言うのである。求めるか求めないかによって、善と悪との開きは、或は倍となり五倍となり、ついには測ることの出来ぬほどに大きくなってしまうが、それは本性に善・不善があるためではなく、持って生まれた素質をすっかり発揮できたか、できなかったかによるのである。『詩経』(大雅・烝民篇)にも、
天もろもろの民を生みしとき/ものなべて法(のり)あらしめき/民 この変わらざる法のもと/この美(うる)わしの徳を好めり
とあるが、孔子は『この詩を作った人は道がわかっているね』と言ったという。このように物には必ず法則があるのであって、民衆本来の心も、もともとこの美しい徳を好むものなのである」
公都子曰:「告子曰:『性無善無不善也。』或曰:『性可以為善、可以為不善;是故文武興、則民好善;幽厲興、則民好暴。』或曰:『有性善、有性不善;是故以堯為君而有象、以瞽瞍為父而有舜;以紂為兄之子且以為君、而有微子啟、王子比干。』今曰『性善』、然則彼皆非與?」
打開字典顯示更多訊息 孟子曰:「乃若其情、則可以為善矣、乃所謂善也。若夫為不善、非才之罪也。惻隱之心、人皆有之;羞惡之心、人皆有之;恭敬之心、人皆有之;是非之心、人皆有之。惻隱之心、仁也;羞惡之心、義也;恭敬之心、禮也;是非之心、智也。仁義禮智、非由外鑠我也、我固有之也、弗思耳矣。故曰:『求則得之、舍則失之。』或相倍蓰而無算者、不能盡其才者也。《詩》曰:『天生蒸民、有物有則。民之秉夷、好是懿德。』孔子曰:『為此詩者、其知道乎!故有物必有則、民之秉夷也、故好是懿德。』」
〔訳〕
公都子が言った。
「告子は『人間の本性は善もなければ不善もない』と言い、ある人は『人間の本性は善をすることもできれば、不善をすることも出来る。だから文王・武王のような聖王が現れれば人民はみな善を好むようになり、幽王・厲王のような暴君が現れれば人民はみな乱暴なことを好むようになる』と言っております。また別の人は『本性の善い人もいれば善くない人もいる。だから聖天子尭の下にも象〔しょう、舜の異母弟〕のような悪人が出、瞽瞍〔こそう、舜の父〕のような悪人の子にも舜のような聖人が顕れ、また兄の子に紂王のような悪人を持ち、かつそれを君主としながら微子啓(びしけん)や、王子比干(ひかん)のような賢人が現れたのだ』と言います。ところが、先生は『人間の本性は善だ』とおっしゃるのですが、これらの意見はみな間違いでございますか」
孟子は言った。
「本性が物に触れて外に現れたもの、それが情であるが、そのごく自然に現れた心情のままに従って行動すれば、人は必ず善をするはずのものである。これがわたしの、『本性は善だ』という説である。たしかに人間は善くない事をするが、それは物欲にくらまされるためで、人間の素質の罪ではないのだ。憐れみの心は誰でも持っている。恥ずかしいと思う心も誰でも持っている。敬い慎む心や、是非を判別する心も誰でも持っている。この憐れみの心は仁であり、恥ずかしいと思う心は義であり、敬い慎む心は礼であり、是非を判別心は智であるのだ。仁義礼智の徳は決して外から鍍金(メッキ)されたものではなく、自分がもともと持っているものである。ただ人はぼんやりしていてそれに気付いていないだけだ。だからわたしは、『これらの徳は求めさえすれば得られるけれど、放っておけばなくなってしまうものだ』と言うのである。求めるか求めないかによって、善と悪との開きは、或は倍となり五倍となり、ついには測ることの出来ぬほどに大きくなってしまうが、それは本性に善・不善があるためではなく、持って生まれた素質をすっかり発揮できたか、できなかったかによるのである。『詩経』(大雅・烝民篇)にも、
天もろもろの民を生みしとき/ものなべて法(のり)あらしめき/民 この変わらざる法のもと/この美(うる)わしの徳を好めり
とあるが、孔子は『この詩を作った人は道がわかっているね』と言ったという。このように物には必ず法則があるのであって、民衆本来の心も、もともとこの美しい徳を好むものなのである」
PR
孟子 公孫丑章句上 より (四端)
孟子曰:「人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心、斯有不忍人之政矣。以不忍人之心、行不忍人之政、治天下可運之掌上。所以謂人皆有不忍人之心者、今人乍見孺子將入於井、皆有怵惕惻隱之心。非所以內交於孺子之父母也、非所以要譽於鄉黨朋友也、非惡其聲而然也。由是觀之、無惻隱之心、非人也;無羞惡之心、非人也;無辭讓之心、非人也;無是非之心、非人也。惻隱之心、仁之端也;羞惡之心、義之端也;辭讓之心、禮之端也;是非之心、智之端也。人之有是四端也、猶其有四體也。有是四端而自謂不能者、自賊者也;謂其君不能者、賊其君者也。凡有四端於我者、知皆擴而充之矣、若火之始然、泉之始達。苟能充之、足以保四海;苟不充之、不足以事父母。」
〔訳〕
孟子は言う。
「人には誰でも他人の不幸を見るとじっとしていられない心があるものだ。昔のすぐれた王にはこの心があったからこそ、民の不幸を見過ごせぬという情味溢れる政治が出来たのである。他人の不幸を見るとじっとしていられない心で情味溢れる政治を行うならば、天下を治めるのは、手のひらの上で物を転がすように容易いことである。では何を証拠に、人には誰でも他人の不幸を見過ごすことに耐え難い心があるというのか。今仮に、井戸に落ちそうになっている幼児をふと見たとしよう。すると誰でも、これは大変、可哀想でたまらぬという気持ちになって、思わず助けようと駆け寄るものだ。べつだんそうする事によって幼児の両親と懇意になろうという魂胆があるためではない。村の人たちや友人に誉められたいというためでもない。見殺しにして悪評が立つのが厭だからというのでもない。全く無意識に、反射的にそうするのである。このことから見ても、可哀想でたまらぬという憐れみの心のないものは人間ではないのだ。同様に、不善を恥じにくむ心のないものは人間ではない。自分をさしおいて人に譲る心のない者は人間ではない。是非を判別する心のない者は人間ではない。
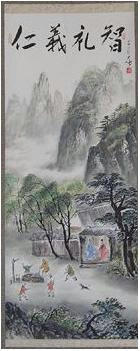 可哀想でたまらぬという憐れみ〔惻隠〕の心は仁の芽生えであり、不善をにくむ〔羞悪〕心は義の芽生え、自分をさしおいて人に譲る〔辭譲〕心は礼の芽生え、可・不可を判別する〔是非〕心は智の芽生えである。人間にこの四つの芽生え〔四端〕が備わっているのは、ちょうど身体に四肢が備わっているようなものだ。それにも拘らず、自分は駄目だ、とても立派な行いは出来ぬと諦めてしまう人は、自分で自分を傷つけるものだ。また、わが君は駄目だといって見捨ててしまう人は、自分の主君を傷つけるものだ。人間にはみなこの四つの芽生えが備わっている以上、すべてこれを広げて中身を満たしてゆけばよいということは、誰でも直感的に判るはずだ。燃え始めの火や、河の源はごく小さくとも、やがては猛火・大河となってゆくように、この四つの芽生えを拡張してゆくならば、ついには全世界をも安らかに治めてゆけるほどの立派な徳になるだろう。しかし、もしその中身を充実させなければ、やがては枯れ果てて、それでは両親に仕えることすらも満足にできなくなってしまうだろう」
可哀想でたまらぬという憐れみ〔惻隠〕の心は仁の芽生えであり、不善をにくむ〔羞悪〕心は義の芽生え、自分をさしおいて人に譲る〔辭譲〕心は礼の芽生え、可・不可を判別する〔是非〕心は智の芽生えである。人間にこの四つの芽生え〔四端〕が備わっているのは、ちょうど身体に四肢が備わっているようなものだ。それにも拘らず、自分は駄目だ、とても立派な行いは出来ぬと諦めてしまう人は、自分で自分を傷つけるものだ。また、わが君は駄目だといって見捨ててしまう人は、自分の主君を傷つけるものだ。人間にはみなこの四つの芽生えが備わっている以上、すべてこれを広げて中身を満たしてゆけばよいということは、誰でも直感的に判るはずだ。燃え始めの火や、河の源はごく小さくとも、やがては猛火・大河となってゆくように、この四つの芽生えを拡張してゆくならば、ついには全世界をも安らかに治めてゆけるほどの立派な徳になるだろう。しかし、もしその中身を充実させなければ、やがては枯れ果てて、それでは両親に仕えることすらも満足にできなくなってしまうだろう」
孟子曰:「人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心、斯有不忍人之政矣。以不忍人之心、行不忍人之政、治天下可運之掌上。所以謂人皆有不忍人之心者、今人乍見孺子將入於井、皆有怵惕惻隱之心。非所以內交於孺子之父母也、非所以要譽於鄉黨朋友也、非惡其聲而然也。由是觀之、無惻隱之心、非人也;無羞惡之心、非人也;無辭讓之心、非人也;無是非之心、非人也。惻隱之心、仁之端也;羞惡之心、義之端也;辭讓之心、禮之端也;是非之心、智之端也。人之有是四端也、猶其有四體也。有是四端而自謂不能者、自賊者也;謂其君不能者、賊其君者也。凡有四端於我者、知皆擴而充之矣、若火之始然、泉之始達。苟能充之、足以保四海;苟不充之、不足以事父母。」
〔訳〕
孟子は言う。
「人には誰でも他人の不幸を見るとじっとしていられない心があるものだ。昔のすぐれた王にはこの心があったからこそ、民の不幸を見過ごせぬという情味溢れる政治が出来たのである。他人の不幸を見るとじっとしていられない心で情味溢れる政治を行うならば、天下を治めるのは、手のひらの上で物を転がすように容易いことである。では何を証拠に、人には誰でも他人の不幸を見過ごすことに耐え難い心があるというのか。今仮に、井戸に落ちそうになっている幼児をふと見たとしよう。すると誰でも、これは大変、可哀想でたまらぬという気持ちになって、思わず助けようと駆け寄るものだ。べつだんそうする事によって幼児の両親と懇意になろうという魂胆があるためではない。村の人たちや友人に誉められたいというためでもない。見殺しにして悪評が立つのが厭だからというのでもない。全く無意識に、反射的にそうするのである。このことから見ても、可哀想でたまらぬという憐れみの心のないものは人間ではないのだ。同様に、不善を恥じにくむ心のないものは人間ではない。自分をさしおいて人に譲る心のない者は人間ではない。是非を判別する心のない者は人間ではない。
孟子が生きた時代は人の本性についての関心が高まり、「性には善も悪もない」とする告子の性無記説(または性白紙説)や「性が善である人もいるが、悪である人もいる」とする説、「人の中で善悪が入り交じっている」とする諸説が流布していた。これらに対し孟子は「性善説」を唱えた。これは孔子の忠信説を発展させたものとされる。
孟子の「性善説」とは、あらゆる人に善の兆しが先天的に備わっているとする説である。善の兆しとは、以下に挙げる四端の心を指す。なお「端」とは、兆し、はしり、あるいは萌芽を意味する。
(1)惻隠…他者の苦境を見過ごせない「忍びざる心」(憐れみの心) (2)羞悪…不正を羞恥する心
(3)辞譲…謙譲の心 (4)是非…善悪を分別する心
修養することによってこれらを拡充し、「仁・義・礼・智」という4つの徳を顕現させ、聖人・君子へと至ることができるとする。端的に言えば、善の兆しとは善となるための可能性である。
人には善の兆しが先天的に具備していると孟子が断定し得たのは、人の運命や事の成否、天下の治乱などをあるべくしてあらしめる理法としての性格を有する天にこそ、人の道徳性が由来すると考えたためである。しかしこの考えは実際と照らし合わせた時、大きな矛盾を突きつける。現実においては、社会に悪が横行している状態を説明できないからである。こうした疑問に対し、孟子は以下のように説明する。悪は人の外に存在するものであるが、天が人に与えたもの、すなわち「性」には「耳目の官」(官とは働き・機能を意味する)と「心の官」が有り、外からの影響を「耳目の官」が受けることにより、「心の官」に宿る善の兆しが曇らされるのだ、と。すなわち善は人に内在する天の理法であり、悪は外在する環境にあると説いた。
荀子は人間の能力、人間の努力を人間生活にとって天よりも優位に考えるから、現実的な人間社会の重視という観点より、人間の本性は自然なままにしておくと社会生活を混乱に陥れる結果を齎すから悪であるという。荀子は悪は偏険悖乱(へんけんはいらん)であり、善は正理平治であると規定していることからしても、人の本性は如何なる時、場所でも、絶対に悪であり、それは人間である限り、一人だけであろうと多人数で生活しようと悪悪であるといっているのではない。人間の本性を自然のままに放置して社会生活をさすという事が前提になって初めてあくが出てくるのである。人間の本性を自然なままではなくて、本性と自制の訓練と教育と努力によって、秩序と礼義に従うようにすれば正理平治、即ち善になるのである。荀子にあっては、本性自体の善悪に問題があるのではなくて、社会生活をする上で本性を自然なままの状態に置くか、人間の作った規制(礼義)に従うかによって善悪がきめられるのである。
本性は誰も同じものを持っているから、性については聖人も凡人も同じであるが、それを自然なままのはたらきに任せるのではなくて、道徳、礼義、聖人の作った規範に従ってはたらかすと言う点においては、聖人と凡人の差が出てくるという。こういう考えを前提として学問の重要性、身を修めることの必要聖、教育の必要性も説かれているのである。
荀子 正論篇 第十八 より 〔井底之蛙〕
世俗之為說者曰:「湯武不善禁令。」曰:「是何也?」曰:「楚越不受制。」是不然。湯武者、至天下之善禁令者也。湯居亳、武王居鄗、皆百里之地也、天下為一、諸侯為臣、通達之屬、莫不振動從服以化順之、曷為楚越獨不受制也!
彼王者之制也、視形埶而制械用、稱遠邇而等貢獻、豈必齊哉!故魯人以榶、衛人用柯、齊人用一革、土地刑制不同者、械用、備飾不可不異也。故諸夏之國同服同儀、蠻、夷、戎、狄之國同服不同制。封內甸服、封外侯服、侯衛賓服、蠻夷要服、戎狄荒服。甸服者祭、侯服者祀、賓服者享、要服者貢、荒服者終王。日祭、月祀、時享、歲貢、終王、夫是之謂視形埶而制械用、稱遠近而等貢獻;是王者之制也。
彼楚越者、且時享、歲貢、終王之屬也、必齊之日祭月祀之屬、然後曰受制邪?是規磨之說也。溝中之瘠也、則未足與及王者之制也。語曰:「淺不足與測深、愚不足與謀智、坎井之蛙、不可與語東海之樂。」此之謂也。

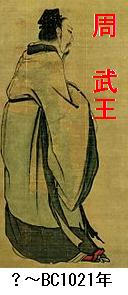 〔訳〕
〔訳〕
世の中で色々説を述べている者の中で、「湯王・武王は天下に普く禁令をゆきわたらせることができなかった」と言っているが、これはどういうことであるかと問うと、「それは楚と越の二つの国が命令に従わなかったからである」と述べているが、これはそうではなくて誤っている。湯王・武王はきわめてうまく天下に禁令をゆきわたらせた人たちである。湯王は亳(はく)という所に居り、武王は鄗(こう)という所に居たが、ともに百里四方の土地に過ぎなかった。しかし天下は一になり、諸侯は臣として仕え、舟や車の通ずる所に住んでいる者たちは、恐れおののき服従し、その徳に感化され従順に使えないものはなかった。どうして楚と越だけが命令に服さないということがあろうか。
王者が天下を治める制度は、土地の形勢(ようす)を見てその使用する器械を定め、習慣にかなわせ、国の遠近をはかってその貢ぎ物の差別をした。決してすべてを同じようにはしなかったのである。だから魯の国の人は榶〔とう・わん〕を献じ、衛の国の人は柯〔か・わん〕を献じ、斉の国の人は皮革を献じた。土地の形勢が違っているとそれに使う器械や服飾もまた違わなければならない。だから中原の諸国は王者に同じように仕え、その制度も同じようにするが、蕃夷戎狄〔ばんいじゅうてき・四方の野蛮国〕の国は、同じように王者に仕えるが、その制度は異なるものである。
都を中心とした五百里四方以内の土地は、王の田を耕すことで仕え〔甸服(でんぷく)〕、方五百里以外の諸侯の土地は、王のために四方をうかがって、思いがけない災難に備えることによって仕え〔侯服〕、侯衛の地の諸侯は、お客の格式で仕え〔賓服〕、蕃夷の国は、好信(よしみ)を結ぶことで仕え〔要服〕、戎狄の国は、何の定めもなく仕える〔荒服〕。甸服の者は祭りごとに物を献じ、侯服の者は祀りごとに物を献じ、賓服の者は享(まつ)りごとに物を献じ、要服の者は歳毎に物を献じ、荒服の者はただ王として仕えるだけで何も献じない。
祭りごとに物を献ずるのは、朝廷の日々の祭に献ずることであり、祀りごとに献ずるのは、朝廷の月々の祀りに献ずることであり、享(まつ)りごとに献ずるのは、朝廷の四季の享りに献ずることであり、歳毎に献ずるのは、朝廷の歳ごとの祀りに献ずることであり、王として仕えるだけなのは、前の王がやめて新しい王が位に即くときに来朝することである。このようなことを土地の形勢を見てその使用する器械を定め習慣に従わせ、遠近を計ってその貢ぎ物を差別するというのである。これが王者の天下を治める制度である。
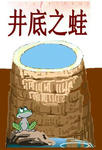 あの楚と越の国は、四季の享りごとに物を献ずる賓服の国か、歳ごとに物を献ずる要服の国か、新王の即位するときにだけ来朝する荒服の国かのいずれかに属している国である。それをこの二国は必ず日々の祭りに献ずる甸服の民とか、月々の祀りにけんずる侯服の国に属するものとして、王の命令を受けるべきものと考えているようである。これは自分勝手に押し付けた理論である。ことわざに「浅薄な者とは、ともに深く大きいことは測れない。愚かな者とは、ともに思慮深いことは謀れない。壊れた井戸の蛙とはともに東海の広く大きい楽しみを語ることは出来ない。知慮の浅い乞食とともに王者の制度を語ることは出来ない」とあるが、まことにこの論者のことを言っているのである。
あの楚と越の国は、四季の享りごとに物を献ずる賓服の国か、歳ごとに物を献ずる要服の国か、新王の即位するときにだけ来朝する荒服の国かのいずれかに属している国である。それをこの二国は必ず日々の祭りに献ずる甸服の民とか、月々の祀りにけんずる侯服の国に属するものとして、王の命令を受けるべきものと考えているようである。これは自分勝手に押し付けた理論である。ことわざに「浅薄な者とは、ともに深く大きいことは測れない。愚かな者とは、ともに思慮深いことは謀れない。壊れた井戸の蛙とはともに東海の広く大きい楽しみを語ることは出来ない。知慮の浅い乞食とともに王者の制度を語ることは出来ない」とあるが、まことにこの論者のことを言っているのである。
世俗之為說者曰:「湯武不善禁令。」曰:「是何也?」曰:「楚越不受制。」是不然。湯武者、至天下之善禁令者也。湯居亳、武王居鄗、皆百里之地也、天下為一、諸侯為臣、通達之屬、莫不振動從服以化順之、曷為楚越獨不受制也!
彼王者之制也、視形埶而制械用、稱遠邇而等貢獻、豈必齊哉!故魯人以榶、衛人用柯、齊人用一革、土地刑制不同者、械用、備飾不可不異也。故諸夏之國同服同儀、蠻、夷、戎、狄之國同服不同制。封內甸服、封外侯服、侯衛賓服、蠻夷要服、戎狄荒服。甸服者祭、侯服者祀、賓服者享、要服者貢、荒服者終王。日祭、月祀、時享、歲貢、終王、夫是之謂視形埶而制械用、稱遠近而等貢獻;是王者之制也。
彼楚越者、且時享、歲貢、終王之屬也、必齊之日祭月祀之屬、然後曰受制邪?是規磨之說也。溝中之瘠也、則未足與及王者之制也。語曰:「淺不足與測深、愚不足與謀智、坎井之蛙、不可與語東海之樂。」此之謂也。
世の中で色々説を述べている者の中で、「湯王・武王は天下に普く禁令をゆきわたらせることができなかった」と言っているが、これはどういうことであるかと問うと、「それは楚と越の二つの国が命令に従わなかったからである」と述べているが、これはそうではなくて誤っている。湯王・武王はきわめてうまく天下に禁令をゆきわたらせた人たちである。湯王は亳(はく)という所に居り、武王は鄗(こう)という所に居たが、ともに百里四方の土地に過ぎなかった。しかし天下は一になり、諸侯は臣として仕え、舟や車の通ずる所に住んでいる者たちは、恐れおののき服従し、その徳に感化され従順に使えないものはなかった。どうして楚と越だけが命令に服さないということがあろうか。
王者が天下を治める制度は、土地の形勢(ようす)を見てその使用する器械を定め、習慣にかなわせ、国の遠近をはかってその貢ぎ物の差別をした。決してすべてを同じようにはしなかったのである。だから魯の国の人は榶〔とう・わん〕を献じ、衛の国の人は柯〔か・わん〕を献じ、斉の国の人は皮革を献じた。土地の形勢が違っているとそれに使う器械や服飾もまた違わなければならない。だから中原の諸国は王者に同じように仕え、その制度も同じようにするが、蕃夷戎狄〔ばんいじゅうてき・四方の野蛮国〕の国は、同じように王者に仕えるが、その制度は異なるものである。
都を中心とした五百里四方以内の土地は、王の田を耕すことで仕え〔甸服(でんぷく)〕、方五百里以外の諸侯の土地は、王のために四方をうかがって、思いがけない災難に備えることによって仕え〔侯服〕、侯衛の地の諸侯は、お客の格式で仕え〔賓服〕、蕃夷の国は、好信(よしみ)を結ぶことで仕え〔要服〕、戎狄の国は、何の定めもなく仕える〔荒服〕。甸服の者は祭りごとに物を献じ、侯服の者は祀りごとに物を献じ、賓服の者は享(まつ)りごとに物を献じ、要服の者は歳毎に物を献じ、荒服の者はただ王として仕えるだけで何も献じない。
祭りごとに物を献ずるのは、朝廷の日々の祭に献ずることであり、祀りごとに献ずるのは、朝廷の月々の祀りに献ずることであり、享(まつ)りごとに献ずるのは、朝廷の四季の享りに献ずることであり、歳毎に献ずるのは、朝廷の歳ごとの祀りに献ずることであり、王として仕えるだけなのは、前の王がやめて新しい王が位に即くときに来朝することである。このようなことを土地の形勢を見てその使用する器械を定め習慣に従わせ、遠近を計ってその貢ぎ物を差別するというのである。これが王者の天下を治める制度である。
荀子 天論篇 第十七より 〔天人分離〕
天行有常、不為堯存、不為桀亡。應之以治則吉、應之以亂則凶。彊本而節用、則天不能貧;養備而動時、則天不能病;脩道而不貳、則天不能禍。故水旱不能使之飢、寒暑不能使之疾、祆怪不能使之凶。本荒而用侈、則天不能使之富;養略而動罕、則天不能使之全;倍道而妄行、則天不能使之吉。故水旱未至而飢、寒暑未薄而疾、祆怪未至而凶。受時與治世同、而殃禍與治世異、不可以怨天、其道然也。故明於天人之分、則可謂至人矣。

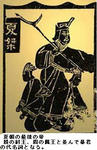 〔訳〕
〔訳〕
天道は常に変わることのないものである。尭のような立派な天子がいるから天道があるのでもなく、桀のような悪い天子がいるからなくなるものでもない。天道に対応してよい政治を行えば吉であり、悪い政治を行えば凶なのである。だから吉凶はすべて点に拠るのではなくて、人によるのである。農業生産に努力して費用を節約すれば、天でもその人を貧乏にすることは出来ず、異色が充分で適度に働いていれば、天もその人を病気にすることは出来ず、人の道に従ってたがわなければ、天もその人に禍を与えることは出来ない。
だから大水や日照りでも彼らを飢えさせることはできないし、非常な暑さや寒さも彼らを病気にさせることは出来ないし、妖怪変化も彼らを不幸にすることは出来ない。これに反して農業生産への努力もせず贅沢で浪費すれば、天でもその人を富ますことは出来ないし、衣食が不十分で、怠けて働かなければ、天でもその人を健康にすることは出来ないし、人の道にそむいてでたらめな生活をしていれば、天でもその人を幸福にすることは出来ない。だからまだ大水や日照りがやってこないうちからもう飢えるようになり、非常な暑さや寒さがまだやってこないのに、もう病気にかかり、妖怪変化もまだ現れないのに早くも不幸にあうのである。
乱世は平和な世と同じ天の下にありながら禍を受けることでは治世と異なっている。しかしこれは天を怨んではいけない。人がそうなるようなやり方をしているからである。だから天道と人道との区別をはっきり知っておれば、至人(最高の人)といえる。
天行有常、不為堯存、不為桀亡。應之以治則吉、應之以亂則凶。彊本而節用、則天不能貧;養備而動時、則天不能病;脩道而不貳、則天不能禍。故水旱不能使之飢、寒暑不能使之疾、祆怪不能使之凶。本荒而用侈、則天不能使之富;養略而動罕、則天不能使之全;倍道而妄行、則天不能使之吉。故水旱未至而飢、寒暑未薄而疾、祆怪未至而凶。受時與治世同、而殃禍與治世異、不可以怨天、其道然也。故明於天人之分、則可謂至人矣。
天道は常に変わることのないものである。尭のような立派な天子がいるから天道があるのでもなく、桀のような悪い天子がいるからなくなるものでもない。天道に対応してよい政治を行えば吉であり、悪い政治を行えば凶なのである。だから吉凶はすべて点に拠るのではなくて、人によるのである。農業生産に努力して費用を節約すれば、天でもその人を貧乏にすることは出来ず、異色が充分で適度に働いていれば、天もその人を病気にすることは出来ず、人の道に従ってたがわなければ、天もその人に禍を与えることは出来ない。
だから大水や日照りでも彼らを飢えさせることはできないし、非常な暑さや寒さも彼らを病気にさせることは出来ないし、妖怪変化も彼らを不幸にすることは出来ない。これに反して農業生産への努力もせず贅沢で浪費すれば、天でもその人を富ますことは出来ないし、衣食が不十分で、怠けて働かなければ、天でもその人を健康にすることは出来ないし、人の道にそむいてでたらめな生活をしていれば、天でもその人を幸福にすることは出来ない。だからまだ大水や日照りがやってこないうちからもう飢えるようになり、非常な暑さや寒さがまだやってこないのに、もう病気にかかり、妖怪変化もまだ現れないのに早くも不幸にあうのである。
乱世は平和な世と同じ天の下にありながら禍を受けることでは治世と異なっている。しかしこれは天を怨んではいけない。人がそうなるようなやり方をしているからである。だから天道と人道との区別をはっきり知っておれば、至人(最高の人)といえる。
荀子 臣道篇 第十三 より 〔暴虎馮河〕
仁者必敬人。凡人非賢、則案不肖也。人賢而不敬、則是禽獸也;人不肖而不敬、則是狎虎也。禽獸則亂、狎虎則危、災及其身矣。《詩》曰:「不敢暴虎、不敢馮河。人知其一、莫知其它。戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰。」此之謂也。故仁者必敬人。敬人有道、賢者則貴而敬之、不肖者則畏而敬之;賢者則親而敬之、不肖者則疏而敬之。其敬一也、其情二也。若夫忠信端愨、而不害傷、則無接而不然、是仁人之質也。忠信以為質、端愨以為統、禮義以為文、倫類以為理、喘而言、臑而動、而一可以為法則。《詩》曰:「不僭不賊、鮮不為則。」此之謂也。
恭敬、禮也;調和、樂也;謹慎、利也;鬥怒、害也。故君子安禮樂利、謹慎而無鬥怒、是以百舉而不過也。小人反是。
仁徳のある人は必ず人を敬う。一般に人は賢くなければ、愚かなものである。賢い人がいてもこれを敬わなければ、鳥や獣とおなじである。愚かな人がいてもこれを敬わなければ虎を侮るようなもので、必ず害を受けることになる。鳥や獣と変わりがなければ混乱し、虎を侮れば危害を受け、その災害は自分の身までおよんでくる。『詩経』(小雅・小旻篇)に「ことさら素手で虎をなぐらず、河を歩いてわたらず、人はこの危険をしっているけれども、その他の危険はしらない」とは、このことをいっているのである。
だから仁徳ある人は必ず人をうやまうのである。人を敬うのにやり方がある。賢者には尊敬し、愚かなものには警戒して敬う。賢者には親しんでそんけいし、愚かなものには疏遠にして敬う。その敬うことにあっては同じであっても、その意味はちがっている。敬う意味がちがっていてもまことで正しくまじめであって、危害を加えられず誰に対しても同じように敬うようになれば、これこそ仁徳ある人の本質なのである。まことを本質とし、ただしくまじめであることを本領とし、礼義を文飾に用い、人間関係や同類によって類推することを道理とするので、ほんの少しの言葉でもほんの少しの動きにもすべて法則とすることが出来るのである。『詩経』(大雅・抑篇)に「僭越にふるまわず危害を加えざれば、法則とならざること少なし」とあるのはこのことを言っているのである。
恭しく敬うのは礼義であり、調和するのは音楽である。謹み慎重であるのは利益であり、たたかい怒るのは損害である。だから君子は礼義に安んじ音楽を楽しみ、謹み慎重であることを利としてたたかい怒ることをしない。こういうわけであらゆる挙止動作には過ちがないのである。小人はこれと反対である。
荀子 非十二子篇 第六 より 〔禹行舜趨〕
士君子之容:其冠進、其衣逢、其容良;儼然、壯然、祺然、蕼然、恢恢然、廣廣然、昭昭然、蕩蕩然。是父兄之容也。其冠進、其衣逢、其容愨;儉然、恀然、輔然、端然、訾然、洞然、綴綴然、瞀瞀然。是子弟之容也。
打開字典顯示更多訊息 非十二子: 吾語汝學者之嵬容:其冠絻、其纓禁緩、其容簡連;填填然、狄狄然、莫莫然、瞡瞡然、瞿瞿然、盡盡然、盱盱然;酒食聲色之中、則瞞瞞然、瞑瞑然;禮節之中、則疾疾然、訾訾然;勞苦事業之中、則儢儢然、離離然、偷儒而罔、無廉恥而忍謑詬。是學者之嵬也。
打開字典顯示更多訊息 非十二子: 弟陀其冠、衶禫其辭、禹行而舜趨:是子張氏之賤儒也。正其衣冠、齊其顏色、嗛然而終日不言、是子夏氏之賤儒也。偷儒憚事、無廉恥而耆飲食、必曰君子固不用力:是子游氏之賤儒也。彼君子則不然:佚而不惰、勞而不僈、宗原應變、曲得其宜、如是然後聖人也。
〔訳〕
 士君の態度について。その冠は高く、その衣服はゆったりと、その容貌はなごやかであって、いかめしく、犯しがたく、安らかでのびのびと、度量が大きく、広々と、明るくおうようなのは、父兄として〔子弟にたいするときの〕態度である。その冠は高く、その衣服はゆったりと、その容貌は謹み深く、謙遜で、形うるわしく、親しげに、礼儀正しく、柔和で、恭しく、そむき離れず、ひかえめなのは、子弟として〔父兄に接するとき〕の態度である。
士君の態度について。その冠は高く、その衣服はゆったりと、その容貌はなごやかであって、いかめしく、犯しがたく、安らかでのびのびと、度量が大きく、広々と、明るくおうようなのは、父兄として〔子弟にたいするときの〕態度である。その冠は高く、その衣服はゆったりと、その容貌は謹み深く、謙遜で、形うるわしく、親しげに、礼儀正しく、柔和で、恭しく、そむき離れず、ひかえめなのは、子弟として〔父兄に接するとき〕の態度である。
私は君たちに学者の怪しげな態度について話そう。その冠は垂れ下がり、冠の紐はしどけなく緩み、その容貌は傲慢であって、さも得意げに、飛び回ったり、黙りこくったり、こせこせし、きょときょとし、しょげ込んだり、目を見張ったりし、酒食や音楽とか美人の前では、ことさら目を閉じて視て見ぬふりをし、礼節を守るべき場所では、人を憎々しげに罵りあい、骨の折れる仕事の時には、ずるけて身を入れず、投げやりで道理に暗く、恥知らずで、他人の非難を気に止めない。これが学者の怪しげなさまである。

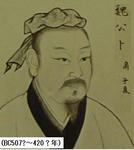

その冠を低くかぶり、その言うことはあっさりしていて、禹のような歩き方をし舜のように走るのは、これは子張の末流の儒者である。その衣服や冠をきちんと身につけ、顔色を整えて、控えめな態度で一日中物をいわないでいるのは、子夏の末流の儒者である。怠惰で仕事を嫌い、恥知らずで飲食を好み、きまって「君子はもともと労働しない」というのは、これは子游の末流の儒者である。
かの君子といわれる人はそうではない。安楽な境遇にいても怠けず、苦労なときにも気を緩めず、根本を守って変化に対応し、すべてその宜しきにかなっている。このようであってこそ初めて聖人ということが出来る。
士君子之容:其冠進、其衣逢、其容良;儼然、壯然、祺然、蕼然、恢恢然、廣廣然、昭昭然、蕩蕩然。是父兄之容也。其冠進、其衣逢、其容愨;儉然、恀然、輔然、端然、訾然、洞然、綴綴然、瞀瞀然。是子弟之容也。
打開字典顯示更多訊息 非十二子: 吾語汝學者之嵬容:其冠絻、其纓禁緩、其容簡連;填填然、狄狄然、莫莫然、瞡瞡然、瞿瞿然、盡盡然、盱盱然;酒食聲色之中、則瞞瞞然、瞑瞑然;禮節之中、則疾疾然、訾訾然;勞苦事業之中、則儢儢然、離離然、偷儒而罔、無廉恥而忍謑詬。是學者之嵬也。
打開字典顯示更多訊息 非十二子: 弟陀其冠、衶禫其辭、禹行而舜趨:是子張氏之賤儒也。正其衣冠、齊其顏色、嗛然而終日不言、是子夏氏之賤儒也。偷儒憚事、無廉恥而耆飲食、必曰君子固不用力:是子游氏之賤儒也。彼君子則不然:佚而不惰、勞而不僈、宗原應變、曲得其宜、如是然後聖人也。
〔訳〕
私は君たちに学者の怪しげな態度について話そう。その冠は垂れ下がり、冠の紐はしどけなく緩み、その容貌は傲慢であって、さも得意げに、飛び回ったり、黙りこくったり、こせこせし、きょときょとし、しょげ込んだり、目を見張ったりし、酒食や音楽とか美人の前では、ことさら目を閉じて視て見ぬふりをし、礼節を守るべき場所では、人を憎々しげに罵りあい、骨の折れる仕事の時には、ずるけて身を入れず、投げやりで道理に暗く、恥知らずで、他人の非難を気に止めない。これが学者の怪しげなさまである。
その冠を低くかぶり、その言うことはあっさりしていて、禹のような歩き方をし舜のように走るのは、これは子張の末流の儒者である。その衣服や冠をきちんと身につけ、顔色を整えて、控えめな態度で一日中物をいわないでいるのは、子夏の末流の儒者である。怠惰で仕事を嫌い、恥知らずで飲食を好み、きまって「君子はもともと労働しない」というのは、これは子游の末流の儒者である。
かの君子といわれる人はそうではない。安楽な境遇にいても怠けず、苦労なときにも気を緩めず、根本を守って変化に対応し、すべてその宜しきにかなっている。このようであってこそ初めて聖人ということが出来る。
荀子 非十二子篇 第六 より
假今之世、飾邪說、文姦言、以梟亂天下、矞宇嵬瑣使天下混然不知是非治亂之所在者、有人矣。
縱情性、安恣孳、禽獸行、不足以合文通治;然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾;是它囂魏牟也。
忍情性、綦谿利跂、苟以分異人為高、不足以合大眾、明大分、然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾:是陳仲史鰌也。
不知壹天下建國家之權稱、上功用、大儉約、而僈差等、曾不足以容辨異、縣君臣;然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾:是墨翟宋鈃也。
尚法而無法、下脩而好作、上則取聽於上、下則取從於俗、終日言成文典、反紃察之、則倜然無所歸宿、不可以經國定分;然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾:是慎到田駢也。
不法先王、不是禮義、而好治怪說、玩琦辭、甚察而不惠、辯而無用、多事而寡功、不可以為治綱紀;然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾;是惠施鄧析也。
略法先王而不知其統、猶然而猶材劇志大、聞見雜博。案往舊造說、謂之五行、甚僻違而無類、幽隱而無說、閉約而無解。案飾其辭、而祇敬之、曰:此真先君子之言也。子思唱之、孟軻和之。世俗之溝猶瞀儒、嚾嚾然不知其所非也、遂受而傳之、以為仲尼子弓為茲厚於後世:是則子思孟軻之罪也。
若夫總方略、齊言行、壹統類、而群天下之英傑、而告之以大古、教之以至順、奧窔之間、簟席之上、斂然聖王之文章具焉、佛然平世之俗起焉、六說者不能入也、十二子者不能親也。無置錐之地、而王公不能與之爭名、在一大夫之位、則一君不能獨畜、一國不能獨容、成名況乎諸侯、莫不願以為臣、是聖人之不得埶者也、仲尼子弓是也。一天下、財萬物、長養人民、兼利天下、通達之屬莫不從服、六說者立息、十二子者遷化、則聖人之得埶者、舜禹是也。
今夫仁人也、將何務哉?上則法舜禹之制、下則法仲尼子弓之義、以務息十二子之說。如是則天下之害除、仁人之事畢、聖王之跡著矣。
〔訳〕
当今の世に、邪説をつくろい姦言を飾り立てて天下をかき乱し、人を欺く誇大な言や奇怪でくだくだしい説をなして天下を混乱させ、是非・治乱の規準がいずれにあるかわからないようにさせる者がある。
性情をほしいままにして放縦(ほうしょう)に振舞い、禽獣のような行いで、とうてい礼義にかない治道に通ずることは出来ない。しかしながら、その主張するところは根拠があり、その弁舌は筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが它囂(たごう)と魏牟(ぎぼう)である。
性情を押し殺し、世に超然としてひとり己を潔くし、何事によらず人と異なるのを高尚と考えていて、到底多くの民衆を会合し礼の分(きまり)を明らかにすることは出来ない。しかしながら、その主張するところは筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが陳仲と史鰌(ししゅう)である。
 天下を統一して国家を建てるための準則を知らず、功利を、倹約を尊んで区別をなおざりにし、とても社会的な差別を設け、君臣上下の秩序を立てることは出来ない。しかしながら、その主張するところは根拠があり、その弁舌は筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが墨翟と宋鈃である。
天下を統一して国家を建てるための準則を知らず、功利を、倹約を尊んで区別をなおざりにし、とても社会的な差別を設け、君臣上下の秩序を立てることは出来ない。しかしながら、その主張するところは根拠があり、その弁舌は筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが墨翟と宋鈃である。
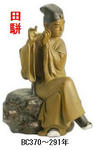 法の尊ぶべきことを強調しながら法を無視し、学問修養を軽蔑しながら好んで書物を著し、上は王侯に聴き入れられ、下は世俗に従われ、終日弁舌して立派な議論をするが、その言う所を詳らかに観察してみると、支離滅裂で帰着するところがなく、とても国家を治め上下の分(きまり)をたてることは出来ない。しかしながらその主張するところは根拠があり、その弁舌は筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが慎倒と田駢である。
法の尊ぶべきことを強調しながら法を無視し、学問修養を軽蔑しながら好んで書物を著し、上は王侯に聴き入れられ、下は世俗に従われ、終日弁舌して立派な議論をするが、その言う所を詳らかに観察してみると、支離滅裂で帰着するところがなく、とても国家を治め上下の分(きまり)をたてることは出来ない。しかしながらその主張するところは根拠があり、その弁舌は筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが慎倒と田駢である。
いにしえの聖王にのっとらず礼義をよしとせず、好んで不可解な説をなし奇異な言辞を弄し、はなはだ明察であるが急務ではなく、達弁であるがなんの用にもたたず、為すことは多いが実効に乏しく、とても政治の大本とすることは出来ない。しかしながら、その主張するところは根拠があり、その弁舌は筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが恵施(けいし)と鄧析(とうせき)である。
大方いにしえの聖王に則っているが、その根本を知らず、態度はゆったりしているが性質は激しく志は大きく、見聞は広いが粗雑である。上古の事を考えて自説をたて、それを五行と呼んでいるが、はなはだ片寄っていて規準がなく、奥深そうで説明がなく、要約だけで解説がない。それでいて言葉を飾り立て、それを慎み敬って、これこそ真に先君孔子の説だといっている。
 子思がこれを唱え、孟子がこれに和した。世俗の愚昧な儒者どもは、口喧しく論じたてるけれども、その謝っていることが分らない。そのまま受け伝えて、孔子と子游が後世に重んぜられるのも彼らのお陰と思い込んでいる。これこそ子思と孟子の罪である。
子思がこれを唱え、孟子がこれに和した。世俗の愚昧な儒者どもは、口喧しく論じたてるけれども、その謝っていることが分らない。そのまま受け伝えて、孔子と子游が後世に重んぜられるのも彼らのお陰と思い込んでいる。これこそ子思と孟子の罪である。
もし誰かが種々の方策を統べおさめ、言行を斉一にし、大小の法則を一定にし、そのうえ天下の優れた人物を集めて、真の大道を告げ、至順の徳を教えたならば、その人は家屋の内を出ず、敷物の上を離れずして、聖王のうるわしき教えがすっかり完備し、治世の風俗が勢いよく起こってくるであろう。そうなれば、先の六派の邪説は人心に入り込むことが出来ず、十二人の人々は近づくことも出来ない。かかる偉大な人は、たとい錐を立てるほどの領地すら持たなくても、王公もこれと名声を争うことはできず、また一大夫の位にあるときは、一君だけで召抱えることは出来ず、一国だけで留めおくことも出来ず、その盛名は諸侯に聞こえ、自分の臣下にと願わないものはない。これは聖人の勢位をえないもので、孔子と子弓とがそれである。
天下を統一し万物を成就し、人民を養育しあまねく天下を利し、交通の及ぶところでの人々で服従しないものはなく、先の六派の邪説は立ちどころに止み、十二人の者たちは感化されてしまう。このようなのは聖人の勢位をえたもので、舜と禹がそれである。
当今、仁人たるものは何を務めるべきであろうか。上は舜や禹の定めた制度にのっとり、下は孔子や子弓の行った道義にのっとり、これによって十二人の邪説を絶滅することに務めるべきである。そうしたならば天下の害毒は除かれ、仁人のなすべきことは終わり、聖王の治跡もはっきり現れるであろう。
假今之世、飾邪說、文姦言、以梟亂天下、矞宇嵬瑣使天下混然不知是非治亂之所在者、有人矣。
縱情性、安恣孳、禽獸行、不足以合文通治;然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾;是它囂魏牟也。
忍情性、綦谿利跂、苟以分異人為高、不足以合大眾、明大分、然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾:是陳仲史鰌也。
不知壹天下建國家之權稱、上功用、大儉約、而僈差等、曾不足以容辨異、縣君臣;然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾:是墨翟宋鈃也。
尚法而無法、下脩而好作、上則取聽於上、下則取從於俗、終日言成文典、反紃察之、則倜然無所歸宿、不可以經國定分;然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾:是慎到田駢也。
不法先王、不是禮義、而好治怪說、玩琦辭、甚察而不惠、辯而無用、多事而寡功、不可以為治綱紀;然而其持之有故、其言之成理、足以欺惑愚眾;是惠施鄧析也。
略法先王而不知其統、猶然而猶材劇志大、聞見雜博。案往舊造說、謂之五行、甚僻違而無類、幽隱而無說、閉約而無解。案飾其辭、而祇敬之、曰:此真先君子之言也。子思唱之、孟軻和之。世俗之溝猶瞀儒、嚾嚾然不知其所非也、遂受而傳之、以為仲尼子弓為茲厚於後世:是則子思孟軻之罪也。
若夫總方略、齊言行、壹統類、而群天下之英傑、而告之以大古、教之以至順、奧窔之間、簟席之上、斂然聖王之文章具焉、佛然平世之俗起焉、六說者不能入也、十二子者不能親也。無置錐之地、而王公不能與之爭名、在一大夫之位、則一君不能獨畜、一國不能獨容、成名況乎諸侯、莫不願以為臣、是聖人之不得埶者也、仲尼子弓是也。一天下、財萬物、長養人民、兼利天下、通達之屬莫不從服、六說者立息、十二子者遷化、則聖人之得埶者、舜禹是也。
今夫仁人也、將何務哉?上則法舜禹之制、下則法仲尼子弓之義、以務息十二子之說。如是則天下之害除、仁人之事畢、聖王之跡著矣。
〔訳〕
当今の世に、邪説をつくろい姦言を飾り立てて天下をかき乱し、人を欺く誇大な言や奇怪でくだくだしい説をなして天下を混乱させ、是非・治乱の規準がいずれにあるかわからないようにさせる者がある。
性情をほしいままにして放縦(ほうしょう)に振舞い、禽獣のような行いで、とうてい礼義にかない治道に通ずることは出来ない。しかしながら、その主張するところは根拠があり、その弁舌は筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが它囂(たごう)と魏牟(ぎぼう)である。
性情を押し殺し、世に超然としてひとり己を潔くし、何事によらず人と異なるのを高尚と考えていて、到底多くの民衆を会合し礼の分(きまり)を明らかにすることは出来ない。しかしながら、その主張するところは筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが陳仲と史鰌(ししゅう)である。
いにしえの聖王にのっとらず礼義をよしとせず、好んで不可解な説をなし奇異な言辞を弄し、はなはだ明察であるが急務ではなく、達弁であるがなんの用にもたたず、為すことは多いが実効に乏しく、とても政治の大本とすることは出来ない。しかしながら、その主張するところは根拠があり、その弁舌は筋道だっていて、愚昧な民衆を欺き惑わすのにじゅうぶんである。これが恵施(けいし)と鄧析(とうせき)である。
大方いにしえの聖王に則っているが、その根本を知らず、態度はゆったりしているが性質は激しく志は大きく、見聞は広いが粗雑である。上古の事を考えて自説をたて、それを五行と呼んでいるが、はなはだ片寄っていて規準がなく、奥深そうで説明がなく、要約だけで解説がない。それでいて言葉を飾り立て、それを慎み敬って、これこそ真に先君孔子の説だといっている。
もし誰かが種々の方策を統べおさめ、言行を斉一にし、大小の法則を一定にし、そのうえ天下の優れた人物を集めて、真の大道を告げ、至順の徳を教えたならば、その人は家屋の内を出ず、敷物の上を離れずして、聖王のうるわしき教えがすっかり完備し、治世の風俗が勢いよく起こってくるであろう。そうなれば、先の六派の邪説は人心に入り込むことが出来ず、十二人の人々は近づくことも出来ない。かかる偉大な人は、たとい錐を立てるほどの領地すら持たなくても、王公もこれと名声を争うことはできず、また一大夫の位にあるときは、一君だけで召抱えることは出来ず、一国だけで留めおくことも出来ず、その盛名は諸侯に聞こえ、自分の臣下にと願わないものはない。これは聖人の勢位をえないもので、孔子と子弓とがそれである。
天下を統一し万物を成就し、人民を養育しあまねく天下を利し、交通の及ぶところでの人々で服従しないものはなく、先の六派の邪説は立ちどころに止み、十二人の者たちは感化されてしまう。このようなのは聖人の勢位をえたもので、舜と禹がそれである。
当今、仁人たるものは何を務めるべきであろうか。上は舜や禹の定めた制度にのっとり、下は孔子や子弓の行った道義にのっとり、これによって十二人の邪説を絶滅することに務めるべきである。そうしたならば天下の害毒は除かれ、仁人のなすべきことは終わり、聖王の治跡もはっきり現れるであろう。
荀子は非十二子篇第六で、十二人の思想家を非難し、孔子・子弓、舜帝・禹王を顕彰している。その十二人とは――




〔道家・快楽説批判〕生まれつきの感情のままに振る舞って放縦をよいことにし、鳥や獣のように行動して、その結果として、礼義にかなった秩序のある生活ができない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応筋道がたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが它囂と魏牟である。
〔道家・無欲説批判〕生まれつきの感情をおしころし、世間から超然として、ほんの少しでも人々に異説を唱えることを良いことと考え、その結果として、一般の人々と一緒になって、基本的な秩序をわきまえた生活をすることがとうていできない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応筋道がたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが陳仲と史鰌である。
〔墨家批判〕全世界を統一し国家を安定させるための基準である礼を知らないで、功利実用を尊び、倹約を重んじ、しかも、秩序のための差別を無視する。そこで、その結果として、社会的な階層の差別を容認して、君臣間の秩序を立てることができない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応すじみちがたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが墨翟と宋鈃である。
〔法家批判〕法令を尊びはするものの、理想的な王の定めた法を無視し、教育修養を軽視しながら、新たにことを始めることを好み、上は君主に厚遇されることを願い、下は世間からもよく言われたいと無理をしている。終日説きつづけて立派なことをいってみても、それを繰り返しよく調べてみると、実際とかけ離れて支離滅裂で論旨に統一がなく、それによって国家を運営し社会秩序を立てることはとうていできない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応筋道がたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが慎到と田駢である。
〔名家批判〕古代の理想的な王の教えを模範とせず、社会の根本規範をよしとせず、好んであやしげな説をまなび、奇怪な言辞をもてあそび、きわめて分析的だが不必要で、あれこれ説きたてるがさっぱり役に立たず、多くの仕事に手を出すがさっぱり成果があがらず、それらを国政を秩序立てる根本原理とすることはできない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応筋道がたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが恵施と鄧析である。
〔儒家・子思孟子批判〕おおよそは古代の理想的な王の教えの模範としてはいるが、その政治の根本理念はわきまえず、みかけはゆったりしているが、激しい気性で野望は大きく、知識は広いが雑然としており、古い昔のことに照らして自分の学説をつくりあげ、それを五行と呼んでいる。だが、それはきわめてよこしまな説で、規範がなく、曖昧模糊としていて深くは解き明かされておらず、ぶっきらぼうで具体的な解説をしていない。そのくせことばを飾り立てもったいを付け、「これこそほんとうのむかしの理想的な人物、孔子のことばである」と主張する。孔子の孫の子思がこれを言い出し、孟軻がそれを支持した。世間の暗愚な儒者たちは、口やかましくさわぎたてるが、それがまちがいであることが分からないでいる。あげくのはてに、それをまに受けて伝えるようになり、孔子と子游とは子思と孟軻によって後世に重んぜられるようになったのだと考えている。このようなことは、つまり、子思と孟軻が犯した罪悪である。
〔道家・快楽説批判〕生まれつきの感情のままに振る舞って放縦をよいことにし、鳥や獣のように行動して、その結果として、礼義にかなった秩序のある生活ができない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応筋道がたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが它囂と魏牟である。
〔道家・無欲説批判〕生まれつきの感情をおしころし、世間から超然として、ほんの少しでも人々に異説を唱えることを良いことと考え、その結果として、一般の人々と一緒になって、基本的な秩序をわきまえた生活をすることがとうていできない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応筋道がたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが陳仲と史鰌である。
〔墨家批判〕全世界を統一し国家を安定させるための基準である礼を知らないで、功利実用を尊び、倹約を重んじ、しかも、秩序のための差別を無視する。そこで、その結果として、社会的な階層の差別を容認して、君臣間の秩序を立てることができない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応すじみちがたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが墨翟と宋鈃である。
〔法家批判〕法令を尊びはするものの、理想的な王の定めた法を無視し、教育修養を軽視しながら、新たにことを始めることを好み、上は君主に厚遇されることを願い、下は世間からもよく言われたいと無理をしている。終日説きつづけて立派なことをいってみても、それを繰り返しよく調べてみると、実際とかけ離れて支離滅裂で論旨に統一がなく、それによって国家を運営し社会秩序を立てることはとうていできない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応筋道がたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが慎到と田駢である。
〔名家批判〕古代の理想的な王の教えを模範とせず、社会の根本規範をよしとせず、好んであやしげな説をまなび、奇怪な言辞をもてあそび、きわめて分析的だが不必要で、あれこれ説きたてるがさっぱり役に立たず、多くの仕事に手を出すがさっぱり成果があがらず、それらを国政を秩序立てる根本原理とすることはできない。とはいうものの、自説を主張できるだけの理由はあり、その発言は一応筋道がたっていて、愚昧な民衆を欺きまどわすにはじゅうぶんである。このようなのが恵施と鄧析である。
〔儒家・子思孟子批判〕おおよそは古代の理想的な王の教えの模範としてはいるが、その政治の根本理念はわきまえず、みかけはゆったりしているが、激しい気性で野望は大きく、知識は広いが雑然としており、古い昔のことに照らして自分の学説をつくりあげ、それを五行と呼んでいる。だが、それはきわめてよこしまな説で、規範がなく、曖昧模糊としていて深くは解き明かされておらず、ぶっきらぼうで具体的な解説をしていない。そのくせことばを飾り立てもったいを付け、「これこそほんとうのむかしの理想的な人物、孔子のことばである」と主張する。孔子の孫の子思がこれを言い出し、孟軻がそれを支持した。世間の暗愚な儒者たちは、口やかましくさわぎたてるが、それがまちがいであることが分からないでいる。あげくのはてに、それをまに受けて伝えるようになり、孔子と子游とは子思と孟軻によって後世に重んぜられるようになったのだと考えている。このようなことは、つまり、子思と孟軻が犯した罪悪である。
今日はブログ集18のプリント・製本で1日を過した。
 西宮のYK氏から、例年の通り、朝倉の志波柿を送ってきた。かれは、朝倉の地が斉明天皇崩御の地であることに因んで、この志波柿を「斉明柿」と名付けている。
西宮のYK氏から、例年の通り、朝倉の志波柿を送ってきた。かれは、朝倉の地が斉明天皇崩御の地であることに因んで、この志波柿を「斉明柿」と名付けている。
斉明天皇6年(660年)7月に百済が唐と新羅によって滅ぼされると、斉明天皇は難波などを経て斉明天皇7年(661年)3月25日に娜大津(現在の福岡市博多区)の磐瀬行宮(いわせのかりみや)に入り、5月9日に朝倉橘広庭宮に遷して、百済復興の戦に備えた。しかし、7月24日に朝倉宮で崩御。朝倉橘広庭宮に都が置かれたのはわずか2か月余りということになる。
 朝倉橘広庭宮の所在地は、現在の福岡県朝倉市とされるが、具体的な場所は特定されていない。朝倉市大字須川には、奈良時代の寺院跡である長安寺廃寺跡が残っており、「橘廣庭宮之蹟」の碑が建てられている。
朝倉橘広庭宮の所在地は、現在の福岡県朝倉市とされるが、具体的な場所は特定されていない。朝倉市大字須川には、奈良時代の寺院跡である長安寺廃寺跡が残っており、「橘廣庭宮之蹟」の碑が建てられている。
『日本書紀』は、朝倉橘広庭宮の建設に際して、朝倉社の木を切って用いたために、神が怒って宮殿を壊し、宮中では鬼火が目撃され、大舎人らに病死者が続出したと伝え、皇太子の哀悼歌を載せている。
「是(ここ)に、皇太子、一所(あるところ)に泊(は)てて、天皇を哀慕(しの)ひたてまつりたまふ。乃(すなわち)口號(くちうた)して曰(のたま)はく、
君が目の 恋(こほ)しきからに 泊(は)てて居(ゐ)て かくや恋ひむも 君が目を欲(ほ)り〔ただあなたの目が恋いしいばっかりにここに舟泊りしていて、これ程恋しさに耐えないのも、あなたの目を一目みたいばかりなのです〕」(日本書紀より)
斉明天皇6年(660年)7月に百済が唐と新羅によって滅ぼされると、斉明天皇は難波などを経て斉明天皇7年(661年)3月25日に娜大津(現在の福岡市博多区)の磐瀬行宮(いわせのかりみや)に入り、5月9日に朝倉橘広庭宮に遷して、百済復興の戦に備えた。しかし、7月24日に朝倉宮で崩御。朝倉橘広庭宮に都が置かれたのはわずか2か月余りということになる。
『日本書紀』は、朝倉橘広庭宮の建設に際して、朝倉社の木を切って用いたために、神が怒って宮殿を壊し、宮中では鬼火が目撃され、大舎人らに病死者が続出したと伝え、皇太子の哀悼歌を載せている。
「是(ここ)に、皇太子、一所(あるところ)に泊(は)てて、天皇を哀慕(しの)ひたてまつりたまふ。乃(すなわち)口號(くちうた)して曰(のたま)はく、
君が目の 恋(こほ)しきからに 泊(は)てて居(ゐ)て かくや恋ひむも 君が目を欲(ほ)り〔ただあなたの目が恋いしいばっかりにここに舟泊りしていて、これ程恋しさに耐えないのも、あなたの目を一目みたいばかりなのです〕」(日本書紀より)
プロフィール
ハンドルネーム:
目高 拙痴无
年齢:
93
誕生日:
1932/02/04
自己紹介:
くたばりかけの糞爺々です。よろしく。メールも頼むね。
sechin@nethome.ne.jp です。
sechin@nethome.ne.jp です。
カレンダー
| 12 | 2026/01 | 02 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新コメント
[enken 02/23]
[中村東樹 02/04]
[m、m 02/04]
[爺の姪 01/13]
[レンマ学(メタ数学) 01/02]
[m.m 10/12]
[爺の姪 10/01]
[あは♡ 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
[Mr.サタン 09/20]
最新トラックバック
ブログ内検索
カウンター
